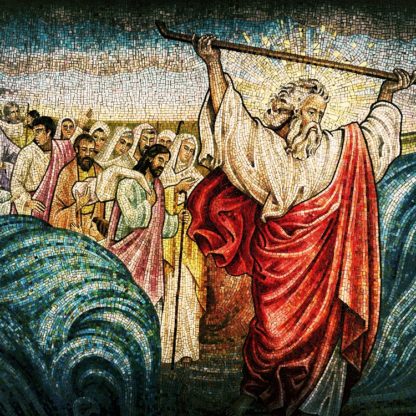2025年7月20日説教「求めよ。探せ。叩け」松本敏之牧師
歴代誌下6:12~21 マタイによる福音書7:7~14
(1)本気で祈り求める
先ほど読んでいただいた歴代誌下の言葉と、マタイ福音書の言葉は、本日の日本基督教団の聖書日課であります。詩編交読の詩編143編もそうです。これらの聖書日課に共通することとして「祈り」というテーマが掲げられています。
主イエスは、こう語られました。
「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも、求める者は受け、探す者は見つけ、叩く者には開かれる。」マタイ7:7~8
私たちは、まず、この言葉を素直に聞きたいと思います。一生懸命祈って求めれば、必ずそれが通じるということです。私たちは「だめもと」(だめでもともと)で祈ることがいかに多いことでしょう。祈らないよりは祈ったほうがましだという程度の気持ちです。しかしそれは、神様が全能であり、不可能を可能にする方であることを信じないで祈っていると言えないでしょうか。
(2)真夜中に友人にパンを求める人の話
この言葉は、ルカ福音書にも出てくるのですが、ルカ福音書では、この言葉が語られる前に、「真夜中に友達を訪ねて、パンを求めた人の話」が記されています。
「あなたがたのうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。『友よ、パンを三つ貸してください。友達が旅をして私のところに着いたのだが、何も出すものがないのです。』すると、その人は家の中から答えるに違いない。『面倒をかけないでくれ。もう戸は閉めたし、子どもたちも一緒に寝ている。起きて何かあげることなどできない。』しかし、言っておく。友達だからということで起きて与えてはくれないが、執拗に頼めば、起きて来て必要なものを与えてくれるだろう。」ルカ11:5~8
まして神は、もっとよいお方である。私たちの心からの願いを聞いてくださらないはずがない、ということです。
(3)ヤコブの格闘
執拗に食い下がる他の聖書の話として思い起こすのは、旧約聖書、創世記のヤコブ物語です。ヤコブはアブラハムの孫、イサクの息子です(創世記32:23~33)。ヤコブは、長い間は伯父ラバンのもとで過ごすのですが、兄エサウのもとから逃げておりました。いつかはそこへ帰っていかなければならないという状況です。そのところで、この世的な準備、できることはすべてしながら、どうしても不安が消えない。そうした中、真夜中に(こちらの話も真夜中です)、謎の相手と格闘技をするのです。この相手が誰であるのか謎のままです。しかしこの謎の相手が言ったことによれば、「あなたは、神と闘い、人々と闘って勝った」(32:29)とありますので、何かしらの神の力を帯びた存在であったのでしょう。そこでその相手に「放してくれ。夜が明けてしまう」(32:27)と言わせるのです。お互いにもう疲れたから、もうこの辺で終わりにしよう」と言うことでしょう。その時、ヤコブは「いいえ、祝福してくださるまでは放しません」(32:27)と食い下がるのです。相手は「あなたの名はもはやヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる」(33:29)と告げます。ヤコブという名前には「かかとをつかむ者」という否定的な意味合いがありましたが、「神が支配される」という意味のイスラエルという祝福された名前を、受け取るのです。これもしつように食い下がって、祝福を勝ち得た話でありましょう。主イエスは、「叩け、そうすれば、開かれる」と言って、「しつこく食い下がるほど祈りなさい」と教えられたのです。
(4)そのまま聞かれるとは限らない
しかし「求めなさい。そうすれば、与えられる」とは、「欲しい物は何でも私たちの思い通りに手に入る」ということではありません。
神様が私たちのわがままな祈り、たとえば極端なことを言えば、「あの国を滅ぼしてください」とか、「私をこの国の支配者にしてください」とかいうような祈りに、そのまま応えられる方であるならば、それこそ恐ろしいことです。この世界は、とっくの昔に滅んでいるのではないでしょうか。
神は、私たち以上に、私たちに何が必要であるかをご存じです。イエス様は神と私たちの関係を親子にたとえて、こう言われました。
「あなたがたの誰が、パンを欲しがる自分の子どもに、石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに、蛇を与えるだろうか。」マタイ7:9~10
しかし考えてみてください。もしもこれが逆で、私たちのほうで、パンだと思って、知らずして石を求めているとすれば、どうでしょうか。魚だと思って、蛇を求めているとすれば、どうでしょうか。その時には、「はい、石をあげましょう。蛇をあげましょう」というのではなく、むしろ石や蛇が与えられないことのほうが恵みであると思います。真剣な祈りは必ず聞かれます。しかし私たちの求めとは違った形で応えられることもあるのです。
「求めなさい。そうすれば、与えられる」(マタイ7:7)。この約束を信じ、正直に自分の願いを主の前に差し出すことが大切です。それをしないと、私たちの中で祈りがくすぶって、不完全燃焼になってしまうのではないでしょうか。私たちも、祈りがきかれていないように思える時でも、とにかくこの祈りは届いている、と信じたいと思います。
(5)最もふさわしい時と形
それでは、どうして祈りがすぐにこたえられないことがあるのでしょうか。それは祈りがこたえられるには、それに最もふさわしい時と、最もふさわしい形があるからです。私たちの期待している時に、私たちが期待している形で、祈りがきかれるとは限りません。主は私たちの熱い思いを受けとめつつ、最もよい時と、最もよい形を選ばれます。
神様は、しばしば時を延ばされます。それはどうしてかと言えば、すべての人間的可能性が終わり、ここから先はもう神様の可能性でしかないということがわかるため、つまり私たちが神様に栄光を帰するためではないでしょうか。
(6)ダビデの祈り、ソロモンの祈り
今日は、旧約聖書は、歴代誌下6章12節以下を、読んでいただきました。ここはソロモン王の祈りです。ソロモン王というのはイスラエルのダビデの息子で、ダビデの次の王様です。これは、エルサレム神殿奉献の祈りです。エルサレム神殿というのは、神の臨在を示すものです。もともとは十戒の板を収めた「契約の箱」が神の臨在を示すものでした。出エジプトの旅の間は、それを幕屋で安置したのですが、約束の地に入った後は、聖所で保管されました。そしてダビデの時代に、それを収める神殿を建てる計画が立てられるのです。しかしダビデの時代にはそれが実現しませんでした。そしてその息子ソロモンの時代にそれは実現することになります。ダビデの祈りは聞かれたけれども、まだその時ではなかったということができるでしょう。神様は、しばしば時を延ばされるのです。先ほど読んでいただいた歴代誌下6章の少し前のところ、7節以下にこう記されています。
「父ダビデは、イスラエルの神、主の名のために神殿を建てようと志していた。だが、主は父ダビデにこう仰せになった。『あなたは私の名のために神殿を建てようと志してきた。その志は立派である。しかし、神殿を建てるのはあなたではなく、あなたから生まれた息子である。彼が私の名のために神殿を建てるであろう。』主は約束されたことを実現された。主が約束されたとおり、私は父ダビデに代わって立ち、イスラエルの王座に着いた。そしてイスラエルの神、主の名のためにこの神殿を建て、そこに主の契約の箱を置いた。その契約は、主がイスラエルの人々と結ばれたものである。」歴代誌下6:7~11
そして、先ほど読んでいただいたような祈りが始まるのです。このソロモンの祈りは、なかなか優れたものです。ソロモンは、こう祈りました。
「神は果たして人間と共に地上に住まわれるでしょうか。天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの神殿などなおさらです。」歴代誌下6:18
ソロモンの神殿はとても豪華な、きらびやかなものであったそうです。この言葉はソロモンの謙虚さを表しています。私たちは、イエス・キリストが野の花をさして、「栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった」という言葉で、逆にソロモン王の神殿の豪華さを想像することができます。ソロモンの祈りは、こう続きます。
「わが神、主よ、あなたの僕の祈りとその願いを顧みてください。……ここは、あなたが、そこにご自分の名を置くと仰せになった所です。……あなたの僕がこの所に向かって献げる願いを聞き入れてください。あなたは住まいである天からそれを聞いてください。聞いてお赦しください。」歴代誌下8:19~21
このようなソロモンの祈りを読むときに、ダビデの願いは、世代を超えてようやくソロモンの時代になって形になった、実現したということを思うのです。
(7)私の恵みはあなたに十分である
しかし神様は時を延ばされるだけではなく、祈りが聞き入れられないということもあります。少なくとも、形の上では、聞き入れられない、しかしそれでもその祈りは聞かれていたということを信じたいと思うのです。
聖書の中で、それを経験したのは、使徒パウロでした。パウロは何かはっきりとは記されていないのですが、伝道者としては致命的な欠点のようなものを抱えていたようです。パウロはそれを「棘」と呼んでいます。パウロは、こう述べています。
「(私は、あまりに多くの啓示を受けたため)、それで思い上がることのないように、私の体に一つの棘が与えられました。それは、思い上がらないように、私を打つために、サタンから送られた使いです。この使いについて、離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。ところが主は、『私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中で完全に現れるのだ』と言われました。」コリント二12:7~9
この棘が何であったのか。さまざまな説があります。目がかなり悪かったのではないか。使徒言行録9章に、ダマスコへ行く途中で、いったんパウロの目が見えなくなったことが記されています。その後、アナニアを通して再び見えるようになるのですが、完全に戻ったわけではないのではないかという説。パウロは、手紙をすべて口述筆記で、別の誰かに書かせていました。ガラテヤの信徒への手紙の最後のところで、こう述べています。
「御覧のとおり、私はこんなに大きな字で、自分の手であなたがたに書いています。」ガラテヤ6:11
しかし実は、パウロは目が悪くて、大きな字しか書けなかったのではないかというのです。あるいは、パウロは今日の言葉で言うところの、「てんかん持ち」であったのではないかという説もあります。その他にも幾つかの節があるのですが、いずれにしろ、伝道者として活動していくには致命傷に思えたのです。しかし「それを取り除いてください」というパウロの願いはかなえられませんでした。しかし祈りが聞かれなかったわけではありませんでした。
神さまの答えはこうでした。「私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中で完全に現れるのだ。」自分に自信があって活動する時には自己完結して、かえってキリストに頼らなくてもいいと思ってしまう危険性があります。パウロはこう言うのです。
「だから、キリストの力が私に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ、私は弱さ、侮辱、困窮、迫害、行き詰まりの中にあっても、キリストのために喜んでいます。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。」コリント二12:9~10
これは、パウロが得た認識でした。パウロがこうした認識に至ることができたのも、パウロが真剣に何度も祈ったからと言えるでしょう。そうでなければ、「私の恵みはあなたに対して十分である。力は弱さの中で完全に現れるのだ」という声も聞くことがなかったでしょう。パウロの祈りは聞かれていた。パウロの求めていたものとは、別の形ではありましたが、答えが与えられたのです。
神さまは、私たちの祈りをお聴きくださいます。そして答えてくださいます。その答えは、私たちの求めているものと違うかもしれません。しかし、私たち以上に、私たちに何が必要であるかをご存じの神様が、私たちにふさわしい答えをしてくださるということを信じて祈り求めていきたいと思います。