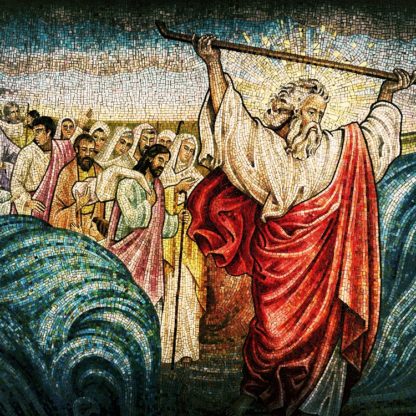2023年9月17日説教「神の愛」松本敏之牧師
ルカによる福音書15章11~24節
(1)「失われた息子」のたとえ
先ほど読んでいただいたルカによる福音書15章11節から24節は、本日の日本基督教団の聖書日課の前半です。本来は、週報にも記載しています32節までなのですが、少し長いので、後半は11月頃に改めて取り上げたいと考えています。
これはルカによる福音書のクライマックスとでも言うべきものです。「放蕩息子のたとえ」として知られていますが、「放蕩」という日本語は、最近では、聖書のこの箇所以外ほとんど使われないのではないでしょうか。
「放蕩」とは、ウィキペディアでは、こう説明されていました。
「(放蕩とは)自分の思うままに振る舞うことであり、やるべきことをやらず自分のやりたい放題にして、家の財産などを蕩尽することである。特に、酒にふけったり、女遊びにふけったりすることを指すことが多い。」
このたとえは、ルカ福音書15章の前半にある「見失った羊」のたとえと「無くした銀貨」のたとえに続くものであり、共通するテーマを扱っています。そのことを思えば、「失われた息子のたとえ」と呼ぶほうがふさわしいと思いますし、弟息子の放蕩を強調するよりは、「失われたものが戻ってきた」ということ、そして「一緒に喜んでください」ということを語ることこそが中心であると思います。
(2)財産の生前分与
物語はこう始まります。
「ある人に息子が二人いた。弟のほうが父親に、『お父さん、私に財産の分け前をください』と言った。それで、父親は二人に身代を分けてやった。」ルカ15:11~12
いわゆる財産の生前分与です。これは今日でも、よく行われることでしょう。父親が死んでしまってからでは、どうなるかわからない(兄弟争いが起こるかもしれない)から、最初からきちんと分けておこう。その場合は、むしろ親のほうから言う場合が多いかもしれません。
しかしこの時の状況はそうではありませんでした。その後を見ると、弟はそれを処分して、お金に換え、そのお金をもって故郷を出て行くのです。
鹿児島加治屋町教会にも来てくださったことのある聖書学者の山口里子さんは、『イエスの譬え話1 ガリラヤ民衆が聞いたメッセージを探る』(新教出版社)という本の中で、この物語を扱っておられます。なかなか興味深い、そして刺激に満ちたものです。
山口里子さんによれば、「財産」には二重の意味がある。それは所有権と処分権です。弟息子が要求した「財産」(の分け前)と、父が与えた「身代」は、別の言葉(ギリシア語)が用いられている。最初の「財産」(ousia)は「所有財産・資産」という意味、父が与えた「身代」(bios)は「いのち・生活」という意味があります。通常は、息子はたとえ分与されて「所有権」を与えられたとしても、「処分権」は父の死までは与えられず、その日から父の死まで、父親も息子も、勝手に財産を売ることができなくなるというのです。
「何日もたたないうちに、弟は何もかもまとめて遠い国へ旅立ち、そこで身を持ち崩して財産を無駄遣いしてしまった。」ルカ15:13
「何もかもまとめて」というのは、新共同訳では「全部を金に換えて」となっていました。聖書協会共同訳では、注のところで、別訳「全部を金に換えて」と書いてありました。もしもそうだとすれば、彼は実質的には財産の「所有権」だけではなく、「処分権」をも望んでいた。これは、父の死を望んでいるようなものなので、通常であれば、父はこの要求を退けるでしょう。しかしこの父は彼の希望どおりにしてやるのです。
またこの時、兄は何も語っていませんが、本来であれば、父に対して、弟にその要求をやめさせるようにするか、それとも弟にそう告げるか、どちらかでしょう。しかし彼はそれをせずに、兄もここでその財産を受け取ったように記されています(「それで、父親は二人に身代を分けてやった」)。つまり、兄も兄としての責任を果たしていないということが、ここから少し読み取れます。
(3)弟息子の放蕩の果て
弟息子は、好き放題のことをしたのでしょう。それこそが彼のあこがれていた生活でした。小さい頃から、いつも兄の下に置かれてきました。兄からも厳しく言われてきたかもしれません。ようやく自由を手にしたのです。最初のうちはうれしくて仕方がなかったことでしょう。友だちもいっぱいできました。少なくとも彼のほうではそう思っていました。男友だちも女友だちも。しかしそれは彼の勘違いでした。みんなは、彼の財産、彼のお金が目当てであったのです。
働いていないわけですから、お金は減る一方です。もしかすると、彼もそれを元手に事業でも起こそうと考えて出立したかもしれません。しかし世間はそう甘くはなかった。
そして運の悪いことにひどい飢饉が起こります。彼はそこでこそ、友人たちが助けてくれるものと思ったかもしれませんが、それも甘かった。彼に財産がなくなると、友人たちは手のひらを返したように去っていきました。ひどい仕打ちをしたり、ひどい言葉を投げかけたりもしたかもしれません。彼は「食べるにも困り始めた」(14節)。どんどん落ちぶれて、とうとうどん底にまでいたったのです。
彼は、その地方に住むある人のところに身を寄せます。その人は、彼を畑にやって豚の世話をさせました。この記述から、その人がユダヤ人ではないこと、その地域が異邦人の住む地域であったことがわかります。ユダヤ人は豚を食べないからです。この弟息子は、家を出た時、ユダヤ人のコミュニティーからも去り、できるだけ違う世界へ行きたいと思ったのかもしれません。
(4)2種類のいなご豆
「彼は、豚の食べるいなご豆で腹を満たしたいほどであったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。」ルカ15:16
このところでも山口里子さんの解説は興味深いものでした。「いなご豆」には、二つの種類があったというのです。ひとつは、さやが果肉のようにふっくらとして人間が食べられるもの。それはおいしくはないが食べることができて、栄養もあるそうです。この弟息子の故郷では、このタイプのいなご豆があり、彼はこれを知っていたというのです。ところが豚飼いの仕事をしていた時に目の前にあった「いなご豆」は別の種類、牧草地に生える野生の黒いいなご豆で、「トゲだらけ」です。人間が食べられるものではなかった。
豚はそれにかぶりつきますが、人間は食べられない。たとえ食べても苦いもので、栄養もない。それでもこの弟息子は、野生のトゲトゲのいなご豆に、豚がかぶりつくのを見て「自分も食べたい」と思ったのでしょう。けれどもとても食べられるものではないし、たとえ食べたとしても、トゲだらけで苦くて栄養もないし、空腹を満たすことはできなかったわけではありません。
豚がいやがらせをして、「人間のお前にはやらないよ」と言ったのではありません。もしかすると、「おいそこの人間、よかったら一緒に食べないか。ぶーぶー。」位言ったかもしれません。「いや、硬そうなので遠慮しときます」というような会話か、そのような目配せはあったかもしれません。
「食べ物をくれる人は誰もいなかった」というのは、人々に物乞いまでしたけれども無駄であったということでしょうか。豚飼いをしていたならば、その報酬として何らかのものを得ていたと思われます。飢饉のおり、安い労働力があふれ、わずかの報酬しか得られなかったのかもしれません。
もっとも豚飼いたちは、主人が食べ残したものや主人が食べない豚の臓器など何らかのおこぼれにあずかることはできたと思います。しかし彼はユダヤ人としての自覚が残っていて、他の人は食べていても、彼はそれを食べることはできなかったのかもしれません。いやむしろそういうところでこそ、自分はユダヤ人であることを思い起こし、「家に帰ろう」という気持ちを起こしたことも考えられます。
(5)我に返って
そこで彼は「我に返る」のです。
「父のところには、あんなに大勢の雇い人がいて、有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここをたち、父のところに行って言おう。『お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。』」ルカ15:17~19
彼は何と言えば、受け入れてもらえるか、一生懸命考えたのでしょう。こう言えばどうか、ああ言えばどうか、と考えた末の言葉のようです。この言葉にはそういう熟考の跡がうかがえます。そしてこの言葉を携えて、故郷の家へ向かいます。道中、この言葉を暗誦するように、何度も口にしたかもしれません。
「我に返って」(17節)というのが、心からの悔い改めであった、ということも考えられますし、ただ生き延びるためにはそうするしかなかった、ということも考えられます。そのどちらかは最後まで定かではありませんが、いずれにしろ父親のところへ帰っていきます。
(6)憐れに思い
「ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。」ルカ15:20
この父親の姿は、とても印象的です。普通では考えにくい。彼が行動に出たのは、弟息子が悔い改めの言葉を語ったからではありません。息子が用意してきた言葉を語る前です。自分のほうから走り寄って、息子を抱きしめるのです。しかもこの父親が遠く離れているのに、息子を見つけたというのは、その瞬間としては偶然かもしれませんが、息子が帰ってくるかもしれないと思って、外に出ては遠くを眺め、待ち続けたのではないでしょうか。
弟息子は、父親の抱擁と接吻が一段落するのを待って、落ち着いてから、自分が用意してきた言葉を語り始めました。
「私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。」ルカ15:21
彼には、その後に一番言おうと思っている言葉がありました。それは「雇い人の一人にしてください」という言葉でした。しかしその言葉を父親は語らせません。それを語る前に、父親は僕たちに言うのです。
「『急いで、いちばん良い衣を持って来て、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を引いて来て屠りなさい。食べて祝おう。この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。』そして、祝宴を始めた。」ルカ15:22~24
(7)小山晃佑『富士山とシナイ山』
この父親の姿、これは聖書に現れている神様の姿を表しています。そしてそれは新約聖書で突然始まったのではなく、実は、旧約聖書以来、この神の姿が中心的な聖書のメッセージです。
私のニューヨーク・ユニオン神学大学時代の恩師の小山晃佑先生は、1984年に『富士山とシナイ山』という著書を英語で出版されました(”Mt. Fuji and Mt. Sinai”)。これは小山先生の主著とでもいうべきものですが、30年の時を経て、2014年秋に、この本の日本語訳が出版されました(教文館)。私は、この日本語版の書評を依頼されて、日本語でこれを読み直したのですが、改めて、これが歴史的意義のある彼の主著であることを改めて思いました。 (この書評は、鹿児島加治屋町教会のホームページの「牧師の部屋」の「書評」コーナーにも置いていますので、どうぞご覧ください。)
この本の主題は、まさに神の愛、神の熱情的な愛、というものであります。情熱的な愛、と言ってもよいのですが(その方が自然な日本語でもあるのですが)、情熱的な愛だと、男と女の愛を思い浮かべてしまいますし、一時の情熱で、その後は冷めてしまうと受け取られかねないので、あえて「神の熱情的な愛」としておきましょう。それはどこまでも冷めない。どこまでも人間を見放さないで追いかけてくる愛です。アブラハム・ヘシェルというユダヤ教学者が、『人間を探し求める神』という本を著していますが、小山先生もしばしばこの言葉を用いられました。
何かの折に、小山先生が冗談半分でおっしゃったことをよく覚えています。「神様はエデンの園からアダムとエバを追放した時に、『これでエデンも平和になる』と言って、エデンの園に鎮座したのではなく、アダムとエバを追放した時に、一緒にエデンの園を出てきてしまったのです。だから聖書はこんなに分厚いのです。そうでなかったら、聖書は最初の4頁で終わっていたでしょう。聖書のほとんどの部分は、エデンの園の外の物語です。」
(8)ホセア書11章の「神の愛」
小山先生が、神の熱情を語るのにしばしば用いられたのが、ホセア書11章の言葉でした。ホセア書11章の初めに「神の愛」という小見出しがついています。私も大好きな箇所です。よかったらお開きください。旧約聖書1396頁です(聖書協会共同訳)。
「まだ幼かったイスラエルを私は愛した。 私はエジプトから私の子を呼び出した。 しかし、私が彼らを呼んだのに 彼らは私から去って行き バアルにいけにえをささげ 偶像に香をたいた。 エフライムの腕を支え 歩くことを教えたのは私だ。 しかし、私に癒されたことに 彼らは気付かなかった。」ホセア11:1~3
せっかくそのようにかわいがって世話をしてやったのに、「エフライム」、「イスラエル」は不信仰のゆえに自ら滅びようとしている。その「エフライム」「イスラエル」に向かい、「どうしてあなたを引き渡すことができようか」「どうしてあなたを明け渡すことができようか」と言います。そしてこう言うのです。
「私の心は激しく揺さぶられ 憐れみで胸が熱くなる。」ホセア11:8
これが神の熱情的な愛の姿です。聖書の中で最も重要で、最も深い言葉の一つだと私は思っています。 放蕩息子の父親もまさに、この言葉の通りの姿ではなかったでしょうか。息子を放っておくことができない。心配で、心配で、仕方がないのです。たとえ自業自得であったとしても、どん底の状態になろうとも、この父親は、「いても立ってもいられない」のです。
ホセアはこう続けます。
「私は神であって、人ではない。 あなたのただ中にあって、聖なる者。 怒りをもって臨むことはない。」ホセア書11:9
神様は、「私は神であって、人ではない」と宣言されました。しかしその宣言の意味することは、私たちの考えることと少し違っているのではないでしょうか。普通は「神であって、人間ではない」、ということは、人間を超越していて、何があっても動じない。人間が滅んでいこうとも動じない。びくともしない、ということを想像するのではないでしょうか。しかしここではそうではないというのです。
「私は神であって、人ではない」と言いながら、人間のことが心配で心配でたまらない。おろおろしている。そして人間に近づいてくるのです。「人間を探し求める神」です。そこにむしろ神の愛の本質が現れてくる。この父親の姿も、そういう神の熱情的な愛を指し示しているのです。