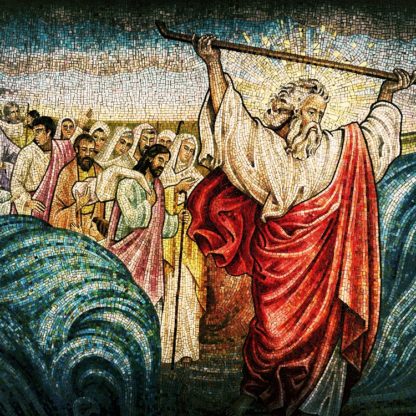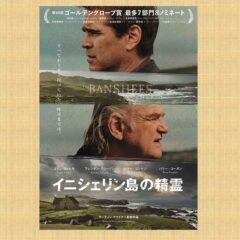2025年1月19日説教「宣教の開始」松本敏之牧師
イザヤ書8:23~9:6
マタイによる福音書4:12~22
(1)洗礼者ヨハネの逮捕と死
先ほどお読みいただいたマタイによる福音書4章12節から22節は、日本基督教団の本日と来週の2回分の聖書日課です。(ただ23節以下は省略しました。)
この箇所は、イエス・キリストが悪魔との対決を終えて、いよいよ公の宣教活動に入られるところです。
最初に洗礼者ヨハネが捕らえられたことが記されていますが、彼が捕らえられたのには、こういういきさつがありました。
この当時ガリラヤ地方を治めていたのは、ヘロデ・アンティパスという領主です。彼にはすでに妻がいましたのに、自分の兄の妻に恋をして、彼女を奪ってしまいました。その女性の名前はヘロディア、その娘がサロメです。洗礼者ヨハネは大胆にも、「あの女と結婚することは律法で許されていない」とヘロデ・アンティパスを追及したために、捕らえられたのでした。
やがてヨハネはこの家族にもてあそばれるように、殺されていきます。ヘロデの誕生日にサロメがみんなの前で踊りを踊るのですが、それをたいそう気に入ったヘロデは、サロメに「褒美に何でも好きなものをやろう」と約束してしまいます。母親ヘロディアの入れ知恵により、サロメは「洗礼者ヨハネの首を盆に載せて、この場でください」と言い、ヘロデはみんなの前で約束した手前、その通りにしたのでした(マタイ14:1~12参照)。
洗礼者ヨハネは、人々の罪を責め、悔い改めを叫び求めました。彼は正義に生き、正義に死にました。ただこのことは、イエス・キリストが十字架にかけられる時も全く同じであったことを忘れてはならないでしょう。その意味では、洗礼者ヨハネは、言葉の面だけではなく、その歩みにおいても、イエス・キリストの先駆けであったと言えるでしょう。そしてイエス・キリストがそれと同じ歩みをすることによって、洗礼者ヨハネの生と死をしっかりと受け止め、引き受けておられると言ってもよいと思います。
(2)端っこから始まる
イエス・キリストの宣教活動はガリラヤ地方で始まります。それはマタイによれば、イザヤ書8章23節~9章1節の言葉の成就でした。
「ゼブルンの地とナフタリの地、
湖沿いの道、ヨルダンの川の向こう
異邦人のガリラヤ、
闇の中に住む民は
大いなる光を見た。
死の地、死の陰に住む人々に
光が昇った。」マタイ4:15~16
ゼブルンとナフタリというのは、もともとヤコブの息子たちの名前ですが、その後ユダヤ部族の名前となりました。そしてこの部族が住んだ北ガリラヤ全体を指す地名にもなっていました。「湖沿い」の「湖」というのはガリラヤ湖のことです。ガリラヤ地方は、エルサレムのあるユダヤ地方から見れば、田舎です。田舎の田舎で、異邦人とまじって住んでいる汚れたところと思われていました。とてもそこからメシア(救い主)が現れるとは思えない。暗闇の地です。しかしマタイは、「主イエスの宣教は、中心エルサレムではなく、このガリラヤの田舎から始まった」と告げたのです。「周辺(端っこ)から中心へ」というのは、イエス・キリストの活動や生涯にも、通じることです。王様の宮殿ではなく、馬小屋でお生まれになったことも、そうでありましょう。
(3)夜中の11時と12時
さて17節にこう記されています。
「その時からイエスは、『悔い改めよ、天の国は近づいた』と言って、宣べ伝え始められた。」マタイ4:17
イエス・キリストの宣教の初めの言葉です。この「悔い改めよ、天の国は近づいた」という言葉は、実は洗礼者ヨハネが語ったのと全く同じ言葉でした。洗礼者ヨハネは、マタイ福音書3章2節のところで、「悔い改めよ。天の国は近づいた」と告げています。
その同じ言葉で宣教を始めるということは、イエス・キリストは、洗礼者ヨハネの活動を引き継がれたということでしょう。ヨハネが捕らえられた時に、主イエスはそれを引き継いで、宣教活動を始められたのでした。ヨハネが公の宣教活動を終えたところから、イエス・キリストの公の活動が始まる。洗礼者ヨハネの活動と主イエスの活動は連続していたのです。
しかし二人の語った言葉が同じであり、二人の活動の間にこうした連続性があったとしても、二人の間には大きな違いがありました。ある人はそれを「夜中の11時と12時のような違いだ」と言いました。今は夜で、同じように朝を待っています。ところが11時と12時ではすでに日付けが変わっています。ヨハネはもうすぐ来る、といことで悔い改めを呼びかけました。明日来るものとして待っていたものが、主イエスが活動を始められたことによって、すでに今日のこととなりました(「アスクル」が「キョウクル」?になった)。
洗礼者ヨハネは、いわば「天の国は近づいた」と、天を指して叫んだのですが、イエス・キリストは、ご自分で天の国をもたらすために来られたからであります。イエス・キリストがおられるところに、すでに天の国、神の国が始まっているからです。
ルカ福音書17章20節以下に、このように記されています。
「ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスはお答えになった。『神の国は、観察できるようなしかたでは来ない。「ここにある」とか、「あそこにある」と言えるものでもない。実に、神の国はあなたがたの中にあるからだ。』」ルカ17:20~21
「あなたがたの中にある」というのは、「心の中」という意味ではありません。新共同訳聖書では、「あなたがたの間にある」と訳されていました。「あなたがたの真ん中に、私がいるだろう。それがまさに神の国(天の国)が来ているということだ」と言おうとされたのでしょう。
ですから、話を今日のテキストに戻しますと、イエス・キリストが「悔い改めよ。天の国は近づいた」と言われるのは、すでに来ていることとして告げておられる。ヨハネが告げた時から、象徴的に言えば、日付が変わり、すでに今日のことになった、ということです。
天の国が近づいた時に、私たちがしなければならないことは悔い改めです。悔い改めとは、神様に向かって方向転換することです。また悔い改めとは、洗礼を受ける時に、一生に一度だけすればよいものではなく、全生涯をかけて絶えずするものです。私たちの心は放っておくと、すぐに神様から離れてしまうからです。
(4)「時」を逸しないように
さて、イエス・キリストが宣教活動の初めになさったことは、弟子たちを呼び集める(召し集める)ことでした。
「イエスは、ガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが、湖で網を打っているのを御覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、『私に付いて来なさい。人間をとる漁師にしよう』と言われた。」マタイ4:18~19
この時、「二人はすぐに網を捨てて従った」(マタイ4:20)とあります。彼らがどうしてこんなにすぐに従うことができたのか、よくわかりません。イエス・キリストの声が特別であったのか。顔が輝いていたのか。あるいは何か不思議なことをなさったのか。もしかすると、彼らは以前からイエス・キリストを知っていたのかもしれません。しかし、ここには何も書いてありません。ただマタイは本質的なことだけを記しました。それは主が彼らに呼びかけ、彼らはそれに従ったということです。
私たちが主に従うのは、突き詰めてみれば、そういうことではないでしょうか。余分なことをそぎ落としていけば、そうなると思います。別に論理的理由などないのです。主イエスは、今も私たちに対しても、私たち一人ひとりに向かって、「私に付いて来なさい」と呼びかけておられるのではないでしょうか。その声に「はい」と言って、従っていく時に、私たちの人生は、そこから変わっていきます。しかしその声に気づかないでいる時、あるいは無視している時、私たちの人生とイエス・キリストは、交差しません。何事もなかったかのごとく、再びだんだん遠く離れていってしまいます。
(5)青年、壮年、老年
加藤常昭牧師は、この箇所の説教で興味深い話を紹介しておられます。
「若い者は、主の求めを聞くと、こう言いがちである。ちょっと待ってください、わたしはまだ若いのです。決心するには若すぎます。正しい決心をするには、まだ十分な人生経験を踏んではいないのです、と。中年になるとこう言うのです。主よ、お言葉はよく分かります。しかし、御覧のように今わたしはこの生活に打ち込んでおります。間もなくこの生活から離れるのです。その時、改めて考えます。ところが年を取りますと、こう言うのです。主イエスよ、わたしは今からあなたに従うには、あまりにも年を取りすぎました。今更この人生を変えることはできません。もっと若かったら別ですが、と」加藤常昭説教全集1『マタイによる福音書1』219頁
冗談のようでもありますが、笑うに笑えない話です。私たちは、主の招きを断ろうと思えば、いつもそれなりの言いわけをもっているということでしょう。
ペトロとアンデレの後に、主イエスはゼベダイの子ヤコブとヨハネにも呼びかけられました。彼らも漁師でした。彼らには父親がいました。彼らの父親の面倒をみなければならなかったかもしれません。「父親がいますから」と断ることもできたでしょう。しかし彼らは「舟と父を残して」、イエスに従いました。家族のきずなが、主に従う決心を鈍らせることもあると思います。まず主に従って生きる決心をすること、その決心をするのは今だ、ということです。
(6)従う中で信仰を学ぶ
福音書を読んでいると、興味深いことに気づかされます。それは、イエス・キリストへの服従は、イエス・キリストに対する信仰告白に先立つということです。
イエス・キリストがシモンとその兄弟アンデレにかけられた言葉は、「私を信じなさい」ではなく、「私に付いて来なさい」でした。私たちは、信じてから従うのではなく、従う中で信仰を学ぶのです。シモン・ペトロが信仰の告白をしたのは、ずっと後のことでした。
マタイ福音書16章13節以下に、こういう記事があります。
イエスは、フィリポ・カイサリア地方に行かれた時に、弟子たちに「人々は、人の子を何者だと言っているか」とお尋ねになりました。「人の子」というのは、イエス・キリストご自身のことです。弟子たちは、口々に、いろんな応答をしました。その後、「それでは、あなたがたは私を何者だと言うのか」(マタイ16:15)と切り込んでこられました。それに対して、シモン・ペトロはこう答えました。
「あなたはメシア、生ける神の子です。」マタイ16:16
これは、人類最初のイエス・キリストへの信仰告白の言葉だと言えますが、このシモン・ペトロの信仰告白は、最初にガリラヤ湖畔でイエス・キリストに従ってから、大分日が経っています。彼は従っていく中で、少しずつ、自分が従っている方が誰であるかを悟っていったと言えるでしょう。
ボンヘッファーは、こう言うのです。
「信じるならば、第一歩を踏み出せ! その第一歩がイエス・キリストに通ずるのである。信じないならば、同じく一歩を踏み出せ。……あなたが信じているか信じていないかを問う問いは、あなたにゆだねられているのではない。従順の行為こそあなたに命じられている……のである。その行為においてこそ、信仰が可能となり、また信仰が現実に存在する状況は与えられるのである。」ボンヘッファー『キリストに従う』47頁
興味深い言葉です。今、言ったように、信じてから従うのではなくて、従う中で、信じられるようになってくるのです。洗礼を受ける時にも、私は、必ずしも信仰の確信がもてなくてもよいのだと思います。信じたいという気持ちがあれば、十分でしょう。求められるのは、信じること以前に従うことです。そして従う中で、信じるということもわかってくるのだと思います。