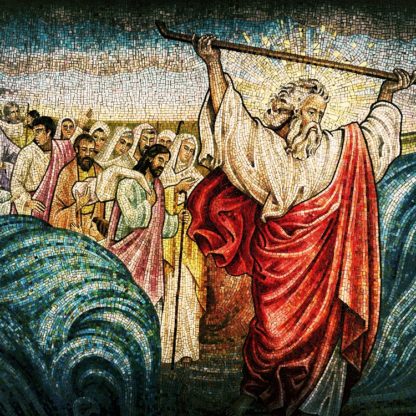2022年9月25日説教「彼女の記念として」松本敏之牧師
マルコによる福音書14章1~9節
(1)だまして捕える
今日は、日本キリスト教団の本日の聖書日課から、御言葉を聞いていきたいと思います。
マルコによる福音書は、この第14章から受難物語に入っていきます。このように始まります。
「さて、過越祭と除酵祭の二日前になった。祭司長たちや律法学者たちは、どのようにイエスをだまして捕え、殺そうかと謀っていた。」マルコ14:1
「だまして」と訳された言葉は、新共同訳聖書では「計略を用いて」という言葉でした。その前の口語訳聖書では「策略をもって」でした。しかし原語のニュアンスは、「だまして」「道を曲げて」という意味合いが近いです。「だまして」というほうがリアルでわかりやすい感じがします。それをわざわざ「計略を用いて」とか「策略をもって」と訳していたのは、イエス・キリスト自身がだまされることはありえないからでしょう。では一体誰をだますのか。それは民衆でしょう。あるいは裁判官の立場に着くことになるピラトでしょう。今日の政治家にも通じるものがあります。国民をだます政治家、あるいはだまそうとして同じ答弁を繰り返したり、策略をしたりする政治家を思い起こさせます。国民をだまして、特定の政治家、しかもあやしい過去をもつ政治家を、それを検証もせずに、類例のない偉い人であるかのように祭り上げる政治家集団があることを思います。
マルコ福音書はこう続きます。
「彼らは、『祭りの間はやめておこう。民衆が騒ぎ出すといけない』と話していた。」マルコ14:2
民衆をだますのにも、国民をだますのにもタイミングがあるのですね。すんなりだまされてくれる時をねらわなければならない。そうでないと、デモを起こされたり、暴動を起こされたりしかねない。一般民衆のほうからすればだまされないように、目を光らせていなければならないでしょう。だまされていることに気づいた時には、取り返しのつかないことになっているかもしれないからです。
受難物語に関しては、このわずか数日後に、民衆はまんまとだまされて、イエス・キリストは捕えられてしまうことになります。
(2)ナルドの香油を注ぐ
しかし受難物語は、この短いプロローグに続いて、美しいナルドの香油の物語を記しています。
「イエスがベタニヤで、既定の病を患っているシモンの家にいて、食事の席に着いておられたとき、一人の女が、純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。」マルコ14:3
「既定の病」と訳された言葉は、新共同訳聖書では「重い皮膚病」でした。聖書協会共同訳では、巻末の用語解説に「既定の病」も出ていますので、どうぞそれをご覧ください。この規定の病を患っていた人について、はっきりしていることは健康な人から遠ざけられて、差別されていたということはありました。今日の箇所は、イエス・キリストは、そのように差別を受けていた人の家に入られて、しかも食事を共にしておられたということに意義があると思います。
そこへ一人の女性が近づいてきます。食卓に着いておられる主イエスに近寄り、突然石膏の壺を割り、香油を注いだというのです。ナルドの香油というのは、「インド原産の甘松(かんしょう)から作った香油。ヘレニズム・ローマ世界で愛用され、富裕のユダヤ人の間にも人気があった」とのことです。
彼女がなぜそれをもっていたのかはわかりませんが、彼女のしたことは、思いつきでできるようなことではありません。恐らく彼女にとって、この香油はかけがえのないものであったに違いありません。彼女はすでにどこかでイエス・キリストと出会い、自分の人生が根本から揺さぶられ、新たに生きる経験をしたのでしょう。そして「自分もこの方のために何かをしたい。自分にできることは何か。自分の大切な宝物をささげること。自分の宝物といえば、あの香油以外にない」ということになったのではないでしょうか。
(3)彼女の行動の意味
では彼女の行為には、いったいどういう意味があったのでしょう。まず、頭に香油を注ぐ行為は、古代近東では何らかの特別な役割、あるいは任務への選びを意味していたと言われます。王はその戴冠式の一部としてしばしば油を注がれました。預言者にも、ときにその儀式が行われました(サムエル記上10:1、同16:13)。そういう意味からすれば、この女性は知らずして、イエス・キリストを王として認める油注ぎをした、ということができるでしょう。さらに言えば、キリストという言葉は、もともと「油注がれた者」という意味でした(ヘブライ語でマシアハ、旧約聖書ではメシア)。つまりこの女性のイエスに油を注ぐという行為は、「この方こそ、キリスト(油注がれた者)である」と象徴的に宣言しているとも言えます。名前も知られていない女性、匿名の女性に、メシアの戴冠式をさせるというのは、いかにもイエス・キリストにふさわしいのではないでしょうか。
もう一つは主イエスご自身が語っておられるように、彼女は、前もって主イエスの体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしたということです。当時、人が死ぬとその死体が臭くならないように香油をかけたそうですが、それをあらかじめこの女性がしたというわけです。
彼女は自分の行為の意味について考えてはいなかったでしょうが、イエス・キリストが彼女の心をしっかりと受け止めて、ご自分の計画の中で意味づけと位置づけをされたのです。
(4)ある人々の反応
彼女の突飛に見える行為に対してその場にいた人々はどうしたでしょうか。憤慨してこう言いました。
「何のために香油をこんなに無駄にするのか。この香油は三百デナリオン以上に売って、貧しい人々に施すことができたのに。」マルコ14:4~5
この言葉だけを取り出してみれば、間違ってはいません。なかなか立派なことを言っています。問題はその人の本当の心はどこにあるのか、その立派な言葉の陰に、果たしてその人の心があるのかということです。全く正しいことを語っていても、それが的外れになることがあり得るのです。
この女牲が高価な香油の入った石膏の壺を割ったとたん、その場にいた人々は、恐らく瞬間的に「なんともったいない!」と思ったのでしょう。しかしイエス・キリストの手前、そうは言えないので、もっともらしい言葉に整えて語ったのではないでしょうか。実際にそのように貧しい人に尽くしていたわけではないでしょう。
(5)ブラジルでの経験
私はブラジルで働いていたとき、1998年9月、貧しい教会の家庭集会でこの物語を読みました。10月の総選挙を控え、街中が選挙運動でにぎやかな時でした。その日の聖書研究会にスエリーという女性がいました。彼女は4人の子どもを女手ひとつで育てており、当時36歳で、すでに孫がいる人でした。定職はなく、日雇いで家政婦の仕事をしていました。
このスエリーが聖研の中でぽつりと言いました。「この人々の言ったことは、今の州議員候補とまるでおなじだ。『貧しい人のために何々をする』と言いながら、してくれたためしがない」。彼女はもうそういう発言を信じてはいません。彼女は、この人々の言葉の中に、そうした政治家の公約と同じ何かしらを感じたのです。「いつも貧しい者を引き合いに出して格好いいことを言いながら、結局心の中では自分のことを考えているのではないか」。それが実際に貧しい人の生の声でした。私は彼女の直感はなかなか鋭いと思いました。
(6)イエス・キリストの応答
この女性とその場にいた人々、もしも議論すれば、彼女はおそらく負けたでしょう。しかし彼らの言葉に比べて、この女性の行為には深い愛情があり、心がこもっていました。 イエス・キリストはこう言われます。
「するままにさせておきなさい。なぜ、この人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなたがたと一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし、私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり、前もって私の体に香油を注いで、埋葬の準備をしてくれた。」マルコ14:6~8
主イエスは彼らの優等生的な言葉を聞きながら、その一般的な真理性は否定されませんでした。それでいてそこに彼らの心がないことを見破っておられました。しかしその言葉を退けるのではなく、それよりも上に、その言葉の上に、この女性の行為を置かれたのです。彼女の深い愛情、真実な心を受け取られたのでした。同時にその場にいた人々にも、「確かにあなたがたの言うとおりだ。貧しい人にそうしてあげなさい」と暗に告げられたのです。さすがだと思います。
私たちは正しい言葉を正しい言葉として受け止めつつ、その背後に潜む偽善や、自己正当化を見抜く訓練をしなければならないと思います。だまされないようにしなければならない。
教会の中においても、正しい言葉を語りながら、時に意識的に、時に無意識のうちに、いかに人を裁いていることが多いことでしょう。聖書の言葉でさえも、神様のみ心と反対の行動を正当化するために使われることもあります。ですから、気をつけなければなりません。聖書の言葉で人をだますこともある。戦争をしかけ、相手を力でねじ伏せながら、それを聖書の言葉でもって正当化し、「神よ、この国を祝福してください」と祈ることもありうるのです。
(7)砂漠の中のオアシス
イエス・キリストは言われました。
「よく言っておく。(これは「アーメン」という言葉です)。世界中どこでも、福音が宣べ伝えられる所では、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。」マルコ14:9
人間の罪というものをいやというほど見せつけられるような受難物語の中で、この物語は私たち人間の側で、イエス・キリストに対してなし得た美しい奉仕として、砂漠の中のオアシスのごとく、忽然とたち現れます。この物語のすぐ後では、またユダの裏切りが出てくるので、この物語は砂漠の中のオアシスのようです。
マタイ福音書では、「ある人々」は「弟子たち」となっています。彼らが同じように言ったかどうかはともかくとして、その場にいたことには違いありません。後に弟子たちは、使徒として立派な伝道者となった時に、この事件を赤面の思いで振り返ったのではないでしょうか。しかしそれと同時に、弟子の誰もが主イエスに対して無理解であり、最後には全員が逃げ出してしまったような中で、せめて彼女だけでも、よくぞ主イエスに対して心のこもった行為をしてくれたと感謝したのではないでしょうか。彼女はその場にいた人たちにしかられながらも、はからずも弟子たちの代表として、いや私たち人間の代表として、主に対し埋葬の準備をしたのです。だからこそ、代々の教会によって「記念として」語り継がれることになったのだと思います(9節)。主イエスはそれを預言なさったのです。