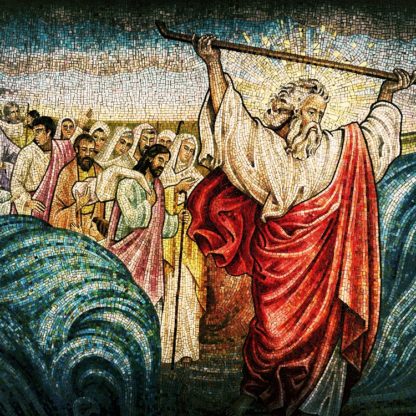2025年4月27日説教「手を携えて、歩もう共に」松本敏之牧師・奏楽椎名雄一郎
ミカ書6章1~8節 エフェソの信徒への手紙4章25~32節
(1)今年度の主題
今年度、鹿児島加治屋町教会では、「手を携えて、歩もう共に」という年間主題を掲げて歩み始めています。今日は、この言葉を説教題に掲げました。そして、この主題にちなんで、旧約聖書、新約聖書、それぞれから年間聖句を定めました。それを含めた前後の聖書個所を、今日のテキストとしました。
「手を携えて、歩もう共に」という年間主題には、二重の意味が込められています。
(2)私たちの交わり
一つは、教会に来ている私たち自身が交わる機会を多くし、さらに信頼を深めていきたいということです。私たちは昨年度、「礼拝に集い、主を賛美しよう」という年間主題を掲げて歩んできました。そこには、コロナ禍の長いトンネルを抜け出して、対面で礼拝に集えることを喜び、心から賛美歌を歌いたいという思いが込められていました。礼拝の長さも少しこれまでよりも長くし、信徒研修会では、礼拝についての学びもいたしました。
今年は、もちろんそうした思いは継続しながらでありますが、お互いがもっと親睦を深めていきたいと思っています。先週はイースターの愛餐会を、幼稚園のホールにて行うことができました。ホールを用いての愛餐会は、コロナ禍以降、初めてでありましたので、5年ぶり位かなと思います。とても楽しい、すてきな愛餐会となりました。5月21日に行われるシオン会主催の野外礼拝も、みんなが親睦を深める大事な時となるでしょう。シオン会以外の方々もぜひご参加いただき、楽しい思い出を共有していきたいと思います。
また今年度は月に一度、愛餐会か茶いっぺ会のどちらかを行うことにいたしました。茶いっぺ会は、一部の人が準備や片付けをするのではなく、多くの方にかかわっていただきたいと願って、ボランティアを募ることにしました。ロビーに茶いっぺ会の年間日程表を貼り出しています。自分ができそうなところに、4人くらいを目処に、ぜひお名前を書いていただきたいと思います。また準備もできるだけ簡単にできる形にしたいと思っています。詳しくは全体の係りの大迫さんにお尋ねください。
(3)愛し合い、赦し合う共同体
そのような親睦を深めつつ、信頼も深めていきたいと願っています。困っている人があれば、助け合いたいと思います。困っている人がいないか、気にかけていただきたいと思います。また交わりが増え、仲がよくなったら、逆に傷つけてしまうこともあるかもしれません。そういうことのないように配慮していきたいですし、傷つけてしまうようなことがあっても、祈りあい、愛の心で赦しあいたいと思います。そうした思いで、新約聖書の年間聖句は、次の言葉を選びました。
「互いに親切で憐れみ深い者となり、神がキリストにおいてあなたがたを赦してくださったように、互いに赦し合いなさい。」エフェソ4:32
この言葉のもとになっている言葉を、イエス・キリストも語られました。
「私があなたがたを愛したように、互いに愛し合いなさい。」ヨハネ15:12
私たちの交わりの土台にイエス・キリストの愛があります。それを思い起こしつつ、それを模範にしつつ、お互いに配慮しあい、赦しあう共同体を形成していきましょう。今回の年間聖句の前の部分にも、興味深い言葉が並んでいます。
「怒ることがあっても、罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはなりません。」エフェソ4:26
これも面白い言葉です。怒ることは仕方のないこととして、ある程度は、認められているのでしょう。私にも、本当に怒りたくなる時があります。でも度を越してはいけない。それで罪を犯してはいけないというのです。「こいつめ」と思うことも、時々あります(ほんの時々ですが)。でも、「そこで抑えておけ」ということなのでしょう。「怒ることがあっても、罪を犯してはいけない。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。」このことは、むしろ私たち自身の心の健康を保つために必要なことなのでしょう。夜はぐっすり眠りなさい、ということなのです。パウロは、ローマの信徒への手紙の中で、「悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。」(ローマ12:21)と勧めています。 エフェソの信徒への手紙の年間聖句の直前のところでは、こういうことも語っています。
「悪い言葉を一切口にしてはなりません。口にするなら、聞く人に恵みが与えられるように、その人を造り上げるために必要な善い言葉を語りなさい。神の聖霊を悲しませてはなりません。あなたがたは、聖霊によって、贖いの日のために証印を受けたのです。恨み、憤り、怒り、わめき、冒涜はすべて、一切の悪意と共に捨て去りなさい。」エフェソ4:29~31
そして私たちの年間聖句です。
「互いに親切で憐れみ深い者となり、神がキリストにおいてあなたがたを赦してくださったように、互いに赦し合いなさい。」エフェソ4:32
そのような愛に満ちた教会、共同体を成していきましょう。
(4)公正を行い、慈しみを愛する
さて、「手を携えて、歩もう共に」という言葉には、そうした私たち自身の交わりの他に、教会を超えたところでの人たちと手を携えて歩みたい、ということがあります。日本国内外の災害の被災者のことも視野に入れて、共に歩んでいきたいと思います。
社会委員会では、さっそく、ミャンマーの地震の被災者を覚えて、募金活動を始めました。皆さんのご協力をお願いします。
そのような自然災害だけではなく、いや自然災害よりももっと大事なことは、憎み争うことのない世界を築いていくために、祈り、働いていきたいということです。自分たちがよければ、それでよいということではありません。また私たち、日本の歩みが他の国の人々の生活を圧迫していないかということも考えていきたいと思います。
もう一つの年間聖句は、旧約聖書ミカ書の言葉ですが、そうしたことを考えながら選びました。
「人よ、何が善であるのか。 そして、主は何をあなたに求めておられるか。 それは公正を行い、慈しみを愛し へりくだって、あなたの神とともに歩むことである。」ミカ6:8
これは旧約聖書の中でも、特に大事な言葉です。私の、ニューヨーク・ユニオン神学校の恩師である小山晃佑先生は、この言葉を座右の銘のように大事にしておられました。
預言者ミカは、この直前で、こう述べています。
「主の正義の御業を考えてみよ。 何をもって主にまみえ いと高き神にぬかずくべきか。一歳の子牛か。 果たして、主は幾千の雄羊 幾万のしたたる油を喜ばれるだろうか。 私は自らの背きの罪のために長子を 自らの罪のために 胎から生まれた子を献げるべきか。」ミカ6:6~7
自らそう問うのです。ここに掲げられたものは、大きな犠牲の献げものです。しかしもっと大事なことがあるだろう。それが欠けていたのでは、どんなに大きな献げものをしようとも、神様は喜ばれない、というのです。そして、こう語ります。
「人よ、何が善であるのか。 そして、主は何をあなたに求めておられるか。 それは公正を行い、慈しみを愛し へりくだって、あなたの神とともに歩むことである。」ミカ6:8
ぜひ、この言葉を覚えていただきたいと思います。
(5)「勝利をのぞみ」
年間聖句の「手を携えて、歩もう共に」という言葉は、実は『讃美歌21』471番「勝利をのぞみ」という賛美歌の3節の歌詞の冒頭の言葉です。
「手をたずさえて 歩もう共に、勝利のときまで ああ、その日を信じて われらは進もう」
という言葉です。1節は、こうです。
「勝利をのぞみ 勇んで進もう 大地ふみしめて ああ、その日を信じて われらは進もう」
この歌は、1960年代にアメリカ合衆国の公民権運動のテーマソングのようになった歌です。1963年8月28日、ワシントンD.C.に、20万人以上の人が集まり、人種差別撤廃を求める大規模デモ行進、いわゆるワシントン大行進が行われました。マーティン・ルーサー・キング牧師が「私には夢がある」(I Have a Dream)という有名な演説をしたことでも知られています。このワシントン大行進において、ジョン・バエツというフォークソング歌手が、この「勝利をのぞみ」(We Shall Overcome)を歌いました。
We shall Overcome, we shall overcome We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe, We shall overcome someday.
直訳すると、こんな感じでしょうか。
「私たちは勝利する 私たちは勝利する 私たちは勝利する、いつの日か。 心の奥深いところで、私は信じる 私たちはいつの日か勝利すると」
「手をたずさえて 歩もう共に」の部分の原歌詞はこうです。
We’ll walk hand in hand, we’ll walk hand in hand, We’ll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe, We shall overcome someday.
直訳するとこんな感じでしょうか。
「私たちは手をたずさえて歩む 私たちは手をたずさえて歩む 私たちは手をたずさえて歩む。 心の奥深いところで、私は信じる。 私たちはいつの日か勝利すると」
今のアメリカ、特にトランプ大統領の言動を見ていると、なんとアメリカは、こうした歩み、こうした夢から後退してしまったのかと悲しくなります。
先週の4月21日、イースターの翌日に召天し、昨日葬儀が行われたローマ教皇フランシスコのほうが、よほどこの夢に向かって、たゆまない歩みをされてきたことかと思います。平和と正義と公正の実現のために、世界中を飛び回った教皇でした。
(6)キング牧師の説教「失われたものの再発見」
私たちは、水曜日の「聖書を学び祈る会」において、ルカ福音書を続けて読んでいます。先週は、ルカ福音書2章39~52節がテキストでした。それは、12歳の少年イエスと両親がエルサレム神殿に行った時のエピソードです。帰る段になって、少年イエスは神殿に残っていました。ヨセフとマリアは、そのことに気づかず、1日分の道のりを先に行ってしまいます。1日経ってようやくイエスを置き去りにしてしまったことに気づきます。そして引き返していくのです。この箇所で、キング牧師が興味深い説教をしていることを紹介しました。
キング牧師は、1954年2月に、このルカのテキストに基づいて「失われた価値の再発見」という興味深い説教をしています(『真夜中に戸をたたく』所収)。
キング牧師は、少年イエスがエルサレムに置き去りにされたこと、しかし両親はそれに気付いて、イエスを捜し求めてエルサレムへ戻って行ったこと、そこでイエスをもう一度見出したということを、積極的に(ポジティブに、よいこととして)取り上げて、「失われた価値の再発見」と呼びました。そしてイエスの両親がエルサレムに置き去りにしたイエスを捜しに行ったように、われわれもどこかに置き去りにしてしまった大切なものを捜し、取り戻さなければならない、と訴えるのです。
キング牧師は、この説教を「われわれの世界は、何かが根本的に間違っている」という衝撃的な言葉で始めます。
「われわれは無意識的に(アンコンシャスリー)、神を置き去りにしている」「そのことがまさにアメリカで起こっている事柄である」「憎むことは間違いである。」「われわれの生活を暴力的な生に投げ込んでしまうことは、間違いである。」 「われわれは多くの尊い価値を後ろに置き去りにしている。われわれは多くの大切な価値を見失っている。だからもし前進しようとするならば、もしこの世界を住むためのよりよき世界にしようとするならば、われわれは引き返さなければならない。われわれは置き去りにしてきたこれらの大切な価値を、再発見しなければならない。」
そして大胆に語ります。
「今日の世界で必要なことは、一群の人々が立ち上がって、正しいことを擁護し、悪しき事柄に-それが何であれ-反対することである。」前掲書16頁
キング牧師は、この時まだ25歳でボストン大学の大学院生でした。この8か月後に南部アラバマ州モンゴメリーの教会の牧師となります。そして翌1955年、キング牧師が中心となってモンゴメリーにおけるバス・ボイコット運動が起こります。それが公民権運動の始まりとなりました。ですから公民権運動を始める1年位前に、この説教をしている。内的には、彼の中で、そういう機運が高まっていた。そして時を得て、外的な運動が始まっていった、と言えるでしょう。
(7)キング牧師の示した方向
私は、改めてこのキング牧師の「失われたもの再発見」という説教を、読みながら、むしろこの言葉は、今のアメリカにこそ、聞いてほしい言葉だと思いました。
エフェソの信徒への手紙の著者は、「悪い言葉を一切口にしてはなりません」と戒めましたが、今のアメリカの大統領は、口を開けば、人を貶める言葉、人を挑発する言葉ばかり語っているように思えます。彼は、「アメリカを再び偉大な国にする」と言っておりますが、本当の偉大さは、そんな道の向こうにあるのではなく、キング牧師が語ったような道の先にこそあるのではないかと思います。「失われた価値」を再発見し、再び世界中から尊敬されるようなアメリカに立ち返ってもらいたいと願うものであります。
もちろんそのことは、ただ今のアメリカを批判して終わる問題ではありません。世界共通の問題であり、日本の問題でもあります。さらに言えば、私たちの小さな共同体、教会の問題でもあるでしょう。
預言者ミカが示した道、「公正を行い、慈しみを愛し、へりくだって、神とともに歩む道」、「世界の人々と手をたずさえて歩む道」を進んでいきたいと思います。