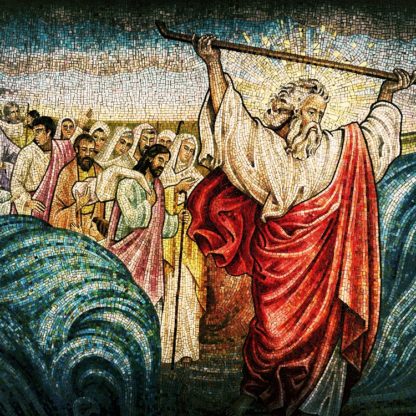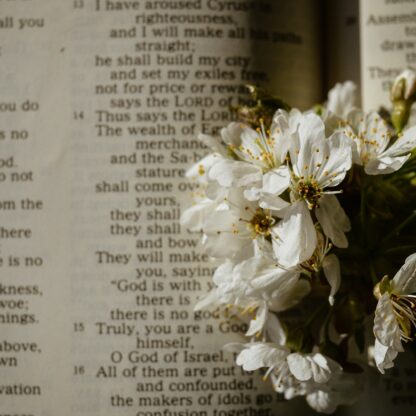2025年2月2日説教「主の喜ばれること」松本敏之牧師
ミカ書6章6~8節
ルカ福音書20章44節~21章4節
(1)律法学者に注意しなさい
新しい年になって早1カ月が過ぎました。
少し間があきましたが、少しずつルカによる福音書を読み進めています。前回は12月1日に、20章41~44節を用いて、「ダビデの子」と題してお話しました。本日、その説教のプリントを配布しました。20章のほとんどの部分は、イエス・キリストが律法学者やサドカイ派の人々など、宗教的指導者と論争、問答をなさったことが記されていました。前回部分はもう論争というよりは、イエス・キリストの説教のようになっています。そしてそれを語り終えたところで、律法学者たちを非難されるのです。イエス・キリストは弟子たちに向かってですが、民衆にも聞こえるように、こう言われました。
「律法学者に注意しなさい。彼らは正装して歩きたがり、また、広場で挨拶されること、会堂では上席、宴会では上座に座ることを好む。」ルカ20:46
要するに偉そうにしているということです。そして民衆から尊敬されることを求めているようです。しかし、これだけであれば。それほど問題は大きいわけではありません。次にこう言われるのです。
(2)やもめの家を食い物にする
「やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。」ルカ20:46
律法学者たちの全員が、この非難に該当したわけではなかったでしょう。正しく、誠実に生きようとした律法学者たちもいたであろうと思います。ですから、イエス・キリストも「このような者たちは」と限定しながら、「このような者たちは人一倍厳しい裁きを受ける」と言われたのでした。
「やもめ」とは夫に先立たれた女性ということで、当時の社会の中で、孤児、寄留者と並んで、社会的に最も弱い立場にある人たちでした。
「やもめの家を食い物にする」とは、具体的にはどういうことが行われていたのでしょうか。最も弱い立場にある人ですから、何かいざこざが起きても自分の立場をはっきり告げることができない。それを告げても信じてもらえない。泣き寝入りの状態です。それで「偉い人」に、自分の言うことをきちんと聞いてくれる人だと信じで、お金か、何かしらのささげものをもって、律法学者さんに相談をする。律法学者は、一応、話をよく聞いてくれた。ところがその後は、全く動くこともなかった。一方で、お金持ちのほうの話も聞いて、そちらからも賄賂のようなものをもらって、そちらの言う通りにした。やもめのほうからすれば、「食い物にされた」ということになるでしょう。そういうことが推察されます。
(3)聖書の神はどんな方か
旧約聖書の中で、私の最も好きな、というか、最も大事だと思われる言葉に、こういう言葉があります。皆さんもぜひ覚えておかれるとよいと思います。それは申命記10章17節以下の言葉です(聖書協会共同訳では、282頁です)。聖書の神さまがどういう方であるかを述べた箇所です。
「あなたがたの神、主は神の中の神、主の中の主、偉大で勇ましい畏るべき神、偏り見ることも、賄賂を取ることもなく、孤児と寡婦の権利を守り、寄留者を愛してパンと衣服を与えられる方である。」申命記10:17~18
神がどういう方であるかを、三つの段落で述べています。
一つ目は「あなたがたの神、主は神の中の神、主の中の主、偉大で勇ましい畏るべき神」ということです。神々と呼ばれるようなものの中で、最も偉大な神であり、そして「勇ましい、畏るべき神である」と告げられます。この「おそれ」という言葉に、「恐怖」の「恐」ではなく、「畏怖」の「畏」という漢字が当てられていることも意義深いと思います。神はあなどられるような方ではない。しかし私たちをむやみに怖がらせる方ではないということです。
二つ目は「偏り見ることも、賄賂を取ることもない」方だということです。先ほどの「律法学者」とは違います。神様は、この世のいろいろな状況にぶれることなく、まっすぐなお方、正義と公正に満ちた方だということです。
そして三つ目、「孤児と寡婦の権利を守り、寄留者を愛してパンと衣服を与えられる方」だということです。その神様は、正義と公正に満ちているだけではなく、「愛に満ちた方」、「慈しみに満ちた方」だということです。人間のリーダーは、なかなかそうはいかない。でも、そのような神様が大事にしておられることを実践することこそが、私たち人間にも求められているのだと思います。
(4)神を愛することと隣人を愛すること
イエス・キリストは、別の箇所で、最も大事な戒めとして、「心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさい」(ルカ10:27)と言われました。聖書が、そしてイエス・キリストが「隣人」という時に、それはただ単に隣にいる人ということではなく、「隣にいて、私に助けを求めている人」に他ならないからです。ルカ福音書で、この問答が出てくるのは、10章の「律法の専門家」が、イエス・キリストに「先生、何をしたら、永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか」と問うたことから始まっていました。そしてイエス・キリストが先ほどの答えをされた後、その律法の専門家が、「では、私の隣人とは誰ですか」と二つ目の質問をするのです。それに対して、イエス・キリストが話されたのが、有名な「よきサマリア人」の話でした。そして、イエス・キリストが最後に、「この3人の中で、誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか」と問い返されました。彼は、「3人目のサマリア人」だということはすぐにわかったことでしょう。しかし、自分たちが下に見ている、あるいはちょっと軽蔑している「サマリア人」とは言いたくなかったので、内容的に「その人に憐れみをかけた人です」と答えました。すると、イエス・キリストは、「行って、あなたも同じようにしなさい」と、励まされたのです。この話からも、「隣人とは、たまたま隣に居合わせて、自分に助けを求めている人」と言うことができるでしょう。その意味で、他人でも隣人になりうるのです。今の時代であれば、物理的に隣にいなくても、その人の情報が耳に入り、私に助けを求めている、ということが分かったら「隣人」と言えるかもしれません。
さて、この二つの戒め「神を愛すること」、「隣人を愛すること」は、別々のもののように見えますが、実は深いところで、くっついています。なぜなら、すべてを尽くして神様を愛するということは、突き詰めて言えば、神様が大事にされていることを、私たちも大事にすることに他ならないと思うからです。神様が大事にされることをないがしろにして、「神様を愛しています」と言ったり、礼拝をしたり、犠牲のささげものをしても、喜ばれないからです。
(5)公正を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩む
今日は、旧約聖書のほうは、ミカ書6章の言葉を読んでいただきました。こういう言葉です。
「何をもって主にまみえ
いと高き神にぬかずくべきか。
焼き尽くすいけにえか、一歳の子牛か。
果たして、主は幾千の雄羊
幾万のしたたる油を喜ばれるだろうか。
私は自らの背きの罪のために長子を
自らの罪のために
胎から生まれた子を献げるべきか。」ミカ6:6~7
そのように自問します。
それに対して、自分でこう答えるのです。
「人よ、何が善であるのか。
そして、主は何をあなたに求めておられるか。
それは公正を行い、慈しみを愛し
へりくだって、あなたの神と共に歩むことである。」ミカ6:8
これは、私が先ほど述べたことに通じます。神様が大事にされることをないがしろにして、どんなに大きな捧げものをしても、神様は喜ばれない。むしろ神様が大事にされることを、私たちも大事にすることこそが求められているのだということです。このミカ書6章8節の言葉も、旧約聖書の中の最も大事な言葉の一つですから、ぜひ心に留めていただきたいと思います。
(6)貧しい人と高ぶる者の逆転
「やもめ」という言葉が出て来たところで、ルカ福音書は、「やもめ」の別のエピソードを語ります。それは、この律法学者の態度と対比的になっているとも言えるでしょう。
章をまたいで、21章1節からです。
「イエスは目を上げて、金持ちたちが献金箱に献金を入れるのを見ておられた。そして一人の生活の苦しいやもめがレプトン銅貨二枚を入れるのを見て、言われた。言っておくが、この貧しいやもめは、誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆、有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。」ルカ21:1~4
私が訳した賛美歌の中に、アルゼンチンの「だから今日希望がある」という賛美歌があります。今日から始まる「希望のダイヤル」で、阿川まち子さんもご紹介くださっています。この賛美歌の日本語歌詞の2節は、こういう言葉です。
「主はおごる者を散らし、高ぶる者を低くし
小さく貧しい者を引き上げ、ほめられたから。」
「だから今日希望がある。
だから恐れず生きる。
貧しい者の未来を信じて(歩み始める)」
まさに今日の聖書箇所に表れている対比が、この歌詞にも表れている、と言えるでしょう。(というか長いスペイン語の原歌詞を、要約すると、こういう日本語歌詞になったということでもあります。)
(7)献金の額をどのように考えればよいのか
さて、このレプトン銅貨2枚をささげた貧しいやもめのエピソードをどのように理解すればよいか、なかなか難しいですし、デリケートでもあります。
これがどの位の貨幣価値であったのか、聖書巻末の度量衡の換算表にはこのように記されています。「最小の銅貨で、1デナリオンの128分の1。」最小の貨幣だと、日本では1円ということになりそうですが、もう少し高いでしょう。1デナリオンが一日の労働者の賃金であったと言われますので、仮に5千円といたしますと、その128分は39円です。まあ少し多めに見積もれば50円位かもしれません。
あるいは、生活費全部をささげてしまうということからすれば、今の日本の社会では500円位かもしれません。この人にとって、大きな決心の上の献金です。
さて、この話を、私たちに引き寄せていえば、献金をいくらささげたらよいのか、あるいはどのように考えればよいのかというデリケートな問題でもあります。私は、洗礼準備会の折に、献金の話もいたします。どのように考えればよいのか、何か目安はあるのかと、問われることもあります。
まず押さえておきたいのは、この女性は誰に強いられたわけでもない。自らすすんでこれをささげたということです。
献金は、誰に強いられてするものではありません。月定献金は自分で額を決めて、それをささげるものですから、一律の会費ではありません。ですから、喜んでささげられる額を自分で決めればよいのです。
この人のしたこと、つまり持っている生活費全部をささげたというのは、どちらかと言えば、例外的なことであったでしょう。そこには、自分の今後の人生を、すべて神様に委ねるという意味合いがあったでしょう。聖書に出てくる一つの目安は十分の一献金ということです。しかしそれも、いろいろな解釈があるわけですから、決まったことではありません。献金が滞って、それで教会に行きにくくなって、教会から足が遠のいてしまったということを、時々聞きますので、それはあまり気になさらなくてもよいでしょう。基本的に、年度をまたいでしまったものは、また新年度から、額も定め直してやっていただければと思います。でも月定献金として約束をするのは、教会がそれによって予算を決めるからです。でもその約束も、年度の途中で変更することも可能です。ですから、喜んでささげられる額にしてください。「あまり無理をしなくていいですよ」ということを申し上げることにしています。
もう一つは、それと一見、真逆のようなことをお話します。献金でありますので、自分の心をそれにのせて、祈りをもってささげるものです。ですから、その献金をしようとしまいと、自分の生活に影響を及ぼさないようなものであれば、果たして献金と言えるだろうかということも言えるでしょう。ですから、残り物、余り物をささげるのではなく、最初にそれを取り分けて献げ、その残りで生活を組み立てていくような心が求められるのかなと思います。私たちは献金をすることによって信仰も成長するのです。そして何らかの「痛み」をもって献げる時に、教会の予算や活動に対しても、責任的にかかわるようになるのではないでしょうか。
ですからまとめて言えば、あまり無理をしないで、喜んでささげられる金額を決めてください。同時に、それが自分の神さまへの献げものなのだという心、つまりそれが自分自身を神様にささげる献身のしるしなのだという心をもって決めてください、ということができるでしょう。
あまり無理をしないで、あまり背伸びをしないで、でもちょっとだけ背伸びをする気持ちがちょうどよいのかもしれません。私たちは、そのようにして献げられたもので、教会形成をしていきます。今、レプトン銅貨2枚の献げものをした人の心を聞き取りましたが、私たちもそういう思いで、献げものをしながら、教会を建て、神様の御前に進んで行きたいと思います。