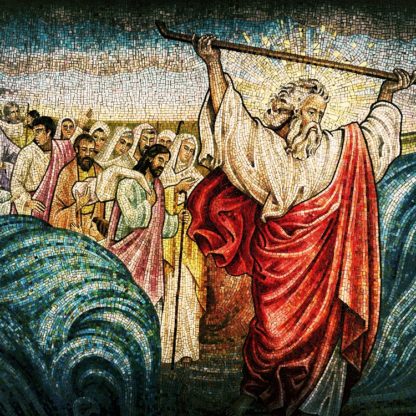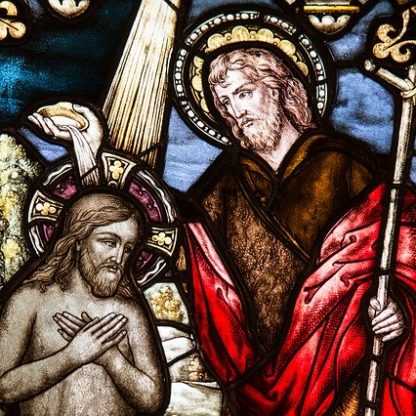2025年11月16日説教「強い人、弱い人」松本敏之牧師
イザヤ書56:6~7
ガラテヤの信徒への手紙2:11~14
(1)アンティオキア教会
今日のテキストでありますガラテヤの信徒への手紙2章11~14節は、アンティオキアの教会において起こったひとつのエピソードについて記しています。アンティオキアというのは、エルサレムのずっと北方、シリアとの国境近くの小都市でありました。このアンティオキアの町には、もともとその地に住んでいた人々の他に、マケドニア人、ギリシャ人、そして大きなユダヤ人のグループがあるという、人種がかなり混在した町であったようです。
アンティオキアについて、使徒言行録の中に興味深い記述があります(使徒11:19~26)。この箇所は、今日のガラテヤの信徒への手紙のテキストを理解する助けとなります。よかったら後ででもお読みください。この箇所からわかることは、まずアンティオキアの教会は、エルサレムから迫害を逃れてきた人々によって始められたということです。つまり、最初は彼らがユダヤ人だけに福音を語っていた。しかしながら、ギリシャ語を話す人々、すなわちユダヤ人以外の異邦人にも福音を語り始めることになります。言い換えれば、最初の異邦人伝道がこのアンティオキアで行われたということが言えるでしょう。そしてそれが成功したので、エルサレムからバルナバが遣わされます。さらにバルナバはパウロを捜し出して、「手伝ってくれ」と頼んだのでしょう。バルナバのほうが先輩の使徒でした。バルナバとパウロ、この二人で丸一年、このアンティオキアで共に働いたのです。それが、今回のガラテヤの信徒への手紙のエピソードの背景です。そのようにして、パウロとバルナバが働いていたところへ、今度はエルサレムからペトロがやってきます。ここに出てくる「ケファ」というのは、ペトロのことです。ペトロというのは、主イエスがつけられた名前でしたが、ギリシャ語で「岩」という意味です。「岩」をアラム語で言えば、ケファでありました。ユダヤ人の間では、ペトロは「ケファ」と呼ばれていたようです。
(2)態度を変えたペトロ
ペトロは、最初このアンティオキアに来た頃は、異邦人キリスト者とも食事を共にしていました。ペトロは、かつてコルネリウスという異邦人の軍人に福音を告げ知らせたこともありました(使徒10:34~48)。ですから基本的に異邦人伝道ということに肯定的な立場であったでしょう。このアンティオキアにおいて、異邦人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンが共に食卓を囲んでいると言うことを、基本的にうれしく思い、自分もそこに加わることを喜んだことであろうと思います。キリスト教会の将来を先取りして、そのひな形がここに実現している、と思ったかも知れません。
ところがエルサレムから「ヤコブから遣わされた人々が来る」と聞くと、突然態度を変えました。「もう異邦人クリスチャンとは、一緒に食事をしない」というのです。このペトロの取った態度に、バルナバも、他のユダヤ人も同調したということです。このようになったきっかけは、「ヤコブから遣わされた人々が来る」ということでした。ヤコブ自身が、どういう立場であったのかは記されていませんけれども、彼は教会外の人々にまで、「義人」として尊敬されるほど、律法を忠実に守っていた人でしたから、恐らく他の人に対しても、律法を守ることに厳格な人であったのでしょう。ともかく「ヤコブから遣わされた人々」はそうでありました。
12節の後半には、「割礼を受けている者たち」が出てきます。これは実際には、ヤコブのもとから来た人々と、その背景にあるユダヤ人クリスチャンたちを指しているのでしょう。ペトロはこの「割礼を受けている者たちを恐れ、異邦人から次第に身を引き、離れて行った」と、パウロは書いています。ここには、パウロのペトロに対する否定的な評価が含まれています。しかしなぜペトロがこの人たちを恐れて、身を引いたのかまでは、記していません。
ペトロはこの時、すでに初代教会の最高責任者の一人であったはずです。ヤコブのほうがペトロよりも上に立っていて、ペトロに対して注意を与えるというのは、考えにくいことです。確かにこの時、パウロが言うように、ペトロが毅然とした態度をとっていれば、よかったのかも知れませんが、それができなかったところが、またペトロらしいと言えるかもしれません。
(3)ダブルスタンダード
少しペトロの側に立って考えてみれば、こういうことではなかったでしょうか。「異邦人クリスチャンと食事を共にする」という、ペトロが最初にとった行動には、ペトロの正直な気持ちがあらわれていたと思います。彼は見せかけではなくて、喜んで異邦人と共に食事の席に着いたのでしょう。ところが、自分のとった行動が思わぬ影響を及ぼしていることを知りました。ペトロの本来的な職務が誰に対してであったかと言えば、2章7節によれば、割礼を受けた人々に対してでありました。そして、割礼を受けていない人々に対する伝道はパウロの職務でした。
ペトロは、自分のそれまでの行動、つまり異邦人と一緒に食事をしていたことが、「割礼を受けている人々への伝道」という、ペトロに本来与えられていた職務に支障が生じるのではないかと心配したのではないでしょうか。ペトロは、ここで自分が出張先、問案先で取っている行動が、自分のホームグラウンドまでは伝わらないだろうと、たかをくくっていたのかも知れません。ですから喜んで食事をしていました。
前回の2章1~10節に、いわゆるエルサレム会議での決定というのが記されていました。それをもう一度振り返ってみますと、「異邦人がクリスチャンになる時は、ユダヤ人のように律法を厳格に守らなくてもよい。割礼も受ける必要はない」ということでした。ところが、これはあくまで暫定的な処置であって、根本的なところはあいまいにされたままであったのです。「それではユダヤ人はどうなのか。やはり律法を守り続けなければならないのか。割礼を受けなければならないのか」ということは、保留のままでありました。ユダヤ人クリスチャンの間では、このことについて、まだ意見が分かれていたのです。異邦人は律法に縛られる必要はないが、ユダヤ人については、どちらとも言っていない。まだ過渡期なのです。
そうすると、この先、どうなるでしょうか。エルサレム会議の決定そのものが、いわばダブルスタンダードなのです。ユダヤ人の教会と異邦人の教会、それぞれが別々の教会を持ち、別々に教会生活をしている分には問題ないのですが、それが一緒になるところでは問題が生じてきます。だからユダヤ人クリスチャンは、異邦人クリスチャンとまだあまり一緒に行動すべきではない。食事も一緒にすべきではない。その理論もそれなりに分かるような気がします。ペトロにしてみれば、自分の本来の「羊」である人々、ユダヤ人クリスチャンをつまずかせたくないという思いから、異邦人クリスチャンから一線を引いた。態度を変えたのではないでしょうか。
これと似たようなことを、実はパウロ自身も述べています。コリントの信徒への手紙一の8章で、「偶像に備えられた肉を食べてよいかどうか」という議論においてです。彼は、基本的にそれは食べていいのだといいます。それで汚れるということはない。私もそこから自由なものだ。そう言っています。しかし「あなたがたのこの強さが、弱い人々のつまずきとならないように、気をつけなさい」(9節)というのです。そしてこういう風に結びます。
「それだから、食物が私のきょうだいをつまずかせるなら、きょうだいをつまずかせないために、私は今後決して肉を口にしません。」コリント一8:13
パウロは、第一コリントの方で、あの肉を食べるか食べないかという話を次のように、広げていきます。9章の19節以下です。
「私は、誰に対しても自由な者ですが、すべての人の奴隷となりました。より多くの人を得るためです。ユダヤ人には、ユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法の下にある人には、私自身はそうではありませんが、律法の下にある人のようになりました。律法の下にある人を得るためです。私は神の律法を持たないのではなく、キリストの律法の内にあるのですが、律法を持たない人には、律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人には、弱い人になりました。弱い人を得るためです。すべての人に、すべてのものとなりました。ともかく、何人かでも救うためです。福音のために、私はすべてのことをしています。福音に共にあずかる者となるためです。」コリント一9:19~23
これはパウロの語っていることですが、私は、何だかこの時のペトロの気持ちを代弁しているような言葉ではないかと、思いました。ペトロにしてみれば、「(私は)ユダヤ人には、ユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法の下にある人には、私自身はそうではないのですが、律法の下にある人のようになりました。律法の下にある人を得るためです。」そういう思いで、自分の本来の羊であるユダヤ人のことを思いやって、その人たちをつまずかせないように、異邦人クリスチャンたちとの食事をやめたのではないか。ペトロの気持ちを察するのです。
(4)ペトロの誤り
そのようにペトロの気持ちを察することができようかと思います。しかしながら、それでもやはり、この時のペトロの判断には問題があったと思うのです。それは「誰かをつまずかせないために」と思って取った行動が、思わぬところで、別の誰かをつまずかせることがあるからです。
これは、私たちもしばしばおかす過ちではないでしょうか。特に八方美人的な性格の人はそうでしょう。パウロは、ペトロが割礼を受けている者たちを恐れて、「身を引き、離れて行った」と批判していますが、私はこの「身を引く」という表現の中に、ペトロのみんなに気遣う性格がにじみ出ているように思います。できればことを穏便に収めたい。
ところがペトロほどの人ですから、ペトロが身を引くと、他のユダヤ人も動揺し始め、私も、私も、とみんなが身を引くと言い出したのです。そしてとうとう、このアンティオキア教会の責任を負っているはずのバルナバまでもが同じように、身を引き始めたのです。そうすると一体どうなるでしょうか。結果的に異邦人クリスチャンたちが疎外されていくことになります。「ユダヤ人クリスチャンをつまずかせない」ためにと思って取った行動が、結果的に異邦人クリスチャンをつまずかせることになるのです。
そういうことを考えてみれば、「ユダヤ人にはユダヤ人のようになる。異邦人には異邦人のようになる」というのは、理論的にはわかるのですが、実際にはつくづく難しいことだと思います。
それは決してカメレオンのように、相手に応じて、自分の色を変えて生きるということではないでしょう。パウロがこの言葉を語った時、それはそのさまざまな相手を救いに導き入れるためだと言っていますが、私たちは、しばしば、そのこと、その理論を、自分を守るために八方美人的に生きることと取り違えてしまうのではないでしょうか。
「肉を食べたらつまずく人がいるなら、私は決して食べない」。これはまだそんなに板挟みになることではないでしょう。しかしどちらの行動をとっても、その反対の人がつまずく、というケースが実際には多いのではないでしょうか。異邦人と共に食事をすれば、ユダヤ人クリスチャンがつまずく。しなければ、異邦人クリスチャンがつまずく。そうした板挟みにおかれた時、私たちは一体どうすればよいのでしょうか。
(5)迷った時の二つの判断基準
これはなかなか難しい問題ですが、私は二つのことを念頭において行動するのがよいと思います。ひとつは、「自分が本当に正しいと思うことはどちらか」ということです。肉を食べるかどうかのようなレベルではない。自分はどちらに立つべきか、それを決断しなければならない時があります。その時に、相手にあわせてころころ変わることはできません。こっちに向かってはこう言い、あっちに向かってはああ言う。そういうころころ変わる態度にまた、つまずく人も出てくるでしょう。私たちは、そのようなディレンマに立たされた時は、勇気を持って、自分が正しいと思っている側に身を置いて、自分の立場を鮮明にしなければなければならないのではないでしょうか。私もなかなかそれができないので、自戒の念をもって語っているのですが、そういうことが必要であるのだと思います。
もうひとつは、どちらの行動をとってもその反対の人がつまずく時、そしてそれは相対的な判断であるという時、どうすればよいか。より弱い立場の人はどちらか、より守られなければならないのはどちらの人か、ということを配慮して行動するのがよいのではないかと思います。
このペトロの場合、基本的に「ヤコブから遣わされた人々」「割礼を受けた人々」というのが、圧倒的に強い立場にありました。異邦人クリスチャンというのは、まだ駆け出しで、いつ押しやられるかわからない人々でありました。もしもこの時、ペトロが毅然とした態度を取って、異邦人クリスチャンたちとの食事を続けていたならば、ヤコブから遣わされた人々も、異邦人クリスチャンに一目をおいたことでしょう。ところが、ペトロは権力者の側におもねいてしまった。私は、やはりこの時、ペトロはここで弱い立場にある異邦人クリスチャンが自分の行動によって躓かないかどうかを、優先して考えるべきであったのではないかと思います。
(6)ペトロとパウロ、二つのキャラクター
さてこのエピソードは、ペトロとパウロという、キリスト教会の最初の二大使徒が一緒に登場する珍しい箇所、おもしろい箇所です。ここには二人の性格がよく表れていますし、二人がどういう関係であったかということも、いろいろと想像させてくれます。
まずパウロのほうは非常に強く、何ものも恐れない、怖じけづかない、福音に固く立って前進していく姿がよく表れています。彼はしっかりとユダヤ教徒として聖書の勉強をしていましたし、頭もいい。パウロのとった態度というのは一貫していますし、教会の権威者であるペトロに対しても、あるいは自分を招いたこのアンティオキア教会の責任者バルナバに対しても全くものおじせず、理路整然と自分の言い分を述べているのはさすがだと思います。情熱的であり、そしてある意味で完璧主義者だとも言えます。ここまで公衆の面前ではっきりとペトロを批判する。一言で言えば、「強い人」だなあと思います。
その一方で、ペトロの方はいかがでしょうか。人を見て、態度を決めてしまう様子、強いものになびいてしまう様子を見ていると、あの主イエスが十字架にかかられる前に弟子であった時のペトロを思い浮かべてしまいます。イエス・キリストが十字架にかかられる時に、「ご一緒になら、牢であろうと死であろうと覚悟しております」(ルカ22:33)と断言しながら、三回も否定してしまう。そしてイエス・キリストの予告どおり、その時に鶏が三回鳴くのを聞いて、おろおろと泣いてしまう、あのペトロです(ルカ22:62)。ペトロはそこから立ち直って、教会の指導者になっていくのですが、それっきり信仰的にも強くなったのかと言えば、やはり弱さをひきずっていたのだなと、思うのです。しかも彼は漁師の出であり、パウロのようにしっかりと神学を学んだわけでもありません。パウロに批判されて、たじたじとしている様子が目に浮かびます。私は、ペトロという人は、何度もこういうことを繰り返したのではないか、と思うのです。そしてその都度、彼の信仰の原体験に立ち帰っていったのではないでしょうか。
このペトロとパウロは全く異なったタイプの使徒です。みんながみんな、パウロのような厳しいタイプの指導者であれば、息が詰まってしまったかも知れません。初代教会は、こうした全く違うタイプの二大リーダーがいたからこそ、育ったのではないでしょうか。
神様は、強い人、弱い人。厳しい人、甘い人。自分の信念をしっかり貫き通すタイプの人。人の反応を見ながら、さまざまな意見を調整しながら、全体のまとめ役に秀でている人。完璧な信仰の模範を示すことのできる人。八方破れで、弱さを見せつつ、それでも人の信頼を得ていく人。
私は、神様は今日の教会においても、あるいは今日の社会においても、さまざまなタイプの人間を用いながら、御業を押し進められるのだと、思います。そうした神様のご計画に栄光を帰し、感謝をしつつ、御用の一端を、それぞれ担っていきましょう。