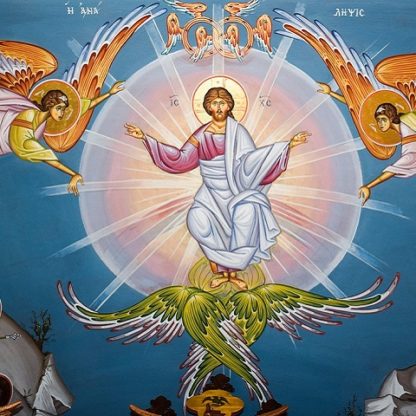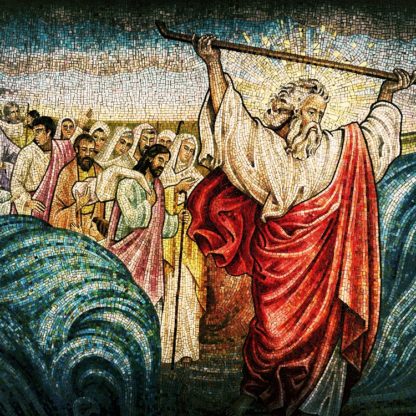2025年9月7日説教「弟子たちの無理解」松本敏之牧師
ホセア書11:1~4
ルカ福音書22:24~30
(1)「弟子」と「使徒」
7月6日以来となりましたが、ルカ福音書を続けて読んでいます。7月6日は「主の晩餐」と題して説教しましたが、本日、プリントにして配布しました。
先ほど読んでいただいたルカ福音書22章24節以下は、まだ最後の晩餐の席での話となっています。「また、使徒たちの間に、誰がいちばん偉いだろうか、という言い争いが起こった」(24節)と始まります。
「使徒たち」というのは、「十二弟子たち」のことです。ただ「弟子たち」と「使徒たち」はニュアンスが違います。「弟子たち」という呼び方は、イエス・キリストが召し集められた者、あるいはイエス・キリストに従った者、という意味ですから、求心的です。ベクトルが内に向いています。それに対して、「使徒たち」という呼び方はイエス・キリストから派遣された人ということですから、遠心的です。ベクトルが外に向いているのです。ルカ福音書6章12節に、こう記されていました。
「その頃、イエスは祈るために山に行き、夜を通して神に祈られた。朝になると弟子たちを呼び寄せ、その中から十二人を選んで使徒と名付けられた。」ルカ6:12~13
そして十二人の名前が記されるのです。改めて、その名前を確認しておきましょう。
「それは、イエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。」ルカ6:14~16
彼らは多くの弟子たちの中から、イエス・キリストのご用をするために特別に選ばれた十二人でした。しかし彼らの間では、しばしば誰が一番偉いかという序列争いがあったようです。この過越の食事、最後の晩餐の時にも、もしかすると、誰が主イエスの隣に、そして近くの席に座るかという議論があったのかもしれません。
(2)「災いあれ」
前回の終わりの部分でも、彼らは別の議論をしていました。少し前の21節から読んでみましょう。
「『しかし、見よ、私を裏切る者が、私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は、定められたとおり去って行く。だが、人の子を裏切る者に災いあれ。』そこで使徒たちは、自分たちのうち、一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論し始めた。」ルカ22:21~23
主イエスの言葉を聞いて、弟子たちはざわめいて、「そんなことを考えているやつは、一体誰だ」という感じで、犯人捜しのような議論があったのでしょうか。当のイスカリオテのユダは、ただ黙ってうつむいていたか、それとも、自分であることがばれないように、かえってその議論に加わっていたかもしれません。
ちなみにイエス・キリストは、この時、イスカリオテのユダを指して、「人の子を裏切る者に災いあれ」と言っておられます。この言葉は私たちを戸惑わせるものではないでそうか。前回、この箇所で説教した直後に、そのことについて私に尋ねてこられた方がありました。「イエス様がそんなことをおっしゃるだろうか」と。新共同訳聖書は、ここを「不幸だ」と訳していました。これ位だと、私たちも受け入れやすいのですが、原文は、「ウーアイ」というのですが、もっと強い意味のようです。田川建三という聖書学者は、新共同訳をさして、「その人ご本人が不幸かどうかを言っているのではない。『禍いあれ』(ウーアイ)は、その人に呪いをあびせかけているのである。いやな表現だが、そう書いてあるのだから、そうとはっきり訳さないといけない」と、やや皮肉っぽく書いておられます。聖書協会共同訳も、田川建三と同じ方向で原文に近い言葉で訳したのでしょう。「ウーアイ」というのは「なんということだ」という嘆きのような言葉だという学者もあります。翻訳者たちをも、これを何と訳すか、苦労してきたようです。岩波書店訳(佐藤研)は「災いだ、彼を売り渡すその人は」と訳しています。ちなみに、本多哲郎訳では「人の子を売り渡す当人には、なげかわしいことだ」、文学者の柳生直行訳では、「『人の子』を裏切るその人は、本当に悲惨だ」というふうに、やや意訳をしています。
しかし、原文がどうであったにせよ、(つまり原文とは言っても、そこには聖書記者、つまりマルコやルカの主観が入っているからです)、聖書全体の文脈からすれば、イエス・キリストは、「災いあれ」と言われた、イスカリオテのユダの災いをも引き受けられた方である、ということです。そういうお方であったと言えると思います。ですから、それと合わせて考えたいと思うのです。ここで、それほど強い呪いの言葉を口にされたとしても、イエス・キリストは、ユダを突き放すように言われたのではない。そこでイスカリオテのユダが受けるべき呪いをも、ご自身で引き受けて十字架にかかられたということができるでしょう。
(3)誰が一番偉いか
さて、話が少し広がりましたが、元へ戻りましょう。使徒たちは、ここで「裏切り者は誰か」という議論をしていたところから、そのまま次の議論、「誰が一番偉いか」という議論に移っています。もしかすると、イスカリオテのユダが議論をそちらに誘導したのかもしれません。
使徒たちの間では、シモン・ペトロが一番弟子で、トップ・スリーをあげるなら、ペトロ、ヤコブ、ヨハネということであったようです(ルカ9:28等参照)。そこには、微妙な他の弟子たちの嫉妬のようなものもあったかもしれません。イスカリオテのユダ自身、「自分がどうしてトップ・スリーに入らないのだ」というひがみがあったのかもしれません。彼らは、決してお互いに仲がよかったという訳ではなかったようです。
マルコ福音書では、ヤコブ、ヨハネの二人の兄弟が、「栄光をお受けになるとき、私どもの一人を先生の右に、一人を左に座らせてください」(マルコ10:37)とお願いしています。マタイ福音書では、同じ言葉を二人の母親の言葉として記しています(マタイ20:21)。二人は、自分たち兄弟はトップ・スリーには入っているけれども、やっぱり一番はシモン・ペトロだという自覚の中で、最後の時には、ペトロを追い抜いて、イエス様の両側にいたい、という思いであったのでしょう。
(4)イエスと使徒たちの最後の対話
そうした使徒たちを見据えて(見かねて)、イエス・キリストが、口を開かれます。この箇所と、次回の部分(30~38節)は、イエス・キリストが使徒たちと対話をされた最後の箇所となります。それ以降、イエス・キリストは逮捕され、使徒たち(弟子たち)に向かって、対話されることはありません。イエス・キリストは、こう言われました。
「異邦人の王たちはその民を支配し、民の上に権力を振るう者が恩人と呼ばれている。」ルカ22:25
ここで「恩人」と訳された言葉は、聖書協会共同訳の注によりますと、「直訳では、『恩恵を施す者』、別訳『守護者』」とあります。新共同訳聖書は、「守護者」と訳していました。「異邦人の王たち」というのは、「信仰を持たない世界の王」とか、「この世の価値観では」というふうに読み替えてもよいでしょう。つまり、この世の価値観では、上に立つ人が偉そうにして、何か恩恵を施すのも、上から偉そうに行っている。だから「恩人」とか「守護者」と呼ばれる、ということでしょう。イエス・キリストは、こう続けられます。
「しかし、あなたがたはそれではいけない。あなたがたの中でいちばん偉い人は、いちばん若い者のようになり、上に立つ人は、仕える者のようになりなさい。」ルカ22:26
このメッセージは、主イエスがことあるごとに語られてきたメッセージでもあります。ルカ福音書14章では、宴会に招待された時には、「上席に着かないで、末席に座りなさい。」「誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる(14:8~11)と語られました。
しかしこれは、単純に「偉そうにしないで、謙虚になりなさい」ということを言っているのではありません。またこの世の処世術のことを言っているのでもありません。そういう風に「下手(したて)に出ておいたほうが、人が持ち上げてくれるぞ」ということではありません。生き方そのものが問われているのです。そしてその何よりのお手本がイエス・キリストでありました。
(5)弟子たちの足を洗うイエス
ルカ福音書では、言葉でそのことを語っていますが、ヨハネ福音書では、それを目に見える仕草で伝えられました。同じ最後の過越の食事の際のこと、主イエスは、使徒たちの前にひざまずいて、一人一人の足を洗われたのでした。それは、誰か客人が来た時にその家の召使がする仕事、あるいは奴隷の仕事でありました。それを主人であるイエス、誰よりも上に立つべきお方がそのようになさったのです。そしてこう言われました。
「私のしていることは、今あなたにはわからないが、後で、分かるようになる。」ヨハネ13:7
「主であり、師である私があなたがたの足を洗ったのだから、あなたがたも互いに足を洗い合うべきである。私があなたがたにしたとおりに、あなたがたもするようにと、模範を示したのだ。」ヨハネ13:14~15
それと同じことを、ルカは言葉で伝えられたのです。このように続けます。
「食事の席に着く人と仕える者とは、どちらが偉いか。食卓に着く人ではないか。しかし、私はあなたがたに仕える者のようになっている。」ルカ22:27
この時、主イエスが弟子たちにどのように奉仕されたかは書いてありませんが、少なくともパンとぶどう酒を給仕されたのでしょう。
(6)身をかがめて食べさせた
今日は、旧約聖書は、ホセア書11章の言葉を読んでいただきました。「神の愛」と題されるところです。この箇所のクライマックスは、11章8~9節ですが、今日はその前、前半の言葉を読んでいただきました。
神様がどのようにイスラエルの民を愛し、育ててきたかが記されています。イスラエルの民は、その神の愛に気づかず、背いて、裏切ることになるのですが、ここに神様の愛を示す象徴的な言葉が出てきます。ホセア書11章4節の言葉です。
「私は人を結ぶ綱、愛の絆で彼らを導き
彼らの顎(あご)から軛(くびき)を外す者のようになり
身をかがめて食べ物を与えた。」ホセア書11:4
神様は動物にエサを与えるように食べ物を与えたのではありませんでした。神様と人間ではサイズが違います。サイズが違うときに、同じようになろうと思えば、大きいほうが身をかがめなければならない。「身をかがめて食べ物を与えた。」上から目線ではないのです。同じ目線となるべく身をかがめ、さらに低く、下から使えるように食事を与えるのです。この言葉は、神様が人と共に歩むために、人と同じようになられた、「神が人になった」というクリスマスの出来事を指し示しているようです。
そしてそのようにして神であったお方が人となり、その最後の時を迎えているのです。その意味を本当に深く知ることができるように、弟子たちの前で身をかがめられるのです。そして、あなたがたもそのように、人に仕える者になりなさい、と言われたのです。
(7)池田守男「サーバント・リーダーシップ」
先ほど、「これは単なる処世術ではありません」と申し上げましたが、経営の面で、これを生かした人がいました。それは化粧品会社資生堂の社長であった池田守男さんという人です。サーバント・リーダーシップということを唱えました。『サーバント・リーダーシップ入門』という著書もあります。彼は、2001年から2006年まで、資生堂の社長を務め、2013年に亡くなっています。
彼は経営者としては、異色の経歴の持ち主です。東京神学大学の出身なのです。同志社大学神学部や関西学院大学神学部の出身であれば、牧師にならない人もたくさんいますけれども、東京神学大学の場合は、ほとんどの人が牧師か、学校の教師になります。しかし池田さんは、東京神学大学を卒業したら、そのまま資生堂に入社されました。しかし彼の経営理念である「サーバント・リーダーシップ」というのは、まさに聖書から学ばれた考え方でありました。「サーバント」というのは「仕え人」「召し使い」という意味です。その意味では、サーバント・リーダーシップという言葉自体、逆説的です。
「サーバント・リーダーシップ」という考え方そのものは、池田守男氏が初めて言い出したものではありません。青山学院大学のシュー土戸ポール先生は、このように述べておられます。
「Servant Leadership
この概念は、ビジネス界で非常に有力なリーダーシップ論として広く知られるようになりました。従来のトップダウン、命令形の指導方法ではなく、仕える精神とチーム中心のリーダーシップを重視することにより、従業員一人一人の貢献と主体性と創造力を十分に発揮させるためのものです。サーバント・リーダーシップは、指導するための具体的な技術よりも、リーダーの人格を強調するものなのです。部下が上司に仕えるのではなく、上司が組織の使命や目標に向けて部下を支えます。信頼関係と共通目標を共有しやすくなるため、組織全体の最善を目指すリーダーシップ論であるといえます。」
「資生堂の故池田守男氏は、日本におけるサーバント・リーダーシップによる企業改革の第一人者でした。池田氏は社長在任中にサーバント・リーダーシップを導入し、社員を下から支える立場で経営改革を実現しました。」
資生堂自身のホームページには、このように記されています。
「逆ピラミッド型の経営組織
店頭がすべてのことの基点であり、そのために自らはとことん仕える者であろう、と池田守男は考えていました。
その考えは、あるとき逆ピラミッド型の組織という形に行き着きます。部屋に戻ってきたとき、机の上に置かれていた組織図が目に入りました。いつも見ている方向からではない、逆さまの図を見たときに、これこそふさわしい組織の形だとひらめいたというのです。
お客様と関わる店頭こそが一番上であり、それを担当者が、支社が、本社が、そして最後には代表取締役である自らが下になって支援することが、資生堂のあるべき姿だと公表するようになりました。」
こういうふうに「人に仕える者となれ」という聖書の教えが経営の理念として生かされている一例であります。ちなみに池田守男氏は「受くるよりは与うるは幸いなり」という聖書の言葉が、人生の指針であったそうです。
ただいずれにしろ、これは主イエスの言葉に対する一つの応答であって、イエス様自身は、この言葉を「成功の秘訣」というような意味で語られたのではありません。ご自身の命をかけた言葉でありました。
(8)最後の不思議な言葉
主イエスは、最後に不思議な言葉を付け加えられました。
「あなたがたは、私が試練に遭ったときも、私と一緒に踏みとどまってくれた人たちである。だから、私の父が私に王権を委ねてくださったように、私もあなたがたにそれを委ねる。こうして、あなたがたは、私の国で食卓に着いて食事を共に、王座に座ってイスラエルの十二の部族を裁くことになる。」ルカ22:28~30
この言葉については、次回、もう一度その意味を尋ねながら、次の箇所へと進んでいきたいと思います。ただ私たちは、この言葉を胸に刻みながら、聖餐式へと進んでまいりましょう。