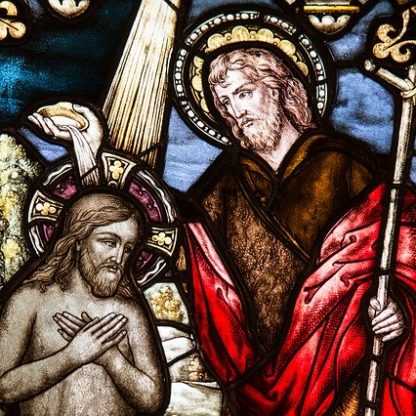2025年7月27日説教「まことの福音」松本敏之牧師
エレミヤ書 7章1~11節
ガラテヤの信徒への手紙 1章6~10節
(1)ガラテヤの諸教会に起こったこと
ガラテヤの信徒への手紙を5月25日に読み始めましたが、2か月経ってしまいました。今回で2回目です。なかなか厳しい言葉が出てきますので、これを読む私たちも気が重くなりがちであるかも知れません。しかしながら、「パウロがそこで、何を見つめ、何を語ろうとしているのか」。「そこまでパウロを熱くさせているものはいったい何であるのか」。パウロの言葉に謙虚に耳を傾けていきたいと思います。
前回の1~5節は、手紙の書き手と受取人が誰であるかということと、それに続く最初の挨拶の部分でありました。そこでも手紙の相手は、非常につっけんどんに、ただ単に「ガラテヤの諸教会へ」としか書かれていません。それは、他のパウロの手紙の書きだしに比べると、とても例外的なことであると、申し上げました。
今回のテキストの6節から、いよいよ手紙の本文が始まります。これがまた、非常に手紙としては例外的と言うか、常識はずれの書き方です。ギリシャ語の原文では、「私は驚いています(新共同訳の表現では、「あきれ果てています」)という言葉で始まります。
「キリストの恵みへと招いてくださった方から、あなたがたがこんなにも早く離れて、ほかの福音に移って行こうとしていることに、私は驚いています。」ガラテヤ1:6
いかにも挑発的な感じがしますが、パウロはそう書き始めずにはいられなかったことが、ガラテヤの教会に起こっていたと言うことが背景にあるのです。
ガラテヤの諸教会とは、パウロが伝道旅行をした際に、いわば開拓伝道をして建てた教会でありました。パウロとしては、自分が心血を注いで建てた教会ですから愛着もあったことでありましょう。その成長を遠くから見守りたいという思いであったに違いありません。ところが何かが違ってしまった。それは彼がガラテヤを離れた後で、エルサレムから、ということはキリスト教会の本家本元から別の伝道者がやって来たのです。
パウロが説いた中心的なメッセージは、「人は行いによって、律法を守ることによって、神に認められるのではない。ただ信仰によって義とされる(神に認められる)のだということでした。この「信仰によって」というのは。厳密には、「神の恵みによって」とか「キリストの真実によって」とか、言い換えられるのですが。今日はそこまで踏み込まないようにします。いずれまた出てきますので、その時にお話しします。
ここでの争点は、「私たちが神さまに認められ、受け入れられるのは、何をしたから、という行為、業績によってではない。ただ信仰によって、あるいは神様の恵みによって」だということです。具体的に、ここで問題になっているのは、割礼を受けなければならないのかどうか、ということでした。
ガラテヤ地方というのは、ユダヤ人の住んでいる地域ではありません。ですから、もともと人々は割礼を受けていません。そこでクリスチャンになるためには割礼を受けなければならないのかということでした。パウロは、それは必要ないと説いたのです。ところが彼が去った後、エルサレム教会の指導者がやって来て、パウロの語ったことを否定したのです。エルサレム教会の指導者は、みんなユダヤ人であり、すでに割礼を受けている人々でした。彼らは、恐らくこんなことを言ったのでしょう。
「パウロという人は、『信仰のみ』、『恵みのみ』と言ったのですか。それはちょっと極端過ぎると思います。確かに私たちは、神の恵みで救われるということはその通りでしょう。信仰が大事であることも、もちろんです。でもそれだけというのは、ちょっと言い過ぎです。人間の側だって、救われるためには、努力しなければならないはずでしょう。そのために私たちには律法が与えられているのです。だからあなたたちも割礼を受けて、きちんと律法を守りなさい。そのほうが理にかなっています。エルサレム教会の偉い先生たちは、みんな、そう教えていますよ。『信仰のみ』とか『恵みのみ』などと極端なことを言うのは、あのパウロという人だけです。
パウロはどうも勝手な解釈で困ります。あなたたちは、パウロから最初にキリストのことを聞いたからよくわからないでしょうが、あの人は決してキリスト教の主流ではありません。傍流です。亜流といってもいいかも知れません。あまり彼の言った通りにしない方がいいですよ。こっちの言うことにも耳を傾けなさい。」
そういうふうなことを言ったのだろうと想像します。ガラテヤの教会の人々も、「そう言われてみると、そうかもしれない」と、彼らの言いなりになりかけていたのでありましょう。
パウロは、この一見非常にもっともらしい言い方の中に、偽物とのすりかえが潜んでいることを見抜いていました。パウロは、決して嫉妬から言ったのではありません。
みなさんはどう思われるでしょうか。私が先ほど述べたように、「救われるためには、人間の側でも努力しなければならない」という意見を聞くと、やはり「そう言われてみれば、確かにそんな気がする、恵みだけで救われるというのは虫が良すぎるかも知れない」と思われる人も案外、多いのではないでしょうか。
しかしパウロは、「それは福音ではない」と、言い切るのです。6節では、「あなたがたは、ほかの福音に移って行こうとしている」という言い方をしたのですが、いや「ほかの福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではない」と補足します。「彼らが『福音』という言葉を使ったから、そう呼んだのであって、それは、本当は福音ではないんだ」。
「ある人々があなたがたをかき乱し、キリストの福音をゆがめようとしているだけなのです。」ガラテヤ1:7
パウロは、「それは決して福音なんかではない。いわば『福音もどき』だと言うのです。
(2)ゼロ・ポイントに立つ
「救われるためには、人間の側でも努力しなければならない」と考えることが、どうして間違っているのでしょうか。それはこういうことです。「キリストの恵みだけがすべてであり、私たちはただ信仰において、それを受け取るだけである」。この信仰は、神さまの前での完全な自己放棄を意味しています。
渡辺英俊という牧師は、そのことを「ゼロ・ポイントに立つ」という言い方をしました。それは偉い人と偉くない人の差が全くなくなってしまう場所だと述べておられます。賢い人も愚かな人もない。生まれも関係ない。男も女もない。そこは、信仰深い人と信仰深くない人の差さえもなくなってしまう場所です。それがゼロ・ポイントだ。人間はそこで全く平等にゼロになる。そこは、人間のあらゆる差別が取り払われる場所だ。全くのゼロから出発するのです。私たちはいつもそれを忘れるのですが、そのゼロ・ポイントへいつも立ち帰っていかなければなりません。そこにおいて私たちは、同じ罪人として、ただ神の恵みによって立ち得る存在として、どんな人とも同じ場所に立つ。そして同じ場所に立つことができるだと言われるのです。
パウロはこのガラテヤの信徒への手紙3章28節において、「ユダヤ人もギリシャ人もありません。奴隷も自由人もありません。男も女もありません」と語ることになりますが、まさにそれは、このゼロ・ポイントにおいてこそ、可能なのだと思います。それが「恵みのみ」「信仰のみ」という信仰の理解です。
それに対して、「いや、そうは言っても、人間の努力も少しは必要だ」という考え方が入ってくると(そしてそれはしばしば入ってくるのですが)、私たちはゼロ・ポイントへ戻ることができなくなるのです。そして何が起こってくるかと言いますと、努力の成果をあげて、人に見てもらいたくなります。そして誰が見ても立派にやっている人は、「あの人は立派な信仰者だ」ということになる。そして私たちは、ひそかに自分を人と比べ始めます。「まあ自分はあの人のようなわけにはいかないけれど、まあそれ程悪くもない。こっちの人よりはましだろう」。そういう風に自分を値踏みして、人も値踏みする。人の立派さや、自分の立派さを計り始めるのです。
そういう風に、人の立派さを計っていく仕方が、律法主義というものです。もちろん私たちは、この時代のユダヤ教のような律法を持ちこむことはありません。割礼をすることもないでしょう。しかしながら、私たちなりの「立派さ」の基準というものを無意識のうちに作ってしまう。それで人を計ってしまう。人によって多少違うかも知れませんが、その時代、その地域にある程度共通する、立派さの基準というものを作ってしまうのです。そこでは、「私たちが神さまの前では全くゼロである」ということを忘れてしまい、ゼロ・ポイントに立てなくなってしまいます。
(3)「私たちであれ、天使であれ」
パウロはそれに続けて8節で、こう言っています。
「しかし、私たちであれ、天使であれ、私たちがあなたがたに告げ知らせた福音に反することを告げ知らせるなら、その者は呪われるべきです。」ガラテヤ1:8
ここで突然「天使」が出てくるのは興味深いことです。天使であっても、もしも福音をねじ曲げてしまうならば、呪われるべきです。天使もひょっとしたら、間違うこともあるかもしれないと言っているのでしょうか。そのことと同時に、その陰には、「天使」でさえも間違うことがあるとすれば、「どんな偉い人であっても誤ることもあるのだ」ということを暗に言おうとしているのではないかと思います。
そこにはエルサレム教会の人々のことが考えられていると思います。パウロからすれば、エルサレム教会の指導者たちをそう簡単には批判できない。あちらはキリスト教の本家本元です。そこで天使を持ち出して、「どんな偉い先生であっても、間違ったことを言うならば、呪われるべきです」と言おうとしているのだと思いました。
「私たち自身であれ」と、パウロは言います。これは、そう語っているパウロ自身でさえも、(そして私たち自身でさえも)、変質してしまう可能性があることを示す言葉であると思います。パウロは、もしかしたら神さまに呪われてしまうかも知れない。その危険の中に、自分自身も置いています。パウロは、人に厳しく、自分に無批判というわけではありません。自分も過ちに陥る可能性がある、自分もそういう危険にさらされている人間であるということから除外されていない。そのことをよくわきまえています。
また「誰であれ、あなたがたが受け取った福音に反することをあなたがたに告げ知らせるなら」ということは、私たちは、前には正しかったかもしれないけれども、いつまでもそうあり続けるとは限らないということです。一度は正しいことを語った人でも、その後ずっとそうだとは限らないのです。
私は、クリスチャンというのは、特に伝道者・牧師というのは、この心構えがなければならないと思います。自分を絶対化しない。例外視しない。もちろん誰かが間違っていると思った時には、勇気を持ってそれを言わなければならないでしょう。建設的批判はしていかなければなりません。しかしその時でも、決して自分を安全地帯においたような批判はしてはならない。牧師というのは、皮肉なことに、他の誰よりも、自分を絶対化する傾向があります。頑固そうに見える牧師だけではなく、一見しなやかそうに見える牧師もその例外ではありません。教区総会や教団総会の様子を見ているとそう思うのです。
私は自戒の意味を込めて語っているのですが、神の言葉を預かり、それを語る者自身が、まず自分をキリストの言葉の前に置き、そこで裁かれなければならない。そしていつもゼロになって、新しく生かされなければならない。そのことが何よりも大切であると思います。
パウロは、ガラテヤの教会の人たちに対して、どんなに憤慨し、心の底ではあちらが間違っているということを信じているのでしょうが、自分をもキリストの福音の前に相対化することを忘れていませんでした。
(4)二つの危険のはざまで
そして10節において、さらに自己吟味する言葉を語るのです。
「今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも、神に取り入ろうとしているのでしょうか。あるいは、人の歓心を買おうと努めているのでしょうか。」ガラテヤ1:10
ここには三つの疑問文が重ねられています。一番目と三番目は事実上、同じことを繰り返していますから、この一つ目と二つ目の疑問文の対比がされているということです。「私は人に取り入ろうとしているのか、それとも、神に取り入ろうとしているのか。」この時のパウロとエルサレム教会からの指導者を比べてみれば、論理としてはどちらも成り立ちます。つまりエルサレム教会から来た指導者たちは、パウロのことを、「あいつは人に取り入ろうとしている」と批判していたのでしょう。「『割礼を受けなくてもよい』というのは、安易すぎる。『信仰によってのみ』『恵みによってのみ』というのも、それはその方が楽だからだよ。そんなことで人は救われるか。パウロという男は、お前たちのご機嫌取りをしているのだ。それでいい、と言って甘やかしているのだ」と言ったのでしょう。
それに対して、パウロはこう考えたでしょう。「いや、私は人に取り入ろうとして、こんなことを言っているのではない。人に取り入るならば、むしろエルサレム教会に取り入って、信仰の先輩の言うとおりにした方が楽です。しかしそんなことはできない。人に聞き従うよりは、神に聞き従う。私たちはどんな立派な行いも誇ることはできない。恵みによって、ただただ恵みによって義とされる(神に受け入れられる)。人間の常識ではわかりにくい、このキリストの恵みにこそ、固執し続け、ゼロ・ポイントに立ち続けなければならないのだ。」そういうことをパウロは語ったのです。
そのように考えていきますと、パウロの説いたキリストの福音というのは、いつも二つの危険にさらされているということができるでしょう。一つは、先ほどから言い続けていますように、いわば「宗教的努力主義」です。今まさにパウロが批判している相手の考え方です。もう一つは、「安易に何でもいいのだ」という考え方です。「自由放任主義」と言えばよいでしょうか。エルサレム教会から来た人がパウロのことをそう誤解した考え方です。
努力して律法をひたすら守り、立派な信仰をもつことで救われるのでなければ、理不尽ではないか。一生懸命やっている人間が馬鹿を見る。ただ恵みによってのみ救われるのであれば、一体誰が真面目な信仰生活など送るか。好き勝手な自由放縦主義に陥ってしまうであろう。
私たち人間の常識では、このふたつ、つまり宗教的努力主義(あるいは真面目な道徳主義)と、「何をしてもいいんだ」という自由放縦主義のどちらかということになってしまいがちです。私たちは救われるために(義と認められるために)、何らかの行いをするという考え方からは自由にされているかもしれませんが、何をしてもよいのだというわけではありません。エルサレム教会の人々は、パウロの考えがそういうものだと誤解したのですが、そうではありません。
パウロは、このガラテヤの信徒への手紙を通じて、そのことを語っていくことになります。そして最後近くの第5章では、こう述べるのです。
「この自由を得させるために、キリストは私たちを解放してくださいました。ですから、しっかりと立って、二度と奴隷の軛につながれてはなりません。」ガラテヤ5:1
「きょうだいたち、あなたがたは自由へと召されたのです。ただ、この自由を、肉を満足させる機会とせず、愛をもって互いに仕えなさい。なぜなら律法全体が『隣人を自分のように愛しなさい』という一句において全うされているからです。」ガラテヤ5:13
これから少しずつ、このガラテヤの信徒への手紙のパウロの言葉に、耳を傾けていきたいと思います。