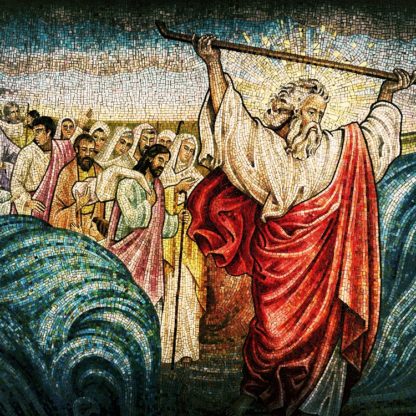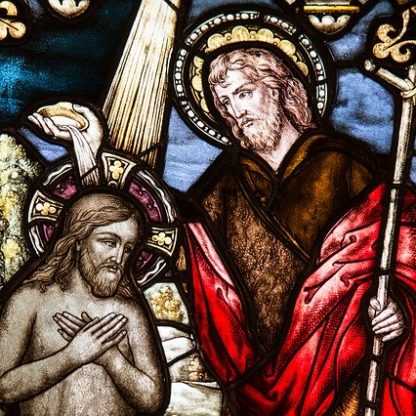2025年5月11日説教「私は復活であり、命である」松本敏之牧師
詩編71編5~9節
ヨハネ福音書11章17~27節
(1)母の日
本日は、母の日です。家族礼拝は母の日を心に留めて礼拝しました。皆さん、それぞれのお母様に対しては特別な思いがあるのではないでしょうか。私ごとになりますが、私の母は昨年の7月30日に、94歳で召天しましたので、今年は初めて地上に母がいない「母の日」となりました。昨年の今頃は、母もだいぶ弱ってきていましたので、月に一度位、鹿児島から兵庫へお見舞いに帰っていたことを思い出しています。
私たちは、信仰をもつ者として、母の日にお母さんに感謝すると共に、そのお母さんをこの世への入口として、私たちをこの世へと送り出してくださった神様にも改めて感謝したいと思います。先ほど詩編71編5節以下を読んでいただきました。
「わが主よ、あなたこそわが希望。
主よ、私は若い時からあなたに信頼し
母の胎にいるときから
あなたに支えられてきました。
あなたが母の胎から
私を取り上げてくださいました。
私は絶えずあなたを賛美します。」詩編71:5~8
詩人は、そのように信仰の告白をしました。私たちも、それに続く者となりたいと思います。
(2)ラザロは確かに死んだ
さて新約聖書のほうは、ヨハネ福音書11章17~27節を読んでいただきましたが、こちらは、本日の日本基督教団の聖書日課です。ヨハネ福音書第11章は、全体としてラザロの復活物語として知られています。ヨハネ福音書の中でもひときわ異彩を放つ物語であり、ヨハネ福音書前半のクライマックスでもあります。今日の聖書の前の部分、11章1節はこのように始まります。
「ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村、ベタニアの出身で、ラザロといった。」ヨハネ11:1
マルタとマリアと言えば、ルカ福音書10章に記されている別の物語でご存知の方も多いでしょう。
「このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である」(2節)と記されていますが、これはこの後の箇所、ヨハネ福音書12章に出てくる話です。このマルタとマリアの姉妹に、ラザロという兄弟がいました。兄であったのか弟であったのかはわかりませんが、たぶん弟であろうと言われます。愛し合っていた兄弟姉妹のようです。そしてイエス・キリストもこの兄弟姉妹を愛しておられました。ベタニアという町は18節によれば、エルサレムに近く(15スタディオン、約2.7キロ)、エルサレムへ行かれる時は、いつもこのベタニアのマルタとマリアの家から通われたと言われます。そのように主イエスに親しいラザロが病気になりました。しかもかなり重い病気、命にかかわる病気です。マルタとマリアは、主イエスのもとへ使いを送りました。
「主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのです。」ヨハネ11:3
しかしイエス・キリストはすぐには動かれませんでした。弟子たちはほっとしたことでしょう。なぜなら、エルサレムにおいて、主イエスは命をねらわれていたからです。10章の終わりには、次のように記されていました。
「そこで、ユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて、去って行かれた。イエスは、再びヨルダンの向こう側、ヨハネが最初に洗礼を授けていた所に行って、そこに滞在された。」10:39~40
「そこ」(ヨルダンの向こう岸)は安全だったのです。ところが二日経ってから、主イエスは突然、「もう一度、ユダヤへ行こう」(7節)と言い出されました。ユダヤ地方というのは、エルサレムやベタニアがあるところです。弟子たちはびっくりして、こう言いました。
「先生、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。」ヨハネ11:8
(3)なぜ二日待たれたのか
弟子たちは、イエス・キリストがすぐに出かけられなかったのは、ユダヤ人を警戒して避けるためだと思っていたでしょうが、それは違いました。イエス・キリストが二日間待機しておられる間に、ラザロは死んでしまいます。
「さて、イエスが行って御覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日もたっていた。」ヨハネ11:17
イエス・キリストのところへ、ベタニアのマルタ、マリア姉妹から「兄弟ラザロが病気で死にかけている」という伝言をもった使いがやってきましたが、イエス・キリストはそれから2日たってからようやく出発されます(6節参照)。片道2日かかる距離であったのでしょうか。あるいは使いがベタニアから主イエスのおられたところへ到着するのに1日、主イエスがそこからベタニアに到着するのに1日かかったとして、合計4日であったのかも知れません。
ここにわざわざ「4日もたっていた」と、福音書記者が記しているのは、ラザロが本当に死んだのだということを強調するためでしょう。つまりこの後、ラザロは復活するのですが、それは単なる蘇生ではなかったということを示そうとしているのだと思います。当時のユダヤ人の間では、死者の霊は、死後3日間はまだ遺体のそばに留まっている。しかし4日目になるとそこを離れて、蘇生の望みは全くなくなると信じられていました(日本にも同じような考えがあるかもしれません)。肉体的にもそうでしょう。4日目になると、腐敗が始まります(38節参照)。
(4)マルタの嘆き
マルタとマリアのところに多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていました。葬儀の弔問客です。当時のユダヤの葬儀は随分長く、1週間位続いたそうです。マルタは、「イエスが来られた」と聞いて、弔問客を家に残したまま、迎えに飛び出していきました。
マルタは、イエス・キリストに向かって、「主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに」(21節)と言いました。どういう思いでこの言葉を語ったのでしょう。少しうらみがましい言葉のようにも聞こえます。「どうしてすぐに出発してくださらなかったのですか。今頃来られてももう手遅れです」。彼女は、まさしく彼女自身の家で、イエス・キリストが不思議な仕方で多くの病人をいやして来られたのを、何度も見てきたことでしょう。「ラザロが生きていさえすれば、どんな瀕死の病気でもいやしてくださる」と思ったに違いありません。
あるいは、何かを期待するというよりも、せめてその場にいて欲しかった。イエス様に看取られて死なせてやりたかった、という思いかもしれません。またもしかすると、別にうらんでいるわけではなく、ただイエス・キリストの顔を見た途端に何か言わずにいられなかったのかもしれません。いずれにせよ、彼女の深い悲しみ、嘆きがこの言葉に表れていると思います。彼女は、こう続けました。
「しかし、あなたが神にお願いすることは何でも、神はかなえてくださると、私は今でも承知しています。」ヨハネ11:22
これはさきの言葉と矛盾するように思えます。彼女は「主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに」と言った後で、「あっ、まずいことを言ってしまった」と思ったのかも知れません。自分で不信仰な言葉だと気づいたのでしょうか。失礼な言葉を語ってしまったという思いもあったかもしれません。「イエス様だって、すぐには出られない事情もあったでしょう。それを考えもせず、ひどいことを言ってしまった。」自分で自分の言葉を一生懸命フォローしようとしたのかもしれません。そうした様子、気が動転している様子が伝わってきます。愛する人を失った時というのは、そういうものではないでしょうか。誰しも、やや支離滅裂になります。
(5)頭の中での理解
マルタの「あなたが神にお願いすることは何でも神はかなえてくださると、私は今でも承知しています」という言葉は、本気ではないのかと言えば、必ずしもそうとは言えません。少なくとも、頭ではそのように理解しています。信仰の論理からすれば、そうなのです。私たちにも同じようなところがあるのではないでしょうか。「神様であれば、何でもできる。イエス・キリストであれば、何でもできる。」その通りです。でも本気で信じているわけではない。そういう思いがあります。彼女も「あなたが神にお願いすることは何でも神はかなえてくださる」と言いながら、兄弟ラザロが、その日のうちに復活させられるということは全く考えてもいないのです。
ですから、主イエスが「あなたの兄弟は復活する」(23節)と言われても、特に何の感動もありません。心は動かず、通り一遍の返事をします。
「終わりの日の復活の時に復活することは存じています。」ヨハネ11:24
当時、ファリサイ派の人々はそう信じていました。ちなみにサドカイ派と呼ばれる人たちは、それと対立して、「復活はない」と言っていました(マタイ22:23~33参照)。マルタはファリサイ派の教えに従って、「自分もそれは信じています」と言ったのです。
(6)最も有名な言葉のひとつ
主イエスは、このマルタの言葉を否定しないで、言葉を続けられました。
「私は復活であり、命である。私を信じる者は、死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も、決して死ぬことはない。」ヨハネ11:25~26
これは聖書の中でも最も有名な言葉のひとつです。私の前任地、経堂緑岡教会の墓地の墓碑にはこの最初の言葉が刻まれていました。ヨハネ福音書11章のラザロの復活物語全体のクライマックスは、この言葉にあると思います。物語全体が、この言葉のためにあると言ってもよい程です。
「私を信じる者は、死んでも生きる」ということと、「生きていて私を信じる者は誰も、決して死ぬことはない」ということは、同じことを裏表で語っています。命の源であるイエス・キリストにつながる時に、死は死でなくなるということです。
本日の聖書箇所から少し前のところ、11章4節に、「この病気は死で終わるものではない」という言葉があります。私たちの人生は、死によって、ある日突然、終わります。切られてしまいます。ところが聖書は、この切断は絶対的なものではないというのです。「これはただ単に肉体の死だ」と。私たちは死によって愛する人と隔てられてしまいますが、命の源であるイエス・キリストとつながることによって、私たちはずっとつながっているのだということです。それが聖書の根幹にあるメッセージの一つです。私たちの前に立ちはだかる肉体的な死、それを超えるものがある。ラザロの復活物語は、それを証しするために、その一つの例として示されているのです。
(7)ボンヘッファーの最期の言葉
私は時々、ボンヘッファーの話をしています。ヒトラー暗殺を企てるほどの地下政治組織にかかわり、それが発覚して処刑されたドイツの神学者です。ボンヘッファーは、1945年4月9日にナチスの手で処刑されますが、それが決定したのはわずか数日前のことでした。彼自身、処刑の数日前まで、自分がいつか釈放されるということを信じていたようです。ヒトラー暗殺計画をもつ組織の一員であったヴィルヘルム・カナーリス提督(海軍大将)の完全な日記がナチスに発見されて、その中にボンヘッファーの名前が組織の一員として記されていたことが決定的となりました。4月5日のヒトラーを囲む国家治安庁中枢部の昼食時の協議の席上でのことでありました。
ボンヘッファーは1945年4月8日、収容所から収容所へと移送中、シェーンベルクという村の小学校に滞在していました。そこで突然、呼び出されてフロッセンビュルク収容所へ移送され、その日のうちに死刑判決を受け、翌日4月9日に処刑されたのでした。
移送中の最期の1週間を共に過ごしたペイン・ベストというイギリス人に、ボンヘッファーは、別れ際にイギリス国教会のチチェスターのベル主教にある伝言を託すのです。ベル主教というのは1932年以来、エキュメニカル運動において、ボンヘッファーと親交のあった人物です。それはこういう言葉でした。
「これが最期です。-わたしにとっては生命の始まりです。」
これは、ボンヘッファーがこの世に遺した最後の言葉として有名になりました。「これが最期です。私にとっては生命の始まりです」。後にベル主教はより詳細に報告しています。
「私にとってはこれが最期です。しかしそれはまた始まりです。あなたと共に、私は、あらゆる国家的な利害を超越するわたしたちの全世界的なキリスト者の交わりを信じています。そして私たちの勝利は確実です。」E・ベートゲ『ボンヘッファー伝』Ⅳ、501頁
ボンヘッファーが肉体の生死を超えたところに、まこと「生」「いのち」を見ていたということが伝わってきます。
(8)命は、主イエスの御手の中に
イエス・キリストにつながる時に、私たちの命は、肉体の死を超えていく。イエス・キリストは、それをマルタに告げ、「このことを信じるか」と言われました。マルタはこう答えます。
「はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じています。」ヨハネ11:27
彼女がどのレベルで信じたのか。どの程度、本気で信じているのか、疑わしいものがあります。この後の彼女のラザロの墓の前での行動を見ていますと、どうも主イエスがおっしゃったことの深い意味は、まだ理解していなかったようです。しかし私は、彼女の応答はそれでも意味があると思うのです。
「このことを信じるか」と言われて、彼女は、とにかく「はい」と答えました。そこには、疑いもあるかもしれません。しかし意識的にそう言いました。これは私たちの信仰告白に似ているのではないでしょうか。一旦、そう告白した後でも、私たちの心は揺れます。本当にそう信じているのかと言われると、疑問もあります。しかし、私たちのそのようなあやふやな信仰告白の上に、私たちの救いがあるのではありません。イエス・キリストがすでに命の主として立っておられるということが根本的に大事なのです。私たちはただそのイエス・キリストの言葉に「はい、主よ、信じます」と応答するだけです。私たちの手の内にではなく、イエス・キリストの御手の内に、私たちの命、救いがある。このイエス・キリストに、私たちも「はい、主よ、信じます」と応答して、新しく歩み始めたいと思います。