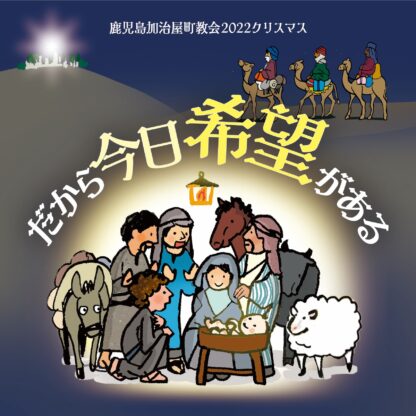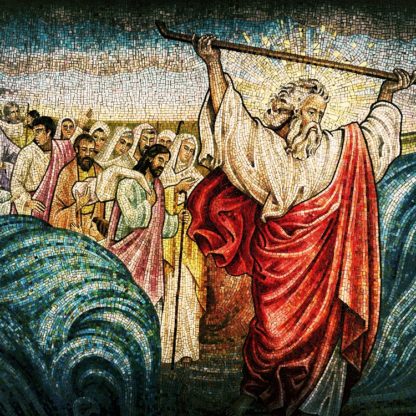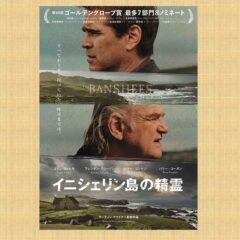2025年4月6日説教「主の言葉は滅びない」松本敏之牧師
イザヤ書40章1~8 ルカ福音書21章25~38節
(1)5つ目の火の消火
受難節第5主日、復活前第2主日を迎え、講壇のキャンドルも5つ目の火を消しました。来週はいよいよ棕櫚の主日、イースターの1週間前の日曜日で、キャンドルのすべての火を消します。聖書の箇所は、ひと月に一度位のペースで読み進めているルカ福音書の21章です。前回の説教プリントを、本日配布しましたが、本日は21章25節以下を読んでいただきました。ルカ福音書21章は、小黙示録と呼ばれ、世の終わりの様子について述べられています。なかなか読みづらい部分であり、しかもわかりにくい部分です。前回のところでは、終末の前兆として、大きな苦難がやってくること、そして、偽メシア、偽預言者が現れることが記され、それに惑わされてはならないと警告されていました。
(2)世の終わりの一つ手前
今日のテキストである25節以下では、こう述べられています。
「そして、太陽と月と星に徴が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂う中で、諸国の民は恐れおののく。人々は、これから世界に起こることを予感し、恐怖のあまり気を失うだろう。天の諸力が揺り動かされるからである。」ルカ21:25~26
これが一体何を意味するのか、理解に苦しむ言葉ですが、当時の世界を根底から揺さぶるようなこと、誰もが想像しえないようなことが起きると、警告しているのでしょう。そして、こう告げるのです。
「その時、人の子が力と大いなる栄光を帯びて雲に乗って来るのを人々は見る。」ルカ21:27
「人の子」というのは、ここではイエス・キリストのことです。イエス・キリストがそのような姿で帰って来るという再臨について述べているのです。孫悟空が「きんと雲」(雲のじゅうたん)に乗ってきたようなイメージでしょうか。そう勝手に想像したりいたします。この情景も、今日の科学を知っている私たちにとっては受け入れがたいものですが、これもまた、私たちの想像をはるかに超える形で、私たちの世界に帰ってこられるという位に理解してよいのではないかと思います。そして、そのような大きな苦難がやってきても、それが終わりではないと励まします。それは終わりの一つ手前の徴だというのです。
「このようなことが起こり始めたら、身を起こし、頭を上げなさい。あなたがたの救いが近づいているからだ。」ルカ21:28
恐ろしい迫害、苦難が起きて世界が終わるのではなくて、本当の最後のところでは、救いが近づいている。そのところにアクセントがあることを見逃してはならないと思います。最終的に恐怖ではなく希望であるということです。
(3)それがいつかは、わからない
ただし、それがいつ起こるのかはわかりません。ここにいちじくの木のたとえが記されています。
「いちじくの木や、ほかのすべての木を見なさい。葉が出始めると、それを見て、夏の近いことがわかる。それと同じように、これらのことが起こるのを見たら、神の国は近いと悟りなさい。よく言っておくが。これらのことが起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。」ルカ21:29~33
こうした前兆が与えられますが、それが「いついつだ」とはわからないのです。そのいつ来るか分からない日を視野に入れて、しかも今、自分に与えられた時を精一杯に生きる。そのような生き方が求められているのです。難しい言葉で言えば、それが終末を生きるということでしょう。
聖書は、いつか世の終わりが来ると語ります。その時には、キリストが帰って来られると語ります。しかしそれがいつかは、わからない。明日来るかも知れないし、来ないかも知れない。1年先かも知れないし、ずっと先かも知れない。いつ帰って来られるかわからないということは、当分帰って来られないことも、もちろん視野に入れて生活しなければならない。カルト宗教が、しばしばもうすぐ終末が来るのだから、「こんな普段の生活は意味がない」と言って、すべてを捨て去せるような(献金させるような)生き方をさせることがありますが、そういうことではありません。それは間違っています。
終わりの日をびくびくして待つのではありません。しかしまた、そのうちに終わりの日が来るからと言って、この世のつとめをおろそかにして生きるのでもありません。宗教改革者のマルチン・ルターは、「明日、世の終わりが来ようとも、私は今日リンゴの木を植える」と言いました。私たちも終末という時を視野に入れつつ、今という時を精いっぱい生きたいと思うのです。
それでも、世の終わりの話は、なかなかぴんと来ないかもしれません。実際に、イエス様の時代から「もうすぐ来る」と言われながら、2000年以上が過ぎてしまいました。しかし、これを私たち一人ひとりの人生の終わりに置き換えてみるならば、それは確実にやってくるわけです。私の人生は必ず終わるわけです。いつかはわからない。突然、明日やって来るかもしれないし、まだまだ先であるかもしれない。そのことを忘れず視野に入れながら、しかしびくびくせずに、のびのびと希望をもって生きる。そういう生き方に通じると思います。
(4)いちじくの枝のたとえ
ちょうどいちじくの枝が柔らかくなり、葉が伸びてくると、夏の近づいたことが分かるように、人の子が近づいた時には、そういう徴があらわれるというのです。そうであれば、私たちはそうした徴を見分ける訓練をしなければならないということになります。神さまからの徴を見分ける訓練をするというのは、何か手っ取り早い方法があるわけではありません。地道に聖書を読み、信仰生活を続けていくということしかないでしょう。ただし「こつ」のようなものはあるかも知れません。 語学とか音楽というようなものは、一人でいくら練習をしてもなかなか伸びませんが、先生にちょっと手ほどきをしてもらうと違うのですね。他の芸術などもそうでしょう。そういう経験をなさったことは多いのではないでしょうか。聖書を読んだり、祈ったりして、信仰生活をするというのは、それに似ているところがあります。それは、聖書の読み方や祈り方というのは、共同体の中で育まれていくものだからです。ひとりでいくらやってもこつが分からない。教会に全く来ないで、ひとりで聖書を読むと、どうでしょうか。もちろんいいことが書いてあるということはわかりますが、何が大事なのか、その中心部分がなかなか分かりません。しかし教会の中で、信仰生活の先輩の姿を見たり、やることを見ながら、次第に育っていくものだと思います。
(5)本物と偽物
刀の鑑定士はどのように訓練するかということを聞いたことがあります。つまり本物の刀と偽物、あるいは真に値打ちのある刀とそうでないものを見分ける訓練です。普通、素人が頭で考えますと、本物と偽物を比べて、「どっちが本物だと思うか。よく比べて見なさい」とか、「そうだ、ここが違うだろう」とか、「色合いが違うだろう」とかするような気がしますが、そうではないそうです。師匠は弟子に本物ばかり、真に価値のあるものばかりを見せ続けるのだそうです。そうするとある価値判断ができるようになって、偽物、まがい物を見ると、「あっ、何かちがうぞ。ちょっとおかしいぞ」とぴんと来る、というのです。つまり特に偽物を見せる必要はないのです。
話は少し広がりますが、マルチン・ルターは、「神は教会を建て、サタンはチャペルを建てる」と語ったそうです。神が教会を建てるのを横目で見ながら、サタンはそれとそっくりのものを建てる。しかしそれは形だけで、神は宿っていない。偽物だ」ということでしょう。
私は、信仰の訓練も、鑑定士の本物を見抜く訓練に似たところがあると思いました。つまり本物の信仰、本物の福音に触れ続けていれば、そうではないものに出会った時に、「何かおかしいぞ。何か違う」「何が違うかはよくわからないけれども、これは、私が聞いてきた福音とは違う」という風に偽物を見分けることができるようになるのではないでしょうか。偽預言者や偽キリストというのも、本物のキリスト、本物の福音に触れていない人こそ、ひっかかるのではないかと思います。そういう意味では、教会というところは、私たちが真実なものに触れる、真実なものに出会う場所であると言えると思います。
私たちの世界にはさまざまな思想が氾濫しています。さまざまな宗教があります。その中には人が飛びつくようなものも無数にあります。すぐに役立つハウツーもののような知識がもてはやされる。せいぜい十年くらいしかもたないような、薄っぺらい思想が次々と出てまいります。宗教でもすぐに答を与えてくれるような宗教、「一生懸命働いたら金持ちになれる」というようなわかりやすい約束をしてくれるような新興宗教は流行ります。
しかし私たちが信じているキリスト教というのは、必ずしもそうではない。ある部分では突き抜けるように単純明快でありつつ、ある部分では非常に難解です。「なぜ正しい者が苦しまなければならないのか。」そういう不条理のようなことまで、きちんと視野に入れているからです。人間は一体どこから出てどこへ帰っていくのか。死ということも恐れずきちんと直視している。いくら学んでも学び尽くすことがない程、奥深いものです。そうした学びをし、教会の中でそうした交わりに加え入れられる時に、私たちは生涯にわたっていかに生きるかということを学んでいくのです。
(6)いつも目を覚まして祈っていなさい
34節以下では、こう警告されます。
「二日酔いや泥酔や生活の煩いで、心が鈍くならないように注意しなさい。さもないと、その日が罠のように、突如あなたがたを襲うことになる。その日は、地の面のあらゆるところに住む人々すべてに、襲いかかるからである。しかし、あなたがたは、起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈っていなさい。」ルカ21:34~36
ルカ福音書は、ここで一つの区切りを終えて、22章から受難物語に入っていきます。次の37節、38節は、その結びの言葉であります。受難物語に入りますと、ユダの裏切りから始まって、最後の晩餐の記事があり、その後、オリーブ山での祈り(ゲツセマネの祈り)があります。イエス・キリストは、弟子たちを連れて、神様と葛藤するような祈りをされました。しかし、弟子たちはそのそばで眠ってしまいました。「心痛のあまり眠り込んでいた」とあります。そこへ主イエスがやって来て、「なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう、起きて祈っていなさい」と言われました。先ほどの「人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈っていなさい」(21:36)という言葉に通じるものがあります。もっとも私たちの体力や気力にも限界があります。ずっと起き続けていることはできません。ですから全く眠らないのではなく。しかるべき準備を整えて眠ることが重要だと思うのです。
それはマタイによる福音書25章の最初に記されている「10人のおとめ」のたとえに通じます。花婿の到着をまつ10人のおとめのうち、賢い5人はランプの油の用意をして眠っていました。愚かな5人の乙女は、油の準備をしないで眠っていました。「花婿の到着だ」という時に、みんな飛び起きるのですが、油の準備をしていた5人はあわてませんでした。油の準備をしていなかった5人は間に合いませんでした。賢い5人は眠っていなかったというのではないのです。その違いは、適切な備えをしていたかどうかということでした。 また「お酒を飲んではいけない」とは書いてありません。「二日酔いや泥酔はよくない。」ですから飲むにしても適度にしておきなさい、ということなのでしょう。「二日酔いや泥酔をするほど飲んではいけません」ということなのでしょう。
(7)神の言葉はとこしえに立つ
33節の「天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない」という言葉にもう一度、注意しましょう。天地は滅びるのです。天地とは、私たちの住んでいるこの世界のことです。その世界に住んでいる私たちも滅びるのです。この地上からいつか跡形もなく消えていく日が来るのです。形あるものはいつか必ず滅びます。そのことから目を背けてはならない。
今日は旧約聖書のほうはイザヤ書40章の言葉を読んでいただきました。その中にこういう言葉がありました。
「すべての肉なる者は草 その榮はみな野の花のようだ。 草は枯れ、花はしぼむ。 主の風がその上に吹いたからだ。 まさしくこの民は草だ。 草は枯れ、花はしぼむ。 しかし、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。」イザヤ書40:6~8
私たちもいつかは死ななければなりません。死から目を背け続けて、そんなことも考えないまま、知らないうちに召される方が幸せだ、という人もいますが、それはどうかと思います。私たちは死を恐れなくてもいいのです。なぜなら私たちはその滅びを突き抜けたところに希望があることを知っているからです。死を超えた希望をすでに与えられているからです。
「天地は滅びる。しかしわたしの言葉は決して滅びない」。私たちは塵から作られたから、塵へと帰っていきます。天地は無から作られたから、やがて無に帰っていくのです。しかしその天地を造り出したのは、主の言葉です。「光あれ」と言われると、光があったように、主の言葉が先にあった。私たちを塵から生きるようにさせたのも、主の言葉と息です。天地は滅びても、それを造り出した神の言葉は決して滅びないと、言っておられるのです。主は、ただ滅びだけを語られたのではない。ただ私たちを脅かしておられるのではない。警告を与え、滅びない永遠のものを指し示しつつ、あなたもこの希望に連なりなさいと、招いておられるのです。
「人はパンだけで生きるものではなく 神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。」マタイ4:4
この主の言葉は私たちを滅びのない世界へと招き入れるものです。私たちも終わりの日までこの言葉に連なり、イエス・キリストに連なって生きるものとなりましょう。