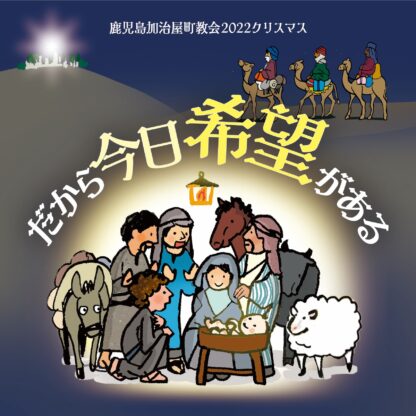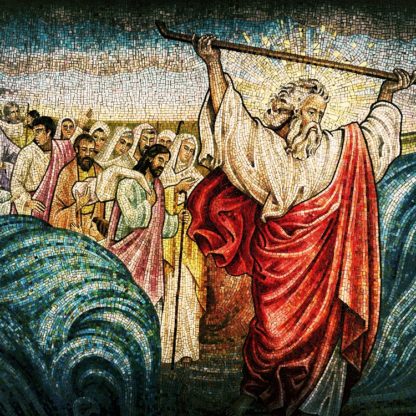2025年11月2日説教「誘惑に陥らないように」松本敏之牧師
イザヤ書53:7~12 ルカによる福音書22:35~46
(1)主イエスの意外な言葉
前回(10月5日)に、ルカ福音書22章31~34節の「主イエスとシモン・ペトロとの対話」の部分を読みました。最後に、もう一度弟子たち(使徒たち)に向き合われて、こう言われました。いよいよ、主イエスが使徒たちと直接話をされた最後の言葉です。
「財布も袋も履物も持たせずにあなたがたを遣わしたとき、何か不足したものがあったか。」ルカ22:35
最初に彼らが主イエスから遣わされた時のことを思い起こさせて、励まされたのでしょう。この言葉は、ルカ福音書9章3節のところで語られた言葉でした。使徒たちは、「何もありませんでした」と答えます。彼らはなつかしく思い起こすと同時に、主イエスの言葉に勇気づけられたことでしょう。ところが、それに続く主イエスの言葉は意外なもの、意表を突くものでした。
「しかし今は、財布のある者は、それを持って行きなさい。袋も同じようにしなさい。剣のない者は、衣を売って剣を買いなさい。」ルカ22:36
この言葉に、使徒たちは大いに戸惑ったことでしょう。同時に、この言葉を読む後のクリスチャンたちも戸惑い、私たちも戸惑います。なぜこのような言葉を語られたのか。ひとつには、今は大変な非常時であるということを告げている。そのために、自衛のために武装することを許可されたということではないかと思います。事実、その後に彼らが、「主よ、剣なら、ここに二振りあります」(38節)と言った時には「それでよい」と答えられました。「十分だ」と訳している聖書もあります(本田哲郎訳)。
(2)「苦難の僕」を引き受けて
非常時というのは、このすぐ後、主イエスご自身が逮捕されてしまうからです。そのことを彼らに告げようとしておられるのです。それは、主イエスが、次のように言われたことからもわかります。
「『彼は犯罪人の一人に数えられた』と書いてあることは、私の身に必ず実現し、事実、私に関わることが今、実現しているのだ」ルカ22:37
この「彼は犯罪人の一人に数えられた」という言葉は、先ほど読んでいただいたイザヤ書の最後の言葉、53章12節からの引用です。
「彼が自分の命を死に至るまで注ぎ出し 背く者の一人に数えられたからだ。 多くの人の罪を担い 背く者のために執り成しをしたのは この人であった。」イザヤ書53:12
これは、メシア預言と呼ばれる「苦難の僕の歌」の締めくくりの言葉です。それを、ご自分の身に引き受け、重ね合わせられたのでした。もっともそこには、ルカ福音書が書かれた時代のルカの信仰の目を通しての言葉であることは否めませんが、そうだとしても、主イエスは、このイザヤ書の預言の通りに、十字架にかかられていくのです。
(3)オリーブ山の祈り
そして、ルカはこう続けます。
「イエスはそこを出て、いつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従った。」ルカ22:39
マタイ福音書やマルコ福音書では、わざわざ「ゲツセマネ」という名前をあげて、それが特別な祈りであったことを強調していますけれども、ルカはむしろ、いつものように「オリーブ山に」というふうに、この特別な祈りも、日常の祈りの延長線上にあったということを告げようとしているようです。そして、弟子たちもこの祈りに従いました。これも日常のことであったかもしれません。ただし「石を投げて届くほどの所」という、弟子たちとつかず離れずの距離で祈られます。面白い表現です。「姿は見えないけれども、すぐそば」、ということでしょうか。弟子たちに、祈りの課題として示されたのは「誘惑に陥らないように」ということでした。この言葉は、最後の46節に、もう一度、出てきます。
「なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう、起きて祈っていなさい。」ルカ22:46
これは主の祈りにも出てくる言葉です。
「私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。」
この時も、これまで弟子たちの教えてこられた、この祈りを思い起こさせようとされたのかもしれません。普段、何気なく祈っている言葉も、この時は特別な意味をもっていました。 そしてイエス・キリスト自身も、この時、「誘惑に陥らせないでください」と切実に祈っておられたのではないでしょうか。
主イエスは、こう祈られました。
「父よ、御心なら、この杯を私から取りのけてください。」ルカ22:42
それにしても不思議なのは、どうしてこのような祈りをなさったのかということです。「神の子」としてはちょっと情けないようにも見えます。往生際が悪いという感じさえします。私たちは、もっと立派に死んでいった偉人をたくさん知っています。ソクラテスなどもその一人です。キリストの弟子たちでさえ、もっと堂々と殉教していった人が数え切れないほどたくさんいます。その本家本元のイエス様が、いったい死を前にして、ここで何を恐れておられるのでしょうか。総督ピラトでしょうか。ユダヤ人たち(最高法院)でしょうか。群衆でしょうか。それとも死そのものでしょうか。 主イエスはかつてこう言われました。
「体を殺しても、その後、それ以上何もできない者どもを恐れるな。」ルカ12:4
もしもイエス様がピラトや肉体の死を恐れていたとすれば、自分の言葉どおりに生きられなかったことになってしまうでしょう。私はそうではないと思います。ご自分でおっしゃったとおり、主イエスはそんなものは何も恐れてはおられなかった。それでは何を恐れていたのでしょうか。実は先ほどの(ルカ12章の)主イエスの言葉の続きにヒントがあります。
「誰を恐れるべきか、教えよう。それは、殺した後で、ゲヘナ(陰府、地獄)に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ。言っておくが、この方を恐れなさい。」ルカ12:5
そうです。主イエスは、ピラトを恐れたのでも、肉体の死を恐れたのでもなく、まさにこのお方、「殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っている方」 を恐れておられたのです。なぜならその方は、今まさにイエス・キリストをゲヘナ(陰府)へ投げ込もうとしておられたからです。
(4)最も重大な夜
私たちは、この夜、人類の歴史を決定するとてつもなく重大なことが天の父なる神様とイエス・キリストの間で語り交わされたことを知らなければなりません。神の子が十字架にかかって殺されるということが避けられないものとして、この夜、最終確認されたのです。
父なる神様にとっても自分で苦しみもだえるほどの闘いであったに違いありません。自分のひとり子を十字架にかけて殺し、陰府にまで突き落とすというのは、はらわたのちぎれるような決心であったことでしょう。しかし人を救うにはこの道しかないと決断されたのでした。私たちの神は全能の神です。できないことは何一つありません。その全能の神が全能の中で選び取られた道でありました。そこで主イエスの心は定まっていくのです。
「しかし、私の願いではなく、御心のままに行ってください。」ルカ22:42
ルカでは、この二つの祈りが続けて記されていますが、主イエスはこの二つの祈りを何時間もかけて行ったり来たりなさったのではないでしょうか。そして最後には、この父なる神の決定を受け入れられました。この決定的な夜に、弟子たちはすぐそばで眠りこけています。何というコントラスト、何という皮肉な光景でしょう。ただこの光景は私たちの現実を象徴しているようでもあります。しかし反対に言えば、私たちが何も知らないで眠りこけている瞬間にも、イエス・キリストはすでに私たちを根源的に支える決定的なことを決意し、しかも始めておられるということを覚えたいと思うのです。
(5)仲間の裏切りという誘惑
一つ目は、「仲間の裏切りを目の当たりに見る」という誘惑です。この時、主イエスと三人の弟子たちのところへやってきたのは、イスカリオテのユダと大勢の群衆でした。この群衆の多くは、恐らくつい数日前まで、主イエスの話を喜んで聞いていた人々です。
しかしさらに驚かされたのは、その群衆の先頭に立って誘導していたのがイスカリオテのユダであったということでしょう。ここでわざわざ「十二人の一人であるユダという者」(48節)と書かれています。このユダは、ヨハネ福音書によれば、弟子たちの財布を預かっていた人でした(ヨハネ13:29)。お金を預かるのは、みんなが最も信頼する人でしょう。その人が主イエスを売り渡してしまうのです。「信頼する仲間に裏切られる」というのは大きなつまずきであり、誘惑であります。
(6)「自分が守る」という誘惑
二つ目は「自分がこの手で守る」という誘惑、あるいはそのために「剣を取る」という誘惑です。群衆がにじり寄って、主イエスを捕らえようとした時、弟子の一人が、大祭司の手下に打ちかかって、片方の耳を切り落とすことになります。主イエスは自衛のために剣をもつことは許可されましたが、それで相手を切りつけることをしろとは言われませんでした。別の福音書では「剣を取る者は剣で滅びる」とも言われています。実際、主イエスは、この時、その大祭司の僕の耳をいやしてやりました。
(7)主イエスが何もなさらないという誘惑
三つ目の誘惑は、まさにそこにあります。「どうして主イエスは今、その力をお見せにならないのか」「どうして神は沈黙しておられるのか」ということです。ここで、イエス・キリストは、人間の眼には本当に無力です。ただすごすごと捕まってしまいます。
今日においても同じ誘惑があるでしょう。悪がはびこり、不義がまかり通っています。「どうして神様は何もなさらないのか」「神が今その力を見せてくださらなければ、いったいいつお見せになるのか」「神がおられるのであれば、どうしてこんなことが起きるのか」。極限状況に立たされる時、人はそう思います。「やはり神はおられないのではないか」。
二〇一一年の東日本大震災においても聞かれた声です。これは私たちにとって、最大のつまずきであり、不信仰への誘惑ではないでしょうか。
(8)イエスを裏切るという誘惑
そしてそのことに由来していますが、四つ目は、主イエスを裏切るという誘惑です。この後、弟子たちはみんな逃げてしまいます。シモン・ペトロも、「主よ、ご一緒になら、牢であろうと死であろうと覚悟しております」(ルカ22:33)と言ったにもかかわらず、主イエスを否定することになってしまいます。私たちはそれほど弱いのです。
弟子たちは、そのような誘惑に取り囲まれていましたけれども、主イエスは「誘惑に陥らないように祈っていなさい」と言われると同時に、そうした弟子たちが誘惑に陥らないためにも祈ってくださったということを、心に留めたいと思うのです。そして同時に、そのような弱い私たちのためにも祈っていてくださるということを心に留めたいと思います。
(9)ボンヘッファーの獄中詩
今日は、この後、「善き力にわれ囲まれ」という賛美歌を歌います。これは、ディートリヒ・ボンヘッファーという神学者・牧師であった人の詩に基づいて作られた賛美歌です。ボンヘッファーは、ナチス・ドイツの時代に、ナチス政府に屈しない教会の抵抗運動を起こしましたが、それもやがて挫折していきます。そして最後にヒトラー暗殺をも企てる地下組織に加わっていくのですが、些細なことからそれが発覚して投獄され、最後には処刑されていきます。1945年4月9日、連合軍がナチス軍を破るわずか数週間前のことでありました。そのボンヘッファーが、1944年の年の終わりに、獄中で書き残した詩です。
「主のよき力に守られて」という題がつけられています。直訳すると、こういう言葉です。
「主のよき力に、確かに、静かに、取り囲まれ、 不思議にも守られ、慰められて、 私はここでの日々を君たちと共に生き、 君たちと共に新年を迎えようとしています。
過ぎ去ろうとしている時は、私の心をなおも悩まし、 悪夢のような日々の重荷は、私たちをなおも圧し続けています。 ああ主よ、どうかこのおびえおののく魂に、 あなたが備えている救いを与えてください。」
そして、こう続けるのです。
「あなたが、もし、私たちに、苦い杯を、苦渋にあふれる杯を、 なみなみとついで、差し出すなら、 私たちはそれを恐れず、感謝して、 いつくしみと愛に満ちたあなたの手から受けましょう。」
これは、イエス・キリストの今日の「オリーブ山の祈り」をほうふつとさせる言葉です。 ボンヘッファーは続けます。
「深い静けさが私たちを包んでいる今、この時に、 私たちに聞かせてください。 私たちのまわりに広がる、目に見えない世界のあふれるばかりの音の響きを、 あなたのすべての子供たちが高らかにうたう讃美の歌声を。
主のよき力に、不思議にも守られて、 私たちは来たるべきものを安らかに待ち受けます。 神は、朝に、夕に、私たちと共にいるでしょう。 そして、私たちが迎える新しい日々にも、神は必ず、私たちと共にいるでしょう」。 村椿嘉信訳
(10)二つのメロディー
この歌にメロディーがつけられ、賛美歌にもなっているのですが、『讃美歌21』にも、469番として出ています。しかし、今日はもう一つのメロディーのほうで歌いたいと思います。バプテスト教会が出している「新生讃美歌」に収録されているほうのメロディーです。
困難を感じながらも、それで自分が突き放されているわけではない。「不思議な、よき力に囲まれている」。その確信があるからこそ、不思議な安心感があり、困難の中を進みゆくことができるのです。苦い杯をも選び取っていく勇気が与えられるのです。
主イエスも、オリーブ山で「父よ、御心なら、この杯を私から取りのけてください」と祈りつつ、「しかし、私の願いではなく、御心のままに行ってください」と祈られました。その時、どんな弟子たちが無理解で、眠りこけていようとも、不思議な、よき力に取り囲まれていることを感じておられたのではないでしょうか。
私たちも、多くの問題、課題を抱えつつも、そして不安を抱えていようとも、誘惑からも守られて、「善き力に囲まれて」守られていることを信じて、歩んでいきたいと思います。