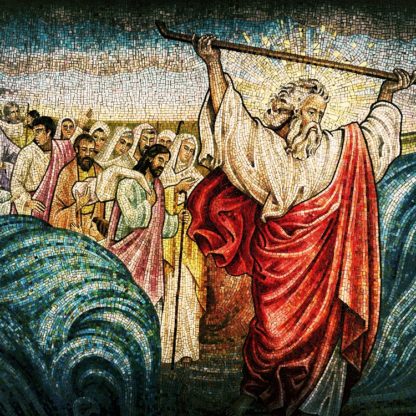2025年8月3日説教「逆転しない正義」松本敏之牧師
詩編85, 9-14
マタイによる福音書10:32~39
(1)NHKの朝ドラ「あんぱん」
8月は、日本では平和を祈る季節です。日本基督教団では、8月第一日曜日を「平和聖日」と定めています。
本日も、日本基督教団の「戦争責任告白」を共に唱和しました。また毎年、在日大韓基督教会と日本基督教団の両議長名で発表される「平和メッセージ」をあわせて配布しました。今年の平和メッセージは、例年のもの比べて、ちょっと難しいと言うか、少し思想的に掘り下げたものとなっています。恐らく起草者が変わったのでしょう。説教で取り上げることはしませんので、どうぞ各自お読みください。
さて鹿児島加治屋町教会では、毎年、この平和聖日に、鹿児島ユネスコ協会と共催で、「平和の鐘を鳴らそう」という行事を行っています。今年も、それにあわせて鹿児島ユネスコ協会関係者の方々が、何人か礼拝から出席してくださっています。
本日の説教題を「逆転しない正義」としました。皆さん、この言葉をご存じでしょうか。聖書の言葉ではありません。この言葉をご存じの方は、NHKの「朝ドラ」「あんぱん」を観ておられますね。我が家では、朝8時は、幼稚園のお祈りの時間なので、録画をして夕食時に観ています。今回の「あんぱん」は「朝ドラ」史上、視聴率でも歴代何位かになるほど、なかなか人気があるようです。放送開始時に公開されたNHKのホームページによると、こう記されています。
「戦後80年を迎える2025年。第112作目の連続テレビ小説『あんぱん』は、“アンパンマン”を生み出したやなせたかしと小松 暢(こまつ・のぶ)の夫婦をモデルに、生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかった二人の人生。何者でもなかった二人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描き、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語です。」2025年4月26日
先週の月曜日(7月28日)に放映された番組では、こういう場面がありました。主人公の柳井崇が、将来妻となるのぶを追いかけて、高知の新聞社を辞めて、「東京に行きたい」ということを編集長に伝えた後の、編集長の言葉です。
「仕事よりも大変な使命がある。入社試験でお前はこう言いよった。『例えば、自分が正義だと思っていても相手の立場になれば、自分は悪になってしまう。何が正しいのか。逆転しない正義とは何か。のぶもおんなじことを言いよった。お前とのぶは性格も行動力も正反対やけんど、根っこのところが似ちゅうがかもしれんにゃ。何年かかっても、何十年かかっても、ふたりでその答えを見つけてみい。わかったな。」
そういう言葉です。柳井崇は、「はい。ありがとうございます」と言って、去っていきます。「のぶもおんなじことを言いよった」というのは、彼女は、戦時中は軍国主義教育の先頭をきって行くような小学校教師だったのです。戦争が終わったとき、彼女は子どもたち前で、ふかぶかと頭を下げて「先生はまちごうちょりました」と言って、教壇を去っていったのです。その経験について入社試験で述べたのでありました。
(2)「逆転しない正義とは献身と愛」
モデルとなっているアンパンマンの作者、やなせたかし氏は、「逆転しない正義」とは何かを求めて、やがて「アンパンマン」というキャラクターにたどり着くのです。それはヒーローらしくないヒーローです。弱々しくて、正義を主張せず、相手を完全に否定することはしません。そして自分の頭であるアンパンを差し出して、相手を生かすヒーローです。相手を完全に打ち負かさないというのは、例えば「アンパーンチ」と」言って「ばいきんまん」にパンチを浴びせると、ばいきんまんは「バイバイキーン」と言って飛んで行ってしまうのですが、翌週になると、何事もなかったかのように、また元気に登場します。
やなせたかしさんは、2013年に94歳で亡くなっていますが、その年に、児童向けに『わたしが正義について語るなら』という本を出版し、それがこのドラマの放映が決まった2024年に新書本として復刊しました。その中で、やなせさんは、こう述べています。
「聖戦だと思って行った戦争だって、立場を変えてみればどうでしょう。中国の側から見れば侵略してくる日本は悪魔にしか見えません。そうして日本が戦争に負け、すべてが終わると日本の社会はガラッと変化しました。それまでの軍国主義から民主主義へ。それまでは天皇が神様だと言っていたのに、急にみんな平等だ、民主主義だと言われるようになりました。……正義のための戦いなんてどこにもないのです。正義はある日逆転する。逆転しない正義とは献身と愛です。」『わたしが正義について語るなら』20~21頁
朝ドラでは、まだこの言葉は出てきません。やがて、崇とのぶは、何十年かかかって、この結論にたどりつくのでしょうか。「逆転しない正義とは献身と愛です。」ネタバレになっていたら、ごめんなさい。「逆転しない正義とは献身と愛です」という言葉の「献身と愛」というのは、イエス・キリストがその生き方そのものです。いや生き方だけではありません。十字架という死に方を含めて、つまり身をもって証しされたこと、そこにこそ真実があると示されたことです。やないたかしさんはクリスチャンではなかったようですが、だれよりもクリスチャン的です。というと、やなせたかしさんに叱られそうですが。「私はクリスチャンではありません。クリスチャンは、もっと戦闘的でしょう」と。でも確かに、どの国にもいるようなあやしいトップ政治家のクリスチャンよりも、よほどイエス様の考えに近いです。あやしいクリスチャン・トップ政治家というのは、アメリカにもロシアにもいます。(あっ、日本にもいましたね。)
(3)正義と平和が口づけする
先ほどは詩編85編を読んでいただきましたが、その中にこういう言葉がありました。
「わたしは神が宣言されるのを聞きます。
主は平和を宣言されます。」詩編85:9
主の宣言される平和とは、一体どういう平和なのでしょうか。詩編はこう続きます。
「慈しみとまことは出会い
義と平和は口づけする。
まことは地から芽生え
義は天から目を注ぐ。」詩編85:11
以前の新共同訳聖書では、「義」というのを「正義」と訳していました。
「慈しみとまことは出会い、
正義と平和は口づけし、
まことは地から萌えいで、
正義は天から注がれます。」詩編85:11、新共同訳
何と美しい言葉、しかも何と奥深い言葉でしょう。これは私の大好きな聖句の一つですが、聖書の中でも最も大事な言葉の一つであると思います。正義と平和が口づけするのです。
人は「正義のために戦争をするのだ」と言います。しかしその正義は、本当の正義ではないでしょう。平和と口づけをしていないからです。一方、差別され、抑圧されている人に我慢を強要しながら、平和を口にするのは本当の平和ではないでしょう。その平和には正義が存在していないからです。「慈しみとまことは出会い」とあります。「慈しみ」とは「愛」と言い換えてもよいでしょう。「まこと」とは真実です。主が宣言される平和のもとでは、「愛」と「真実」が出会い、「正義」と「平和」が口づけをするのです。
イエス・キリストとは、まさにこの言葉が受肉したような方ではなかったでしょうか。この方のもとでこそ、この詩編の言葉は出来事となったのです。このような「主の平和」は忍耐を要し、多くの人々の利益にも反するものですから、嫌われます。そのような道を歩もうとする者、イエス・キリストの弟子であろうとする者は、多かれ少なかれ、逆風の中を生きることを強いられるのです(35~36節参照)。
(4)平和の主
さて、本日、読んでいただいたもう一つの聖書個所、マタイ福音書10章32節以下に、目を留めてみましょう。34節にこういう言葉がありました。
「私が来たのは地上に平和をもたらすためだ、と思ってはならない。平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ。」マタイ10:34
イエス・キリストのこの言葉を聞いて、当惑しない人はいないのではないでしょうか。イエス・キリストは「平和を造る人々は幸いである」(マタイ5:9)と言われましたし、「敵を愛しなさい」(マタイ5:44)とも言われました。それが、ここでは急に好戦的になってしまったかのようです。何だか宗教戦争を正当化しているようにも聞こえてしまいます。しかしそうではないでしょう。私は、深いところではやはり、イエス・キリストは平和をもたらすために来られたのに違いないと思います。ただ主イエスのもたらされる平和というのは、私たちが普通考えるような平和ではないということを、強い言葉で言おうとされたのではないでしょうか。
(5)二つの「平和もどき」
主イエスのもたらす平和は、単に表面的に争いのない状態ではありません。表面的に争いはないけれども、本当の平和ではない状態として、いわば二つの「平和もどき」が考えられるのではないかと思います。
一つは、力と抑圧によって相手を封じ込めることによる「平和」です。古代ローマ帝国の時代に、パックス・ロマーナ(ローマの平和)と呼ばれる比較的穏やかな時代がありました。それはローマ帝国が圧倒的に強い軍事力をもっていたので、周辺諸国が刃向かわなかったのでした。しかしその状況をよく見てみると、特権階級がいて、そのもとで犠牲になって働く人が大勢いて、社会が成り立っている。そのしくみをくつがえさないように、武力で押さえつけているのです。弱い立場の人に我慢を要求し、平和の名のもとに人権を侵害し、自由を奪っている。その圧政のもとで、飢えている人もたくさんいたのです。これは真の平和であるとは言えないでしょう。
やなせたかし氏は、飢えた子どもを助けることが一番大事なんだ。……ところが彼ら(正義のヒーローたち、スーパーマンやスパイダーマン)は、飢えた人を助けに行くとか、そういうことは全然やらないのですね。……ぼくが何かをやるとしたら、まず飢えた子どもを助けることが大事だと思った。それが戦争を体験して感じた一番大事なことでした」(前掲書16~19頁)と言っています。
さて、もう一つの「平和もどき」は、安易な和合です。私たち、特に日本人は、これが好きです。あまり事を荒立てることを好みません。ちょっと違った意見を言うと嫌われます。本当は和解していないけれども、現状維持を望むの。こういう状況は、一見平和に見えます。穏やかです。しかし問題は何も解決せず、先送りにしているだけです。確かに暴力をふるい、ことを解決しようとする野蛮な考えよりはずっとましなのかも知れませんが、根は同じなのではないかという気がいたします。
M・L・キング牧師を中心とする公民権運動の時にも、このような安易な和合を呼びかける人たちがいました。それは白人の穏健派クリスチャンと呼ばれる人たちでした。彼らは温和な人たちでしたが、決して体制が変わることまでは望んでいなかったのです。彼らは黒人たちに向かって、「時代は少しずつ変わってきている。もう数十年もすれば、白人と同じ権利が与えられるから、そう急ぐな。もう少し落ち着いて待て」と言って、過激な行動に走ろうとする黒人たちをいさめたのでした。しかしキング牧師は、そういう助言に対して、「待て」(Wait!)という言葉は「決して与えない」(Never!)という風に聞こえる。自分たちはもう300年以上、待ち続けたのだ」と言いました。
ことを荒立てないことを好む人は、往々にして、自分は損をしない立場にいながら、犠牲になっている人に向かって、妥協を呼びかけることが多いのではないでしょうか。相手に対する理解も、同情も見せる。しかしながら、本質的に抑圧者と同じ差別をしている。いわば役割分担のようなものです。
キング牧師は、「真の平和とは、単に緊張がないだけではなく、正義が存在することである」と述べました。意味深い言葉であると思います。「真の平和とは、単に緊張がないだけではなく、正義が存在することである」その「平和」は正義と口づけしていなければならない。逆に言えば、その正義は「平和」と口づけしていなければならないということになるでしょう。
(6)イエス・キリストの歩まれた道
私たちは、イエス・キリストご自身が、そのような道において殺されたということを忘れてはならないでしょう。イエス・キリストの語ったことは、かえって平和を乱すものだ、一見平穏に見える社会に、あえて波風を立てるものだと思われたのでした。イエス・キリストは、「平和は造るもの、造り出すものだ」と言われました。
やなせたかしさんは、別の本『何のために生まれてきたの?』という本の中で、こういうことを述べておられます。
「自分がまったく傷つかないままで、正義を行うことは難しい。」『何のために生まれてきたの?』54頁
「正義を行う人は、自分が傷つくことを覚悟しなくちゃいけない。…正義には一種のかなしみがあって、傷つくことがあるんです。そんなにかっこいいもんじゃない。」前掲書59頁
そして先ほどの本では「正義は勝ったと言っていばってるやつは嘘くさいんです」(『わたしが正義について語るなら』122頁)と言っています。
「だから、みんな傷つきたくないから正義なんてやらない。長いものには巻かれろとまかれてしまうわけ。…それではいけないのですね。傷ついてもやらなくちゃいけない。そうしないと世の中はどんどん悪くなってしまうんですね。敢然として自分が傷つくことを恐れずにやらなくちゃいけない」(前掲書127~128頁)と語ります。
この「正義」というのは、私の今日の説教のことばで言えば、「平和」と言い換えられるかもしれません。やなせさんは、「自分がまったく傷つかないままで、正義を行うことは難しい」と言いましたが、「自分がまったく傷つかないままで、平和を造る(実現する)ことは難しい」と言ってもよいように思います。
イエス・キリストは、「(私は)平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ」と言われましたが、その剣は、人に向けてではなく、まずイエス・キリストご自身に向けられた剣であったと言えるでしょう。「傷つく」ことを恐れず、敢然とそれをなさった方でありました。私たちも主イエスの弟子として、それに続くものでありたいと思います。