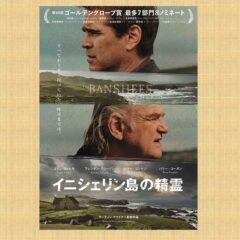2025年10月5日説教「あなたのために祈った」松本敏之牧師
ヨブ記1:6~12
ルカによる福音書22:31~34
(1)世界聖餐日・世界宣教の日
本日、10月の第一日曜日は、世界聖餐日、そして世界宣教の日です。世界聖餐日というのは、最初は、「第二次世界大戦の前に、アメリカの諸教派でまもられるようになったもので、戦争へと傾斜していく対立する世界の中で、キリストの教会は一つであることを、共に聖餐にあずかることによって確認しようとしたもの」です。その意味では、今も、そうしたことが最も求められている時と言えるかもしれません。「戦後、日本キリスト教団でもまもられるようになり、同時に、『世界宣教の日』として、キリスト教会は主にあって一つなのだから、世界宣教を共に担う祈りと実践の日と定め」られました(大宮溥、『信徒の友』2004年10月号より)。
世界が一つであるために、まず教会が一つであらねばならない。そのためにはまず共に聖餐をまもること、一緒にまもることが無理でも、それぞれの聖餐式で、世界の教会に思いをはせること、教派の違いを超えて祈りあうこと、国を超えて祈りあうこと、それが出発点だということが込められているのではないでしょうか。
私たちは、昨年の世界聖餐日には、ブラジル長老教会の日系三世である榛葉ルイス牧師を説教者としてお迎えして、「一致」という題で、説教していただきました。母語はポルトガル語の先生ですが、力強い日本語で、違いを超えて一致することの大切さについてお話しくださいました。
世界聖餐日・世界宣教の日にあわせて、日本基督教団世界宣教委員会は、世界各地で働く日本基督教団派遣宣教師、または関係教会の報告を載せた『共に仕えるために』という小冊子を、毎年発行しています。ここ数年、『共に仕えるために』を手にして、海外で働く日本人宣教師の数がずいぶん減ったなと思っています。毎年、楽しみにしていた、南アメリカからの報告もなくなってしまいました。鹿児島加治屋町教会にも来て説教をしていただいたことのある小井沼眞樹子宣教師は、宣教師は隠退されましたが、サンパウロに住んで、日系人のお年寄りのためのデイサロン。デイサービス、シャロームの運営に携わっておられます。昨年、出版された『ただそこに居なさい! 小さな宣教師のブラジル通信』という、これまでの宣教師生活の総決算であるご著書を、ご寄贈いただきました。図書に入れましたので、どうぞ手に取ってご覧ください。
(2)本日の聖書個所との関連
さて今日は、少しずつ読み進めているルカによる福音書の続き、22章31節から34節を読んでいただきました。「ペトロの離反を予告する」という題が付けられています。このところは、世界聖餐日、世界宣教の日とあまり関係がないように見えるかもしれません。しかし深いところで、その両方と関係しています。
まずこれは、イエス・キリストと弟子たちが最後に交わされた会話の部分だということ、つまり最後の晩餐における会話、言い換えれば、最初の聖餐式の場での会話だということです。それが世界聖餐日につながっていくことです。もうひとつは、この時に主イエスが語られた言葉、「だからあなたが立ち直ったときには、兄弟たちを力づけてやりなさい」という励ましの言葉が、ペトロの宣教活動への原動力となり、それが世界宣教の基となっていったと言えるからです。
(3)主イエスと共に踏みとどまった弟子たち
今日は31節から読んでいただきましたが、前回、その前の部分、28節以下について触れることができませんでしたので、そこから見ていきましょう。
24節から27節の部分では、最後の晩餐の席で、弟子たち(使徒たち)の間で「誰が一番偉いだろうか」という議論がなされていました。イエス・キリストは、少しそれをいさめるようにして、「あなたがたの中でいちばん偉い人は、いちばん若い者のようになり、上に立つ人は、仕える者のようになりなさい」(26節)と言われました。そしてその後は、少しトーンが変わります。こう言われました。
「あなたがたは、私が試練に遭ったときも、私と一緒に踏みとどまってくれた人たちである。」ルカ22:28
少し持ち上げておられるようです。何を指して、主イエスがそう言われたのか、よくわからないところもあるのですが、それまでの宣教活動を全般的に振り返って、弟子たちをほめて自信を与えようとしているのかなと思います。というのは、その前に、イエス・キリストは弟子たちに、「言っておくが、過越が成し遂げられるまでは、私はもはや二度と過越の食事をすることはない」(16節)、「言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ぶどうの実から作ったものを飲むことはない」(18節)と、繰り返し別れの言葉を語られたので、弟子たちも不安になっていたことが考えられるからです。
ここで「私が試練に遭った時も」とありますけれども、この「試練」というのは〈ペイラスモス〉というギリシア語で、「誘惑」と訳すこともできる言葉です。確かに、試練と誘惑は、紙一重です。あるいは裏表です。日本語の文語訳の主の祈りには、「われらを試みにあわせず」という言葉がありますが、そこでは〈ペイラスモス〉という言葉が「試み」と訳されていました。「試み」という日本語は、ちょうどその両方、「誘惑」「試練」の両方のニュアンスを持っている、便利な、珍しい言葉です。新しい口語体の主の祈りでは、「誘惑におちいらせず」と訳しています。
いずれにしろ、弟子たちは、イエス様と共に、試練、誘惑に負けないで、踏みとどまってくれた、と言われるのです。この言葉は、ルカだけが記しているものですが、ルカ福音書が書かれた時代、初代教会の受けていた試練、誘惑が重ね合わせられているとも言われます。つまりこの言葉は、試練や誘惑を受けていた初代のクリスチャンたちへの励ましでもあったわけです。そしてさらにその報いとして、こう語られるのです。
「だから、私の父が私に王権を委ねてくださったように、私もあなたがたにそれを委ねる。こうして、あなたがたは、神の国で食卓に着いて食事を共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を裁くことになる。」ルカ22:29~30
「裁く」というのは、狭い意味での「裁く」ということではなく、「正しい方向へ導く」というような意味で捉えるほうがよいと思います。いずれにしろ、やがて神の国においては、イエス・キリストに連なる者とされるという約束なのです。一連の別れの言葉の一つです。この言葉は、先ほど申し上げたように、ルカの時代に、試練、誘惑を受けていたクリスチャンたちにとっても、またそれ以降の教会、2000年にわたる教会の人たちにとっても、試練、誘惑を受けていた人々に、大きな励ましとなったに違いありません。
(4)ヨブ記に登場するサタン
そこまでは、主イエスと12人の使徒たち全員との会話でしたが、そこから主イエスの言葉は、一人の使徒シモン、ペトロに向かいます。
「シモン、シモン、サタンはあなたがたを麦のようにふるいにかけることを願い出た。」ルカ22:31
一体、誰に願い出たのでしょうか。天の神様でしょう。この言い方は面白いです。サタンも神様の支配下にあるような言い方です。この言い方から思い起こすのは、旧約聖書のヨブ記であります。
「ある日、神の子らが来て、主の前に立った。サタンもその中に来た。主はサタンに言われた。
『あなたはどこから来たのか。』
サタンは主に答えた。
『地を巡り、歩き回っていました。』
主はサタンに言った。
『あなたは私の僕ヨブに心を留めたか。地上には彼ほど完全で、正しく、神を畏れ、悪を遠ざけている者はいない。』」ヨブ1:6~8
ヨブは神様の自慢の種であったのでしょう。しかしサタンは、それをあざ笑うかのように、「それはヨブが恵まれているからですよ」と言い返します。
「あなたの手を伸ばして、彼のすべての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずや、あなたを呪うに違いありません。」ヨブ1:11
神様は、「それならやってみろ」とサタンに許可を与えます。それは、ヨブにとっては試練であり、また「神を呪う」という誘惑でもありました。しかしヨブは、その試練と誘惑に屈しませんでした。ヨブは、そこで有名な言葉、「私は裸で母の胎を出た。また裸でそこに帰ろう」(ヨブ記1:20)という信仰の告白を発することになります。
サタンは、もう一度、今度は神の前に出て、今度は彼の体を打つことを願い出ます。しかしそれでも、ヨブは神を呪うことはしませんでした。
(5)主イエスのとりなしの祈り
さて、ルカ福音書のほうに帰りましょう。サタンは、イエス・キリストの弟子たちを「ふるいかけることを願い出た」とあります。これは、どういう意味か幾つかの解釈はあるようですが、とにかく大きく揺さぶりをかける、ということでしょう。シモン・ペトロはこれから信仰の大きな誘惑に遭うことを予告されたのです。しかし同時に、こう語られました。
「しかし、私は信仰がなくならないように、あなたのために祈った。」ルカ22:32
この言葉は、今日の聖書個所の中で最も大事な言葉です。私の説教の他のことをすべて忘れても、この言葉だけは、ぜひ持ち帰っていただきたいと思います。
「しかし、私は信仰がなくならないように、あなたのために祈った。」
シモン・ペトロのために、そのように祈られたイエス様は、私たち一人一人のためにも同じように祈ってくださっています。私たちが試練に遭う時、誘惑に遭う時、信仰を失いそうになります。なぜ自分がこういうつらい目に逢うのか。なぜ自分だけ不幸なのか。信仰を失いそうになります。しかしその時、イエス・キリストがあなたのために祈ってくださっていることを思い起こしていただきたいのです。
イエス・キリストは、この時、ご自身がとても大きな試練と誘惑を受けておられました。次回の箇所は、オリーブ山の祈り、いわゆるゲツセマネの祈りの箇所です。「父よ、御心なら、この杯を私から取りのけてください」(ルカ22:42)と祈られます。ご自身の信仰の危機です。かつて、イエス・キリストを荒野で誘惑してきたサタンが、今一度近づいてきている。そして最後の誘惑をしかけてくるのです。いわば人の信仰の心配をしている時ではない、と言ってもよいでしょう。しかし主イエスは、そうした究極の危機の時においても、まず弟子たちのために、そして名指しでシモン・ペトロのために祈られたのです。その祈りは私たちにも向けられているということを心に留めたいと思うのです。
(6)ペトロの反発
主イエスは、こう続けられました。
「だから、あなたが立ち直ったときには、兄弟たちを力づけてやりなさい。」ルカ22:32
しかしシモンは、まさか自分の信仰が、信頼が崩れるとは思ってもいません。使徒たちが「誰がいちばん偉いだろうか」という議論をしていた時も、彼は自他ともに認める一番弟子と、余裕でその議論を聞いていたかもしれません。主イエスが、「あなたがたは、私が試練に遭ったときも、私と一緒に踏みとどまってくれた人たちである」と言われた時びは、「それはまさに自分のことだ」と思っていたかもしれません。
彼は、イエス・キリストの言葉にひそかに反発するように、「主よ、ご一緒になら、牢であろうと死であろうと覚悟しております」(33節)と豪語しました。これは、彼の見栄ではなく、本気でそう思っていたのであろうと思います。しかし、見事に彼の自信は打ち砕かれることになります。そして、それを主イエスはこの時、すでに予告されるのです。
(7)初めて「ペトロ」と呼ばれた
「ペトロ、言っておくが、今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度、私を知らないと言うだろう。」ルカ22:34
この時、主イエスは「ペトロ」と呼ばれました。意外なことに、福音書の中で、イエス様が、シモン・ペトロに向かって、直接、「ペトロ」と呼びかけられたのは、ここだけなのです。ルカ福音書では、12人の弟子たちを選ばれた時、「イエスがペトロと名付けられたシモン」(ルカ6:14)という記述がありますが、直接、そう呼ばれたわけではありません。
マタイ福音書では、主イエスが弟子たちに、「それでは、あなたがたは私を何者だと言うのか」と問われたのに対して、イモン・ペトロが「あなたはメシア、神の子です」と答えた時に、主イエスがこう言われました。
「バルヨナ・シモン、あなたは幸いだ。あなたにこのことを現したのは、人間ではなく、天におられる私の父である。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てよう。」マタイ16:17~18
最初の呼びかけは、「バルヨナ・シモン」です。そしてその会話の中で「ペトロ」と名付けられるのです。ペトロとは「岩」という意味です。そこから教会が、そして世界宣教が始まっていったと言えるでしょう。しかし、名指しで面と向かって、ペトロと呼ばれることはなかった。いや恐らくあったでしょうけれども、福音書に記されているのは、ここだけなのです。
復活の主イエスが、シモン・ペトロに向かって、「私を愛するか」と言われた時も、「ヨハネの子シモン」という呼び方でした。(ヨハネ21:15、16、17)。
この直前のところでも、「シモン、シモン」と呼んでおられます。
ここでの、初めは「シモン、シモン」と言って会話を始められたのに、最後にあえて、「ペトロ」と呼び直されたのは、「お前は確かにペトロだ。私がそう命名した。しかし、ペトロが『ペトロ』(岩)でなくなる日が来る。その岩が崩れる。しかしそれで終わることはない。私が祈ったからだ。あなたは立ち直れる。そして再出発できる日が来る。」そういう含みがあったのではないでしょうか。
先の先まで見越しておられるイエス様。つまり挫折、再出発と二つ先まで見越しておられるイエス様が、未来のペトロに向かって、新たな命令をされるのです。
「だから、あなたが立ち直ったときには、兄弟たちを力づけてやりなさい。」ルカ22:32
シモン・ペトロは、この時は、どうして主イエスがそんなことをおっしゃるのか、わからなかったでしょう。しかし後でわかるようになるのです。このすぐ後で、主イエスの予言通りになってしまい、激しく泣いた後で、わかるようになるのです(ルカ23:62)。
(8)私たちも祈られている
先ほど、主イエスは、私たちのためにも祈っておられると申し上げました。そのとおりです。だとすれば、それで終わるのではなく、そこに新たな使命が与えられるのです。「あなたが立ち直ったときには、兄弟たちを力づけてやりなさい。」
私たちは、主イエスに押し出されて、この使命に生きるのです。教会とは、主イエスから、その使命を受けて押し出されて、出て行くところです。「あなたが立ち直ったときには、兄弟たちを力づけてやりなさい。」世界宣教もそのようにして始まり、その使命に促されて広がっていったということができるでしょう。