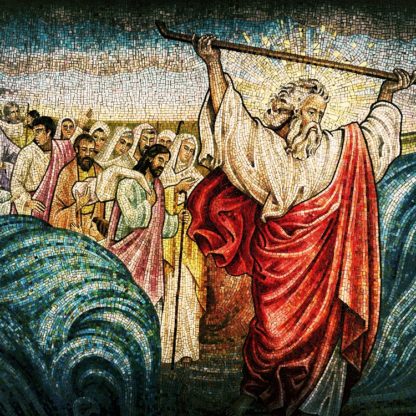2024年12月1日説教「ダビデの子」松本敏之牧師
エゼキエル書34章23~27節 ルカ福音書20章41~44節
(1)ヘルンフートの星
講壇のかけ布が緑から紫に替わり、キャンドルに一つ灯がともって、本日から待降節、アドベントに入りました。キャンドルに4つ灯がともるとクリスマスになります。鹿児島加治屋町教会では、アドベントに入ると、このキャンドルの他に、礼拝堂正面の上のほうに、イガイガの星が空中に浮かんでいるように飾られます。これは、ベツレヘムの星を象徴するものですが、この形の星は固有名詞的に「ヘルンフートの星」と呼ばれます。ヘルンフート兄弟団という教派の教会から始まったからです。ヘルンフート兄弟団というのは、毎年、ローズンゲン(日々の聖句)と呼ばれる短い聖書日課を発行していることでも知られています。ドイツの町や教会では、アドベントに入ると、このヘルンフートの星があちこちでよく見かけられるようになるとのことです。
(2)今年度のクリスマス・テーマ、「もろびとこぞりて」
さて鹿児島加治屋町教会では、今年のクリスマスのテーマを、「もろびとこぞりて」といたしました。この言葉は、「どんな人もみんなそろって」という意味です。「もろびとこぞりて」というクリスマス・テーマは、今年度の「礼拝に集い、主を賛美しよう」という年間主題にちなんで付けました。コロナ禍のさまざまな制限も取り払われた今、みんなで教会に集い、声高らかにクリスマスの賛美歌を歌って、主を賛美しましょうという思いです。もちろん、そうする中で、世界の平和のことも祈っていきたいと思います。
「もろびとこぞりて」というのは、もちろん有名な賛美歌の題でもありますす。「きよしこのよる」「いそぎきたれ主にある民」(以前の歌詞では「神の御子はこよいしも」)とならぶ三大クリスマス賛美歌と言われます。ちなみに、昨年は、「きよしこのよる 平和を祈るクリスマス」というテーマでした。「急ぎ来たれ、主にある民」(ADESTE FIDELES)も2019年度に取り上げました。(テーマとしては、この賛美歌の途中にある「歌え祝え、天使らと共に」という言葉でした。)
(3)賛美歌「もろびとこぞりて」
「もろびとこぞりて」という賛美歌について、少しお話ししておきましょう。日本語の歌詞と英語の原歌詞の意味は微妙に違うのですが、英語の原歌詞を直訳すると、以下のようになります。「世界の民謡・童謡」というサイト(Worldfolksong.com)から、引用させていただきました。
世界に喜びを 主はきませり 主を迎え入れよ みな心に神を抱くのだ 天も地も歌え
世界に喜びを 我らを統べる救世主 歌声を響かせよ 野や丘に 岩山や河川に 響き渡る喜びよ とこしえに
増やすまじ 罪と悲しみ 苦痛の種も蔓延させるまい 祝福を与えんと主はきませり 災いの種のある限り
主は真理と慈悲で世を統べ 人々に確かめさせる 神の栄光と正義を 主の愛の奇跡を
(4)作詞者フィリップ・ドッドリッジ
英語の原歌詞の作詞者は、フィリップ・ドッドリッジという人です。1702年に、イギリスのロンドンの貧しい油商人の家に生まれました。父方の祖父は牧師でしたが、ピューリタンの信仰を貫いて、英国国教会には属さなかったために、弾圧されたそうです。また母方の祖父も牧師です。プラハに住んでいたドイツ人牧師で、プロテスタントの信仰を守るためにイギリスに亡命した人であったそうです。父方の祖父同様、英国国教会に属さず、イギリス政府の国教会主義に反対したために弾圧されたそうです。フィリップ・ドッドリッジは両親を早くに失い、13歳で孤児になってしまいました。彼の才能を惜しむ人から大学進学のための奨学金の申し出があったそうですが、そのためには英国国教会に改宗する必要がありました。フィリップは二人の祖父の主義を受け継ぎ、それを受けず、会衆派の非国教徒たちによる民間の牧師養成学校に進んで、会衆派の牧師になりました。フィリップは詩の才能に恵まれ、毎週の説教の後には、その日の説教の内容を賛美歌にして、皆のよく知っている旋律に合わせて歌ったそうです。彼は貧しい村のために学校を開き、村民の教育をしながら牧会し、多くの神学の著作と400以上の賛美歌を残したそうです。「もろびとこぞりて」の歌詞は1735年12月28日に書かれて、スコットランドの賛美歌集に1745年に発表されたそうです。
さて作曲者は、メサイアで有名なゲオルグ・フリードリッヒ・ヘンデルとなっていますが、ヘンデルがこの賛美歌を作曲したわけではありません。「メサイア」の数か所からヒントを得て後世に作られた曲だということです。
この賛美歌が現在の日本語歌詞になるまで、それなりに興味深い事情があるのですが、今日は煩雑になるのでやめておきましょう。詳しいことを知りたい方は、川端純四郎さんの『さんびかものがたりⅡ』などに出ていますので、どうぞご覧ください。
(5)メシアとは
さて今日は、ルカ福音書による説教の続きとして、20章41節以下を読んでいただきました。この箇所は、イエス・キリストがエルサレムへ入られてきた一連の問答の締めくくりにあたりますが、クリスマスとも関係があります。
新約聖書の冒頭、マタイによる福音書1章1節は、このように始まります。
「アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。」マタイ1:1
イエス・キリストがダビデの子孫として生まれた、ダビデの系譜に属するということを、福音書自身が述べているのです。もっともこれはヨセフの系図であって、そのヨセフとイエスは、血のつながりはないのが面白いと思います。ですからこれは、血統図というよりは、そうした約束の系譜の中でイエス・キリストは生まれたということを告げようとしているのでしょう。
ルカ福音書20章のこれまでの論争は、復活問答、納税問答というものでした。それらは、イエス・キリストは論争を挑まれた側でしたが、それらに見事にこたえられたので、もう誰も何も言うことができません。そこでイエス・キリストのほうから、尋ねられたのでした。ルカでは、誰に尋ねられたのか記されていませんが、文脈からすれば、その前に出てくる律法学者たちであろうと思います。マルコでは群衆に向かって「律法学者たちはこう言っている」と話しかけられたことになっています。マタイでは、ファリサイ派の人々に向かって語られたようになっています。ルカでは、「どうして人々は~」となっているだけですので、あえて誰に向かって、ということよりも、私たち読者も含めて、すべての人に向かっての宣言のような意味合いがあろうかと思います。
イエス・キリストは、「どうして人々は、『メシアはダビデの子だ』と言うのか」(41節)とお尋ねになりました。メシアとは、「油注がれた者」という意味ですが、来たるべき救い主の称号の一つでした。ちなみに「メサイア」というのは、これを英語読みしたものであり、「キリスト」とはメシアのギリシア語訳です。キリストとは、イエス様の苗字だと思っている人もあるかもしれませんが、そうではなく、イエス・キリストという呼称自体が「イエスは救い主」という、一つの信仰告白だと言えるでしょう。
ユダヤの人々は、「来たるべきメシアはダビデの子孫より生まれる」と信じていたのです。例えば、先ほどお読みいただきましたエゼキエル書34章23節以下には、次のような言葉があります。
「私は彼らの上に一人の牧者を立て、彼らを養わせる。それは、わが僕ダビデである。彼は彼らを養い、その牧者となる。主である私が彼らの神となり、わが僕ダビデが彼らの指導者となる。主である私がこれを語った。私は彼らと平和の契約を結ぶ。」エゼキエル34:23~25
ダビデ王が活躍したのは、紀元前10世紀でした。預言者エゼキエルが活動したのは、紀元前7世紀から6世紀です。イスラエルは北王国と南王国に分裂し、この時代、北王国はすでに滅んでいました。そして南王国も、エゼキエルの時代に大国バビロニアに滅ぼされてしまいます。ユダヤの主だった人々はバビロンに連れて行かれ、捕囚の民となりました。彼らは、もうこれ以上落ちようがないどん底のような状況、全くの暗闇の中で、過去の栄光の時代、ダビデ王の時代を思い起こしていました。自分たちの国はいつか回復して、あのダビデ王の子孫からダビデ王に匹敵する王がメシアとして現れる。それが民族共通の希望でした。その希望を語り継いできたのです。
(6)ダビデとキリスト
一方、主イエスは先ほどのルカ福音書の中でこう続けられました。
「ダビデ自身が詩編の中で言っている。 『主は、私の主に言われた。 「私の右に座れ。 私があなたの敵を あなたの足台とするときまで。」』 このように、ダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。」ルカ20:42~44
ちょっとわかりにくい言葉です。少し説明が必要でしょう。主イエスがここで引用されたのは、詩編110編1節の言葉です。この詩編は、古来「ダビデの詩、賛歌」という題がつけられており、ダビデの作と考えられていたことが、話の前提になっています。そして「主は、私の主に言われた」の最初の「主」というのは「主なる神(ヤハウェ)」のことです。「ヤハウェなる神は、私の主に言われた」ということです。次の「私の主」というのが「来たるべきメシア」と受けとめられています。それで、「このように、ダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか」(44節)と言われたのでした。
当時の人々は、自分たちの歴史におけるダビデ王を理想化して、ダビデを超える存在は想定していません。主イエスが問題にされたのは、まさにそのところでありました。その来たるべきメシアは、ダビデをして「私の主よ」と言わせるほどのお方である。そのメシアは形の上では「ダビデの子」として来られるけれども、実質的には「ダビデの主」というべきお方である。その方はダビデの王座に着くにとどまらず、神の右の座に着く。ファリサイ派の人々は、メシアを「ダビデの子」と呼ぶことによって、かえって栄光を狭めてしまっている。メシアをダビデの子として限界づけることはできない。イエス様はそう言おうとされたのです。ですからそのメシアがダビデの王座という地上の王座に着かれるとすれば、それは高い位を意味しているのではなく、むしろ謙遜、低くなった姿を表しているというべきでしょう。
(7)アンセルムスの「神の存在証明」と「神の定義」
中世に活躍したアンセルムスという神学者(哲学者)が、1078年に『プロスロギオン』(対語録)という本を書きました。アンセルムスは、これによって「神の存在証明」をしようとしたのですが、これは、後代の数々の哲学者や神学者によって非常に大事なものとして取り上げられています。エマヌエル・カントなどもその一人です。その中でも、20世紀最大の神学者と言われるカール・バルトが『知解を求める信仰』(1931)という本の中で、この書物を取り上げ、自分の神学の「方法序説」としたことはよく知られています。
アンセルムスは『プロスロギオン』(対語録)の中で、神を指して、「あなたが、それよりも偉大なものは何も考えられ得ない何か、であることを、私たちは信じています」と書いています。まわりくどい言い方ですが、これがアンセルムスによる「神の定義」でした。神とは、「それよりも偉大なものは考えられ得ない何か」、そういう存在だ。当時の彼の論敵は、アンセルムスの、この神の定義を「何よりも偉大なもの」と言い換えて反論をするのですが、しかしそういうふうに言い換えてしまうことによって、実は本質的に違う何かに置き換えられてしまったことに気づきませんでした。「何よりも偉大なもの」であれば、「私たちの考え得るものの中で最高のもの」として、私たちの頭に入り得るでしょう。しかしアンセルムスが「それよりも偉大なものは考えられ得ない何か」と言った時、「何よりも偉大なもの」をさえ超えた方を、はるか遠くから指し示したのでした。
アンセルムスが、それによってどういうふうに神の存在を証明しようとしたのか」については少しだけ触れておきましょう。「それよりも偉大なものは何も考えられ得ない何か」は概念としては存在する。しかしそれが概念としてだけしか存在しえないのと、実際にも存在するのとを比べると、実際にも存在するほうが偉大だ。だから神は存在する」と言ったのです。
さて、この存在証明が成功しているかどうかはさておいて、話を戻しますと、「神はそれよりも偉大なものは考えられ得ない何か」というのは、アンセルムスの論敵が「何よりも偉大なもの」と言い換えてしまったものをさえも超えているというの話は、ちょうどユダヤの人々が理想の王として思い描いたダビデさえも、来るべきメシア(つまりキリスト)は、それさえも超越していたというのと似ているのではないかと思います。
(8)私たちの理想をも超えて
私たちは毎年クリスマスを祝いますが、そのことの大きさ、すばらしさを、私たちはどれほどわきまえているでしょうか。いや私たちはだれもその大きさを知り得ないのです。それは私たちのどんな待望よりも大きいからです。だから私たちの頭にも心にも入り切らない。だからクリスマスはいつも新しいのです。クリスマスは私たちの待望が粉砕される時です。それは私たちの願いが期待はずれに終わるということではありません。喜びの粉砕と言ってもよいでしょう。なぜならばより大きな、よりすばらしい出来事へと置き換えられるからです。
ユダヤの人々は、「メシアは、あのダビデ王のようにやってくる」「あのダビデ王の栄光の時代が再びやってくる」と待ち望みました。それが彼らの考え得る最高のものでありました。しかし主イエスはそれを粉砕されました。キリストはダビデの子として生まれつつ、その称号には収まりきらない、はるかに大きな方でありました。
ここでテキストの中で、問答をしかけておられる主イエスこそがメシア・キリストであるのに、それを聞いている人々はそのことに気づいていません。すぐそばでヒントを出し、揺さぶっておられるのに気づかないのです。
今日もキリストは私たちのすぐそばまで来ておられます。耳を澄ましてその福音を聞き、心の目を開いて、そのお方に気づくことができればと思います。