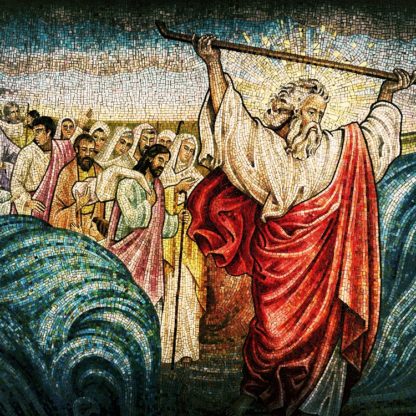2021年12月5日説教「光の源である御父」松本敏之牧師
ヨハネによる福音書1章1~4節
ヤコブの手紙1章12~22節
(1)光と星たち
講壇のキャンドルに二つ火が灯りました。待降節第二主日です。鹿児島加治屋町教会では、今年のアドベントとクリスマス、「光は闇の中で輝いている」というテーマを掲げて歩んでいます。同時に、4月から始めた聖書日課に即した聖書箇所から御言葉を聞くことも続けています。聖書日課は今週の木曜日12月6日で使徒言行録を終えて、12月7日からヤコブの手紙に入ります。ヤコブの手紙は説教で取り上げられることの少ない箇所でしょう。私がこの教会で取り上げるのも、今日が初めてかと思います。
先ほど読んでいただいた中の1章17節にこういう言葉がありました。
「あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は、上から、光の源である御父から下って来るのです。」(ヤコブ1:17)
ここで神様のことが「光の源である御父」と表現されていることは印象的です。天地創造が「光あれ」と言う言葉で始まったということを思い起こします。この「光」という言葉は、原文では複数形になっています。あえて「光たちの父のもとから」と訳している聖書もありました(田川建三訳)。神様は天体を含めた万物の創造者です。ここでそういう言い方をしているのは、天体の数多くの星たちを念頭に置いているのでしょう。そのことはそれに続く文章と関係があります。
「御父には、変化も天体の回転による陰もありません。」(ヤコブ1:17)
新共同訳聖書では、「御父には、移り変わりも、天体の動きにつれて生じる陰もありません」と訳されていました。
これも興味深い表現です。天体はどんどん変化する。移り変わる。当時の人々は星の動きに敏感でした。東方の博士たちも、新共同訳聖書では占星術の学者たちと訳されていました。星の動き、その変化によって、救い主誕生を察知し、その星に導かれて、幼子イエスのもとにたどり着いたのでした。
しかし神様はそれらを造ったお方であり、神様自身が星の光のように移り変わることはない。永遠に不変の方、昨日も、今日も、そして明日も変わらないお方だ、ということでしょう。神様こそすべての中心であり、同時に私たちを裏切らない、心変わりしないということを示しています。心を動かされない冷たい方という意味ではありません。天体の回転、天体の動きによって陰が生じます。しかし神様には陰がないというのです。
(2)夜も昼のように輝く
詩編139編の次の言葉を思い起こします。
「『闇は私を覆い隠せ。
私を囲む光は夜になれ』と言っても
闇もあなたには闇とならず
夜も昼のように光り輝く。
闇も光も変わるところがない」(詩編139:11~12)
これはこの詩人の信仰告白でありました。私たちが闇に覆われてしまうような時にも、神様は違う。「光は闇の中で輝いている」のです。「闇は光に勝たなかった。」
当時は、グノーシス主義と言って、光と闇、善と悪という二元論のような考え方がありました。二つの勢力が拮抗している。聖書もその影響を受けていますが、聖書においては、この二つは決して対等ではありません。私たちは光と闇が拮抗している戦いのもとに置かれているように見えますが、決してそれは対等ではない。見た目には闇が優勢に見えようとも、それは光に勝たないのです。善と悪が拮抗している世界にいるように見えます。見た目には悪が優勢に見えることもあります。しかし決して対等ではない。善が勝つのです。なぜならば、神様は善なるお方だからであります。
そこからもう一度、1章17節の言葉を見てみましょう。
「あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は、上から、光の源である御父から下って来るのです。」(ヤコブ1:17)
「あらゆる良い贈り物」「あらゆる完全な賜物」というのは、同じことを別の言葉で言い換えているのでしょう。すべての良い物、完全な物は神様に由来しているというのです。このことにも感謝したいと思います。
(3)神は誘惑しない
その直前に「私の愛するきょうだいたち、思い違いをしてはいけません」とあります。さかのぼって読んでみると、「誘惑」の話が出てきます。
「誘惑に遭うとき、誰も、『神から誘惑されている』と言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、ご自分でも誘惑をしたりなさらないからです。」(ヤコブ1:13)
すべてのものが神から来ているのであれば、誘惑も神から来ているのではないかという考えがあったのです。私たちもそう考ええることがあるのではないでしょう。私たちが何かの誘惑に負けてどんどん堕落してしまう時、「これも神様の計画なのか。神様がそうさせているのか」と考えてしまう。ヤコブの手紙の著者は「そうではない。神様は悪の支配下にはないし、ご自分も誘惑したりはしない」というのです。
創世記3章に記されている「この実を取って食べたらどうだ。それを食べたら神のようになれるぞ」という「蛇の誘惑」も神から来ているのではないと表現されています。神様は決して悪い方ではなく、善いことだけが神様から来ているというつながりです。そしてこう言います。
「人はそれぞれ、自分の欲望に引かれ、おびき寄せられて、誘惑されるのです。」(ヤコブ1:14)
でも、そうは言っても、誘惑する力は大きく、しかも人格的に私たちに迫って来て、私たちはどんどんそこに引き寄せられていきます。だからこそ、「私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いてください」と祈らなければならないのです。自力で脱出できると思うほど、悪の力を甘く見てはいけないと思います。
(4)試練と誘惑(ペイラスモス)
さらに遡って興味深いことに、試練についても述べられています。「試練と誘惑」という題が付けられています。実は「試練」と「誘惑」は元のギリシア語では同じ言葉です。「ペイラスモス」という言葉です。日本語に「試み」という言葉がありますが、これはギリシア語のニュアンスと似ていて、「誘惑」と「試練」の両方のニュアンスがあるのではないでしょうか。どちらかと言うと、もちろん「誘惑」に近いですが、「試練」の「試」という字を使っています。文語体の主の祈りでは。「我らを試みに遭わせず、悪より救いいだしたまえ」という言葉でした。
神は「誘惑」は与えられないけれども、「試練」は与えられる。特に愛する者には試練を与えられるということも述べられています(ヘブライ12:5以下)。
「試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者とされ、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです」とあります。その前の2節でもこう述べられています。
「私のきょうだいたち、さまざまな試練に遭ったときは、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生まれることを、あなたがたは知っています。あくまで忍耐しなさい。そうすれば、何一つ欠けたところのない、完全で申し分のない人になります。」(ヤコブ1:2~4)
この言葉はパウロの有名なローマ5章3節以下の言葉をほうふつとさせます。
「そればかりでなく、苦難をも誇りとしています。苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を、品格が希望を生むことを知っているからです。この希望が失望に終わることはありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちに注がれているからです。」(ローマ5:3~5)
ただし、神様が私たちを成長させるために与えられた「試練」を、サタンが横から「誘惑」として利用することはあるかもしれません。実際、何かが起きた時、その真っただ中にある時には、それが「試練」であるのか「誘惑」であるのか、わからないのではないでしょうか。だからギリシア語の「ペイラスモス」も日本語の「試み」も両方のニュアンスがあるのかもしれません。私たちは、神様はよいお方であり、あらゆる良い贈り物、完全な賜物こそが神から来るということをわきまえておきたいと思うのです。
(5)公同書簡
さて、ヤコブの手紙について、いつもしていますように、少し概説的なことを述べておきましょう。まず聖書の中の分類としては、公同書簡と呼ばれます。公同書簡の公同というのは、「公同」というのは「公」という字と「同じ」という言葉の「同」です。使徒信条の中に「我は聖霊を信ず」の後、「公同の教会(を信ず)」という言葉がありますが、その「公同」で、もとのラテン語では「カトリカ」(カトリック)という言葉です。なぜそう呼ばれるかと言えば、これは本来手紙というよりは、最初から教会での勧めとして読まれることを前提としているような書物だからです。ヤコブの手紙、ペトロの手紙一、ペトロの手紙二、ヨハネの手紙一、ヨハネの手紙二、ヨハネの手紙三、ユダの手紙、この7つの文書が公同書簡です。
(6)執筆年代、著者
次に、著者および執筆年代ですが、1章1節に「神と主イエス・キリストの僕ヤコブが、離散している十二部族に挨拶いたします」とありますから、著者は「ヤコブ」という名前の人ということになりそうです。新約聖書の中に「ヤコブ」という名の人は、主イエスの弟子のヤコブを含めて、何人か出てきます。一番ありうるのは「主の兄弟ヤコブ」(マルコ6:3等)であろうと言われますが、それにしては時代があわない。
というのは、この手紙が書かれた背景がパウロの「信仰義認」という教えが前提になっているからです。それよりも後で書かれたことがわかるのです。大体紀元1世紀の終わりか2世紀の初め頃であろうと思われます。その頃の教会の指導者が、主の兄弟ヤコブの名前を借りて、その権威のもとに、教会で広く読まれるために書かれたのだろうと言われます。ですから本当の著者名はわからないのですが、便宜上、ヤコブと呼ばせていただきます。
(7)パウロ書簡との補完関係
では一体何のために、どういう動機でこの手紙は書かれたのでしょうか。先ほど申し上げたように、パウロの手紙の中心にあった教えは、信仰義認ということでしたが、その教えを誤って、自分たちに都合よく理解する人たちが出てきたのです。「信仰義認」というのは、「人は行いによってではなく、ただ信仰によって義とされる」ということです。より丁寧に言えば、「律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされる(救われる)」という教えです。パウロはそのことを繰り返し述べています(ローマ3:28、ガラテヤ2:16など)。
一方、ヤコブの手紙には、こういう言葉が出てきます。「人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。」(ヤコブ2:24)
この言葉だけを読むと、パウロが言ったことを否定しているように聞こえかねませんが、パウロとヤコブはアクセントこそ違え、矛盾することを言ったわけではありません。むしろそれが誤解されないために、補完関係にあると言えようかと思います。パウロも信仰の実践としての行いは大事だと考え、その大切さも述べていますが、誤ったパウロ主義者、あるいは都合の良いパウロ主義者たちは、信仰を強調するけれども、それに実践的な行動が伴っていませんでした。
(8)行いを重要視するヤコブ
そういう人たちに対して、ヤコブはこういうのです。
「私のきょうだいたち、『私には信仰がある』と言う者がいても、行いが伴わなければ、何の役に立つでしょうか。もし、兄弟か姉妹が、着る物もなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなたがたの誰かが、その人たちに、『安心して行きなさい。暖まりなさい。存分に食べなさい』と言いながら、体に必要なものを与えないなら、何の役に立つでしょうか。同じように、信仰もまた、行いが伴わなければ、それだけでは死んだものです。」(ヤコブ2:14~17)
そう言い切るのです。これが「ヤコブの手紙」の中心的テーマであると言ってもよいでしょう。ヤコブは、別の言葉でこういうふうにも言います。
「御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけの人であってはなりません。」(ヤコブ1:22)
ヤコブには神学がないと言われることがあります。その筆頭にいるのが宗教改革者のマルチン・ルターです。彼は、パウロの「信仰義認」の教えを原動力として、宗教改革に突き進んでいった人ですから、一見、それに反対しているかに見えるヤコブの手紙を、価値のないものとして、「わらの書簡」と言って批判しました。
しかし私は、「信仰は行いを伴ってこそ、本当の信仰だ。行いの伴わない信仰は、信仰とは言えない」というのは、立派な一つの神学(キリスト教の教え)であると思います。
ヤコブはパウロ以降、時代が下るにつれて、信仰が堕落していくこと、教会が世俗化していくことを悲しんでいたのです。そして裕福な人が自分たちの信仰だけで完結して、貧しい人をないがしろにしていることも批判いたしました。
このことは現代の私たちの教会に対する批判であると言ってもよいのではないでしょうか。
(9)現代の私たちに対するチャレンジ
この手紙の宛先は、先ほど引用した1章1節では、「神と主イエス・キリストの僕ヤコブが、離散している十二部族に挨拶いたします」という言葉で始まっていました。「離散している十二部族」というのは、第一義的には、「ユダヤ・パレスチナ以外の地域に住んでいるユダヤ人たち」(ディアスポラのユダヤ人たち)が考えられます。次に、「異教社会に散在していたユダヤ人キリスト者たち」ということも考えられます。さらには、そうしたことも超えて、この世に住むすべてのキリスト者、クリスチャンに向けて書かれていると読むこともできるでしょう。もともとこのヤコブの手紙は、そのような人々に勧告的文書として読まれることを想定しているのです。
そのことは、ひいては現代に生きる私たちも含めて、すべてのクリスチャン、すべての教会に向けて語られている、ということができるのではないでしょうか。自分たちだけで完結してしまっていないか。この世の貧しい人たち、教会の外で困窮している人たちにも目を向けなさい。持てるものを分かち合いつつ、共に生きていく者になりなさい。
すべての良い贈り物は光の源なる父のもとから来ることを感謝し、それを受けながら分かち合う者として生きていく。そのような思いで、この時期を過ごしていきましょう。