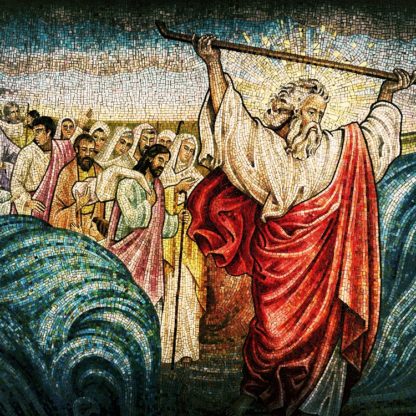2021年10月31日説教「大祭司イエス」松本敏之牧師
ヘブライ人への手紙4章14~5章10節
(1)宗教改革記念日
10月31日は宗教改革記念日です。今年はちょうど日曜日となりました。マルティン・ルターという人物が1517年の10月31日にウィッテンベルク城教会の扉に95か条の提題(質問書)を貼り、当時の(カトリック)教会に抗議(プロテスト)しました。このことから、10月31日はプロテスタント教会の誕生日とも言われるようになりました。
当時の教会が、「贖宥状」(免罪符と言われてきたが、正確ではない)を発行してお金を集めるなど、ある意味で腐敗しておりましたので、ルターが抗議したような形になりました。ただしカトリック教会でもその後教会の刷新運動が起こることになります。
今日、特に20世紀の半ば以降は、エキュメニカルな時代、カトリック教会とプロテスタント教会が共に歩む時代になりました。その20世紀の総決算のような形で、1999年10月31日に、世界ルーテル連盟とローマ・カトリック教会は、「救いは信仰による」と確認する共同宣言に署名し、教義上の根本問題において歴史的な和解をしました。この出来事は、世界のエキュメニカル運動の大きな一歩でした。
(2)信仰のみ
ちなみに宗教改革の精神というものを、私はわかりやすく、覚えやすいように、三つの「のみ」と説明するようにしています。三つの「のみ」というのは、「信仰のみ」「聖書のみ」「キリストのみ」ということです。
「信仰のみ」というのは、「救い」に関してです。「義認」(「義と認められること)と言ってもよいです。ルターの時代の教会では、信仰だけではなく、行為、つまりよいことをすることによって義と認められるとして、いわゆる贖宥状を教会が発行していたのです。それも(つまり教会への寄付)よい行いの一つとされていた。それに対して、ルターは、それは救いとは関係がない。行いも大事だけれども、私たちは救われるために、義とされるためによい行いをするわけではない。ルターは、私たちが救われるのは「信仰と行為」によってではなく、「信仰のみ」によってであるとしたのです。これが一つ目、宗教改革の根本精神です。
(3)聖書のみ
二番目は「聖書のみ」ということです。これは、「信仰の規範」についてです。それまでは、私たちの信仰は「聖書と伝統」に基づくと言われていました。「伝統」というもの中には、イエス・キリスト以降の教会の歴史、教会の権威を含んでいました。この中には、さまざまな聖人伝説など、聖書と関係のないものも含まれてきます。それに対し、宗教改革者たちは、いや信仰の規範は「聖書のみ。聖書に帰れ。その後の教会の歴史は信仰の規範にはならない」と言ったのです。
しかしプロテスタント側のこの主張は、ある矛盾をはらんでいます。なぜかと言えば、「聖書のみ」と言っても、「聖書」という書物が今のような形で、66巻として最初から存在していたのではないからです。つまり、多くの文書の中で、どれが聖書であり、どれが聖書にふさわしくないかを決めていったのは、教会会議なのです。教会の権威なのです。その意味では、教会の伝統を抜きにして「聖書のみ」とは言えないということになります。
(4)キリストのみ
第三は「キリストのみ」ということです。これは一般的には「万人祭司」、より正確には全信徒祭司制というものです。父なる神様と私たちの間に立つ仲保者は、イエス・キリストだけであって、それ以外はすべて平等、特別な人はいないということです。当時のカトリック教会(現代のカトリック教会でもそういう傾向がありますが)、母マリアや聖人などを特別視していました。特別なのは、イエス・キリストだけです。そういう意味で「キリストのみ」というふうに言い変えました。
「洗礼名」を付けるというのも「その聖人に守られる」という由来がありましたので、プロテスタントでは洗礼名を付けることはなくなりました。あるところもあります。聖公会では洗礼名があります。
またカトリックでは聖職者という言い方をしますが、プロテスタント教会では特別な聖職者はいない、ということで、一般的には「教職」「教師」という言葉を使います。そういう言葉の使い方にも、「牧師とは聖職者、特別な存在ではないで」という理解が背景にあるのです。私たちプロテスタント教会からすれば、ローマ教皇といえども、私たちと同じ人間だということになります。特別なのはイエス・キリストのみ、ということになります。これだけがカトリックとプロテスタントで少し違うと言えるかもしれませんが、今は、違いは違いとして認め合いつつ、同じイエス・キリストを主と仰ぐ共に歩む決心をしています。
これらの三つのもとにある精神を突き詰めて考えれば、カトリック教会にとっても大事な信仰の原点を指し示していると思います。この宗教改革の精神に立ち返ることよって、私たちも信仰を新たにしていきたいと思います。
(5)ヘブライ人への手紙について
さて、鹿児島加治屋町教会独自の聖書日課、先週からヘブライ人への手紙に入りました。今日は、ヘブライ人への手紙の中から、先ほどの宗教改革にも関係する部分、4章の終わりから5章にかけての「大祭司キリスト論」と呼ばれる部分をお読みいただきました。私たち人間には誰も特別な祭司はいない、すべてのクリスチャンが等しく祭司であるということは、言い換えれば、イエス・キリストのみが特別な祭司であるということはすでに述べました。そのイエス・キリストがどのような祭司であるかということを述べたのがこの部分なのです。
その前に、ヘブライ人への手紙がどのような文書であるのかについて、概説的なことをお話しておきましょう。
ヘブライ人への手紙は、手紙というよりも、説教、あるいは勧告の文書というような性格のものであり、他の手紙のように、手紙の冒頭の宛先や差出人、挨拶の言葉もなく、いきなり内容に入っていきます。
また新約聖書の中でも特に卓越したギリシア語で書かれており、著者はギリシアの教育を受けたユダヤ人クリスチャンであろうと思われます。ただし誰であるかはわかりません。書かれたのは、恐らく紀元80年から90年の間と考えられます。
最初からいきなり、こういう荘重な言葉で始まります。
「神は、かつて預言者たちを通して、折に触れ、さまざまなしかたで先祖たちに語られたが、この終わりの時には、御子を通して私たちに語られました。神は、御子を万物の相続者と定め、また、御子を通して世界を造られました。御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の現れであって、万物をその力ある言葉によって支えておられます。そして、罪の清めを成し遂げて、天の高い所におられる大いなる方の右の座に着かれました。」(1:1~3)
これはヘブライ人への手紙独特の「御子キリスト論」と呼ばれるものであって、著者の神学的主張が明らかにされます。そこから次第に大祭司キリスト論へと導かれて、この書物独特の思想が述べられることになります。その中心部分が、今日読んでいただいた箇所なのです。
この書物の最初の読者(聴衆)は、どのような人たちであったのか。迫害の危機に襲われていたのでしょう。そのような状況にあっても、先立ちゆくキリストをしっかりと見つめて、望みと忍耐をもって前進するようにといういう勧めを著者はしています。信仰に疲れたキリスト者(クリスチャン)を力づけて、新しい情熱へと駆り立てるために新しい神学を展開するのです。
(6)天から来られた神の子
さて、その新しい神学がどういうものであるか見てみましょう。先ほど読んでいただいた4章終わりから5章にかけての「大祭司キリスト論」と呼ばれるところに、その真骨頂があります。
4章14節で、こう述べられます。
「さて、私たちには、もろもろの天を通って来られた偉大な大祭司、神の子イエスがおられるのですから、信仰の告白をしっかり保とうではありませんか。」(4:14)
この最初の文章で、イエス・キリストが天から来られた神の子であることを確認します。さらりと読み過ごしそうな言葉ですが、これを踏まえていることが大事なのです。
通常、「祭司」というのはあくまで人間です。そして人間の代表として、人間の側に立って、神様にとりなしの祈りをする役割をもった存在です。「大祭司」はその祭司の中の最高の祭司です。そしてここから後、イエス・キリストがそのように人間の側に立ってくださったことが述べられるのですが、その方は神に等しい方であったこと、元来は神の側におられるべき方であったということです。神の側におられるべき方が完全に人間の側に立ってくださったということが重要です。神の子としての資格がある、つまり神と同等であることと、完全に人間の側に立ってくださったということ。普通は結び付かない、この二つが一つになっているのが大祭司キリスト論なのです。
(7)私たちと同じ人間イエス
それゆえに、4章15節でこう続けます。
「この大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪は犯されなかったが、あらゆる点で同じように試練に遭われたのです。」(4:15)
ですから宣教活動の最初に、荒れ野で最も厳しい誘惑に遭われたこともそういう背景があります。私たちは、「イエス・様は神の子だから、自分が十字架にかかって死ぬという定めも、超然と受け止めておられたのだろう」と思いがちですが、決してそうではありませんでした。5章7節では、こう記されます。
「キリストは、人として生きておられたとき、深く嘆き、涙を流しながら、自分を死から救うことができる方に、祈りと願いとを献げ、その畏れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。」(5:7)
これは、ゲツセマネの祈りを指しているのでしょう。ただし、多くの方は、「あれ、あの時、イエス・キリストが献げられた祈りは『父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください』(マタイ26:39)、『父よ、御心なら、この杯を私から取りのけてください』(ルカ22:46)という祈りではなかったか。その意味では、その祈りは聞き入れられなかったのではないか」と疑問に思われるかもしれません。
ここでカギとなるのは、「自分を死から救うことができる方に」という言葉の解釈です。これは「十字架の死を免れさせる」という意味で理解するとわからなくなる。そうではなく、「(すでに起こっている)死の状態から救う」こと、つまり「復活と高挙」を指しているのです。
この時、イエス様が苦しまれたのは、単に死ぬのがこわかったということではなかったと思います。今、自分の目の前に備えられている道が、本当に父なる神様の御心なのだろうか。そのことに躊躇があったのではないでしょうか。悪魔がそばでささやきます。「本当にそれが神様の考えなのか。そんなのばかげているじゃないか。神の子だったら、もっと堂々と相手にそのことを知らせてやればいいじゃないか。」「父よ、わたしをこの時から救ってください」(ヨハネ12:27)というのは、そのような悪魔の誘惑から救ってください、ということでもあったのでしょう。イエス・キリストは、その試練、誘惑に負けてしまったのではなく、それに打ち勝っていくのです。
いずれにしろ、イエス・キリストは「まことの神」であると同時に、「まことの人」でもあったということは、神と等しい方、神の資格をもった方が、まことの人として、私たちと同じ立場に立たれたということです。苦しみも悲しみもなく、超然としているというのはまことの人ではありません。
ヘブライ人への手紙の著者は、ただ「罪を犯されなかった」という点だけは違うと付け加えています。あとはすべて私たちと同じ経験をされた。試練にも遭われたということです。
(8)讃美歌第一編532「ひとたびは死にし身も」
この後、『讃美歌』第一編の532番「ひとたびは死にし身も」という歌を歌います。この曲は私の愛唱歌でもありましたので、『讃美歌21』に収められなかったことを残念に思っています。2節はこういう歌詞でした。
「主の受けぬこころみも 主の知らぬ悲しみも
うつし世にあらじかし いずこにもみあと見ゆ」
イエス様が受けなかった試練や、イエス様が知らなかった悲しみは、この世には存在しない。どこへ行ってもイエス様が通った跡がある。そういう言葉です。
私たちは、時々「どうして私がこんな試練を受けなければならないのか。」「どうしてこんな悲しい思いをしなければならないのか」と思うことがあるのではないでしょうか。「どうして自分なんだ」と思うこともあるでしょう。しかしどんな試練も、どんな悲しみも、どんな苦しみも、どんな迫害も、どんな病も、イエス・キリストもすでに経験しておられた。「自分だけ、どうして」と思っていたけれども、そこにはイエス様の通られた跡があった、というのです。
私は一人で苦しんでいるのではない。私は一人で悲しんでいるのではない。この試練、悲しみを、イエス様はすでに知っていて、共有してくださっている。そのことに、私たちは限りない慰めと救いを見出すのではないでしょうか。