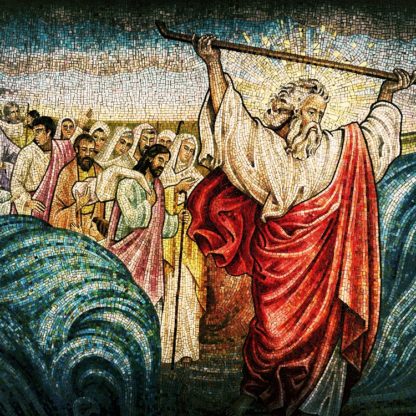2021年8月8日説教「信仰の原点」松本敏之牧師
ガラテヤの信徒への手紙1章1~10節
(1)ガラテヤの信徒への手紙
4月より始めました鹿児島加治屋町教会の聖書日課、皆さんは、いかがでしょうか。続けて読んでおられるでしょうか。先週発行された「からしだね」8月号の第3面には、皆さんそれぞれの読み方や感想が書かれていて、興味深くお読みしました。
さてこの聖書日課、昨日からガラテヤの信徒への手紙に入りました。このガラテヤの信徒への手紙は、教会の基礎は一体何であるか、教会は一体どこに立っているのか、そして私たちの信仰はどこに立つのかということを、教えてくれる大切な書簡であります。
宗教改革者ルターも、そのことを絶えず確認するために、このガラテヤの信徒への手紙を熟読し、愛したと言われております。ルターは愛妻家であったことで知られていますが、そのルターがこの手紙のことを「わが妻」と呼んでいたそうであります。
最初にこの手紙の背景などについて、いわゆる緒論のようなことを申し上げておきます。まずこの手紙の著者でありますが、今日のテキストにも出てきますように、使徒パウロであります。新約聖書の中にはパウロの名前によって書かれた手紙がたくさんあるのですが、実はそれらすべてがパウロの手によるものではないということがわかっています。
そうした中にあっても、ガラテヤの信徒への手紙は、すべての学者が、確実にパウロの手によるものだと認めるものです。しかもローマの信徒への手紙と並んで、パウロの思想、神学というものが最もよく表れており、同時にローマの信徒への手紙に比べれば、短く簡潔にそれを語っていますので、キリスト教の教理を学び、確認する上で、格好のテキストであるということができるでしょう。
パウロは、三回ほど大きな伝道旅行をしています。この手紙は、第三次伝道旅行の途中、約2年間エフェソに滞在していた時に書かれたであろうと言われています(使徒19:1、8~10、20:31)。執筆時期としては紀元後54年頃と推定されます。使徒言行録で、ガラテヤ教会に対するパウロのそれまでのかかわりをたどってみますと、この手紙を書く前に彼は二度にわたってガラテヤ地方を訪れて、伝道したことがわかります(使徒言行録16:6、18:23)。ちなみにガラテヤというのは、現在のトルコの首都アンカラとその周辺であっただろうということです。聖書協会共同訳聖書の巻末の地図を見てみましょう。最後の「12パウロの第三次宣教旅行とローマへの旅」の右上近く7Bのところに茶色い字で「ガラテヤ」という地名が記されています。
(2)ガラテヤの諸教会
こういうふうに始まります。
「人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストと、この方を死者の中から復活させた父なる神とによって使徒とされたパウロ、ならびに、私と共にいるきょうだい一同から、ガラテヤの諸教会へ。」(1:1~2)
この部分は手紙の発信人と受取人が誰であるかについて、述べています。発信人の方は随分長いのですが、これについては後でお話しします。受取人の方は、「ガラテヤの諸教会へ」とだけ記されています。これだけを読みますと、何とも思わないかも知れませんが、他のパウロの手紙と比べてみますと、この書き方は非常に例外的であることがわかります。たとえばローマの信徒への手紙ではこうなっています
「ローマにいる、神に愛され、聖なる者として召されたすべての人たちへ。」(ローマ1:7)
またコリントの信徒への手紙の一ではこうなっています。
「コリントにある神の教会と、キリスト・イエスにあって聖なる者とされた人々、召された聖なる者たち、ならびに至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めるすべての人々へ。イエス・キリストは、この人たちと私たちの主です。」(コリント一1:)
フィリピの信徒への手紙では、こうなっています。
「フィリピにいるキリスト・イエスにあるすべての聖なる者たち、ならびに監督たちと奉仕者たちへ。」(フィリピ1:1)
パウロの相手に対する愛情がにじみ出ているような書き方です。それらに比べてみますと、いかがでしょうか。「ガラテヤの諸教会へ。」実に素っ気ない書き方です。
実はこのガラテヤの信徒への手紙は、「戦いの手紙」と呼ばれることもあるのですが、厳しい、困難な状況に直面する中で書かれました。あいさつの後、手紙の本文の書き出し部分で、彼はいきなりこう書くのです。
「キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなたがたがこんなにも早く離れて、ほかの福音に移って行こうとしていることに、私は驚いています。」(1:6)
挑発的な言葉です。いきなり手紙の書き出しでこう書かれたら、いかがでしょうか。皆さん、こういう手紙を受け取ったら、どきっとするのではないでしょうか。けんかを売っているようで、「何だ、こいつは」ということになりかねません。こうしたところからも、パウロは穏やかならぬ心で、この手紙を書き記していることが伺えます。とても「ガラテヤにいる、神に愛され、聖なる者として召された人たちへ」とか、「ガラテヤにある神の教会へ」とか、書くことができなかったし、書く気にもなれなかったのでしょう。
(3)人ではなく、神によって
宛名が素っ気ないのに対して、書き手である自分については不釣り合いなほど詳しく記しています。そしてその中に、自分がどういう者として書いているのかという、パウロの毅然とした態度がよく表れています。
日本語では語順が逆になってしまいますが、原文では、最初にはっきり「パウロ」と自分の名前を名乗り、そして「使徒とされた」という言葉が続きます。「使徒」というのは「遣わされた者」という意味の言葉です。パウロは「自分は使徒である」と明言するのです。パウロがこの手紙を書き送った背景には、「パウロが使徒であるということはどうもあやしいぞ」という風潮が、あるいはそういう意見が多数あったのです。使徒の中にも暗黙のランク付けがありました。パウロは上の方ではありません。一番上はもちろん、ペトロ、そしてペトロを筆頭にするイエス・キリストの直弟子たちです。直接生前のイエス・キリストから教えを受け、肌で触れ合った人々です。
しかしパウロは生前のイエス・キリストを知りません。さらに悪いことには、彼はもともとクリスチャンに対する熱心な迫害者でありました。「イエス・キリストを救い主などと言いふらす者はけしからん。神の意志に反している。神を冒涜している」。そう信じて、パウロは迫害したのです。「そんな過去をもっている奴がイエス・キリストの使徒だというのだから、どうもあやしいものだ」ということでしょう。
(4)割礼によるのではなく
さらに彼の説くメッセージは、イエス・キリストの直弟子たちの語るメッセージとは一線を画しておりました。ペトロたちは、ある意味でユダヤ教の枠の中でしかイエス・キリストの教えをとらえることはできなかったようです。ユダヤ教が守ってきた律法を守りながら、それにイエス・キリストの新しさを付け加えたようなメッセージを語っていたのです。いわばユダヤ教イエス派のようなものです。パウロはもっと大胆に、イエス・キリストによって何が新しくされたのかを語りました。
ひとつだけ典型的な例をあげますと、ユダヤ人には割礼という習慣がありましたが、異邦人がクリスチャンになる場合に、ペトロたちは「割礼を受ける必要がある」と考えました。しかしパウロは「それは必要ない」と言ったのです。もちろんパウロは、ユダヤ教についてよく知っています。ペトロなどよりずっと専門家でありました。有名なガマリエルという律法学者の門下生でありました。だからこそ逆に、ユダヤ教の教えの中で、何が本質的に重要で、何が二次的なことであるかを判断できたとも言えるでしょう。何をキープし続け、何を刷新しなければならないのか、イエス・キリストによって、何が変わったのか、それを鋭く見抜く力をもっていたのです。
(5)パウロの回心体験
しかしそうしたパウロの経歴も、彼の劇的な回心なくしては、生かされることがなかったでしょう。彼の回心については、使徒言行録の9章に詳しく記されています。彼はその時の出来事を何度も何度も自分の出発点として証し続けました。使徒言行録には、この9章の他に2箇所、その話が記されています。今日はその最後の箇所で、その時、パウロに何が起こったのかを確認したいと思います。使徒言行録の第26章12節以下です(聖書協会共同訳聖書では新約の261頁)。パウロは当初、サウルと名乗っていました。
「こうして、私は祭司長たちから権限を委任されて、ダマスコへ向かったのですが、その途中、真昼のことです。王よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽よりも明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。私たちが皆地に倒れたとき、『サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。突き棒を蹴ると、痛い目に遭うものだ』と、私にヘブライ語で語りかける声を聞きました。そこで、私が、『主よ、あなたはどなたですか』と申しますと、主は言われました。『私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がれ。自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そして、これから私が示そうとしていることについて、あなたを奉仕者、また証人にするためである。私は、あなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに遣わす。それは、彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち帰らせ、こうして彼らが私への信仰によって、罪の赦しを得、聖なる者とされた人々と共に相続にあずかるようになるためである』」。(使徒言行録26:12~18)
パウロは復活のキリストとこのように出会い、それに基づいて宣教をしていきました。これがパウロのよって立っていたところであり、パウロがイエス・キリストを語る根拠でありました。当時、最も権威があったのは、ペトロを中心としたエルサレム教会でありました。そのエルサレム教会から派遣されたのであれば、その権威を背景にそれなりに敬意を持って受け入れられたでありましょう。「本家からのお墨付きだ」ということになったでしょう。またペトロなど権威ある人によって任命されていたのであれば、やはり敬意をもって受け入れられたことでしょう。
ところが「あのパウロという男は一体何者だ。誰が彼のことを保証してくれるのだ」というような問いがうずまく中で、パウロは毅然と書き始めるのです。
「私が使徒であるのは、人々からでもなく、人によってでもない。イエス・キリストと、キリストを死者の中から復活させた父である神とによるのである」と。ここでパウロは、復活のキリストにのみ言及しています。そこには「自分は確かに生前のイエス様は知らない。しかし復活したイエス・キリストを知っている。それで十分ではないか。いやそれこそが最も大切なことではないか」という思いが表れているのではないでしょうか。
この意味において、21世紀に生きている私たちと、使徒パウロは、同じ地平に立っているということができるでしょう。私たちのうち誰一人として、ペトロのように生前のイエス・キリストを知る者はいないからです。しかしそれでもなお、復活のキリストに出会い、キリストによって生かされているならば、「キリストの使徒」と名乗ることがゆるされるのです。
パウロはそう語ることによって、「自分を使徒として立てているのは、エルサレム教会のような、ある種の人間的な権威ではないのだ」と宣言するのです。少なくともエルサレム教会がその権威を独占することをきっぱりと拒否したのです。
それは、宗教改革者のルターがよって立ったところでもありました。彼はローマ・カトリック教会が絶対的な権威をもっていた時代にあって、「このローマ・カトリック教会が、人を使徒として立てるのではない。イエス・キリストと、キリストを復活させた神が、人を使徒として立てるのである。」そのことを発見したルター、その厳粛な事実に気づいたルターは、ローマ・カトリック教会の権威と決別し、宗教改革へと進んでいくのです。
(6)独善的になる可能性
ただし問題はそれほど簡単ではありません。人間的権威を否定することで、問題は解決しません。そもそもどうして人間的権威を求めるかというと、私たちはいつもそれが本物であるかどうかの保証が欲しいからでしょう。ある種の基準を設けて、「この人は大丈夫」という保証をするのです。日本基督教団の場合でもそうです。牧師になるためには、教師試験というものを受けなければなりません。それによって、その人がある審査を経たものであることを保証し、教師であることを認めていくのです。
ただしそのことは、その人の言っていることが正しいという保証にはならないでしょう。教団の牧師だと認定してもらうことは、ある種の目安にはなるかも知れませんが、その人が間違った教えを語らないという保証ではあり得ないわけです。
そういう意味では、私たちも、目に見えるひとつの基準で、牧師を認定しながらも、本質的にはパウロと同じところに立っていると言えます。
「なぜある種の権威による認定を求めるか」というと、そうした権威を取り外してしまった時に、「それでは何でもいいのか」という混沌に陥りかねないからでもあります。そして「人によってでもなく、人を通してでもなく」という時に、私たちはしばしば自己絶対化に陥ることが多いのです。「私は神によって使徒とされた」と誰かが言った場合、いかがでしょうか。他の人にはそれを直接証明する道は何もありません。こうした主張がなされるときに、私たちは逆に自分を絶対化して、誰か他者と対話することが不可能になってしまうことがあるでしょう。個人的権威を押しつけることになってしまいがちであります。
宗教者の対立が、世俗的世界の対立よりも根が深いのは、まさにそこにこそ問題があるからではないでしょうか。諸宗教間の対立にとどまらず、同じキリスト教内での対立、いや同じ教派内、たとえば日本基督教団の中でも、いやそこにおいてこそ熾烈な形で、「自分たちの方にこそ、正しさがある。神が味方している」と譲らず、それぞれが自己絶対化し、硬直していくことがしばしば(あるいは時々)、あるのです。またカルト宗教の教祖も、「自分は神からの啓示を受けて、メシアとして立てられた」と言うでしょう。
(7)自分をも絶対化しない
私は、「人によらず、神による」という時、「人」という中に「自分」も含んでいなければならないと思います。「人によらず」と言いながら、かえって自分を絶対化しているのであれば、何にもならないでしょう。
しかし考えてみれば、それは大変なことを語っているのではないでしょうか。すべての人間的保証を放棄して立とうとすること、何か空中に放り出され、めまいを起こすような事柄です。自分のよりどころを自分で振り払うような決意です。自分も含めて、一切の人間的足場に頼らない。ただキリストを見つめ、そのキリストを復活させた父なる神を見つめ、そこにのみ自分の言葉のよりどころを置く。ある人は(加藤常昭牧師ですが)、これを「信仰のめまい」と呼んでいました。私たちが確かだと思って立っていたところが、実は確かではないことに気づいた。そしてもっと確かなもの、新しいものを求めて出ていこうとする、そうした飛び出しのようなものが、この言葉の中にはあるのではないかと思います。
これはいつも新たにチャレンジされ、いつも新たに検証されていかなければならないことでしょう。つまりパウロがこう言ったからといって、それはその後ずっとそうだということにはなりません。今日の私たちにおいても、神によって立てられたと言っても、それを客観的な形では証明するものは何もないのです。その語っている中身だけが、あるいはその言葉が指し示しているものだけがその真実性を示していると言えるでしょう。それを保証するのは、その言葉の中身しかない、外的な保証はないということです。
パウロは自分が伝道者となったことは、バルナバをはじめとする、多くの人のおかげだということを十分知っていたと思います。パウロが登場した時、バルナバは、パウロよりもランクが上だと認められていました。しかしそれでもあえて、自分が使徒であるのは、人によってではなく、神によるのだと言い切るのです。
ガラテヤの信徒への手紙は、私たちに信仰の原点、教会の原点を指し示してくれる大事な書簡であります。これに聞きながら、イエス・キリストの福音を聞き、理解していきたいと思います。